このたびURLを下記に変更しました。
お気に入り等に登録されている方は、新URLへの変更をお願いします。
新URL http://blog.drnagao.com

日本医師会と平穏死
2014年01月24日(金)
こんなこと書いてええんやろか、と思いながら書いてしまった。
日本医事新報の1月号への連載記事。
医事新報1月号 平穏死シリーズ最終回
“平穏死”と日本医師会、大学病院
長尾和宏
平穏死できる病院はまだ僅か
昨年末に、末期がんで危篤状態であるとの連絡を受けた2人の知人をお見舞いした。1人はがん診療拠点病院で、1人は一般病院だった。偶然、2人とも膵臓がんの末期で、1人は50歳代、1人は80歳代だった。久々に吸いこんだ大病院の空気は、普段在宅で吸っている緩んだ空気とはかなり違っていた。というのも2人とも、見事に管だらけになっていた。酸素、点滴ルート2本、心電図と血圧計モニター、膀胱カテーテル等。久々に“スパゲテイ症候群”という言葉を思い出すとともに大きなショックを受けた。2人とも過剰輸液により顔は腫れあがり、心不全に伴うと思われる呼吸困難を呈していた。詰所にはたくさんの看護師や医師がいた。しかししばし黙って観察していると点滴は交換すれど、患者さんと会話したスタッフはゼロ。1人は、意識不明とのことだったが、顔を近づけると充分に会話が可能であった。しかし痰が多く、息苦しさのため会話しにくいようだった。
思わず看護師たちに平穏死を知っているか、と聞いてみた。「ヘイオンシ??」。どうやら変なオッサンと間違われているようだった。「この人の呼吸困難は簡単に改善できるし、食事も可能なんだ」とも言ったが、若い研修医は怪訝な顔をしていた。一時的にせよ状況を改善させるのは実に簡単なこと。それは、点滴を一時的にでも絞ればいいだけ。それは平穏死のための基本。しかし、大変残念ながらそこには“平穏死”も“最期まで食べる”も“排泄の尊厳”のいずれも見い出せなかった。力不足を感じた。情けなくて力が抜けた。在宅と病院の常識がこんなに違うのか?と改めて思い知らされた機会でもあった。
日本医師会は“平穏死”で人気回復を!
昨年、いくつかの医師会から「平穏死」というテーマで講演に呼んで頂いた。ようやく医師会にも興味を持って頂いたことが素直に嬉しかった。さらに喜んだのは、いくつかの医師会ではそこで市民も一緒になって話を聞いてくれたことだった。死ぬ話は、実はすべての人間に共通しているからだ。往生際の悪い3職種として、教師、坊さん、そして医師である、と言うと市民は笑ってくれたが医師会の重鎮は渋い顔をしていた。しかし在宅現場では、医師の最期に立ちあうことも稀ではない。当たり前すぎて怒られそうだが、医師とて、死は平等にやってくる。しかし一般的に医師や医師の集団は、死の話題を避けようとする。扱っても抽象的であったり、美談であったり、本質を避けようとする傾向が強い。
さて日本医師会はなにかにつけ“圧力団体”というレッテルを貼られてきた。開業医の利益追求ばかりしてと、医学会からもそっぽをむかれようとしているように末端からは見える。もちろん実際は素晴らしい活動もたくさんしているのだが、市民目線からは負の側面ばかりが指摘されている。そこで私は、人気回復の一手を提案したい。すなわち、終活やエンデイングノートの講演会を医師会が率先して企画・発信するのだ。多死社会において最も関心が高い終末期の問題に市民目線で寄り添う医師会をアピールすることは、かなりのイメージアップにつながると思うのだが、いかがだろうか。これ、真剣な提案だ。
死と向き合う医学の創造
一方、医学部や大学病院ではどうであろうか?実は昨年、医学部では2度ほど平穏死の講演をさせて頂いたが、まだまだではないか。「当院では絶対に平穏死させない」という大学病院長もおられた。もちろんその先生は平穏死を見たことが無いので信じられないのも当然だろう。平穏死を知らない教授が臨床医学を教えている。医学は生きることだけを教えておればよくて、終末期や死なんてどうでもいい、あるいはついででいい。そんな考えの大学教官が大部分ではないだろうか。確かに、医学は一分一秒でも長生きさせてQOLを上げるためにある。しかしどうやったって、死は避けられない。ならば、死から生を見つめ直す医学、つまり死生学や終末期医学や看取りの医学もあってしかるべきではないか。
最近は一部の大学で、そのような教育も始まっているようだが、まだ一部にすぎない。当院も研修医を受け入れて、在宅看取りを教えているが、真夜中の看取りであったりすることもあり、充分な教育はできていない。現在、しないよりはした方がまし、といった程度の終末期医療の教育であるが、そろそろ本腰を入れるべきではないだろう。医学教育が、きっちりと死と向き合う医学に、あるいはそうした指向性を示すだけでも医療は大きく変わるのではないか。ちなみに筆者は医学部2年の時の哲学の授業で聞いた「死の哲学」が今でも忘れられず、大きなモチベーションになっている。
患者の想いに寄り添う医療が“平穏死”という思想
平穏な最期を過ごしたいと願う患者は沢山いても、死にたいと願う患者はまずいない。平穏死という言葉を知らない患者は、穏やかな最期、満足できる最期、納得できる最期を望んでいる。しかしその納得や満足という言葉から、医療の現場が相当に距離があるという現実は、多くの医療費定本が飛ぶように売れる要因である。患者の想いを重視する医学は、ナラテイブあるいはNBM(Narrrative based medicine)と呼ばれている。そしてNBMをも包含する医学が、真のEBMであると理解しているが、現実にはそうはなっていないのではないか。そうなっていないので、あれほどまでに医療費定本が売れるという悪循環に陥っているように私には映る。患者の想いに寄り添う、と言いながら、寄り添えていないのが現実ではないのか。インフォームドコンセントと声高に言いながらも、真の意味での同意が得られていないのではないか。“平穏死”という言葉は、単に死そのものや死の周辺だけでなく、医療の土台である患者と医師の信頼関係を象徴する思想ではないかと考えている。
今こそ、医療界、医学界、医学部が全精力を挙げて国民の願いである“納得医療”を“平穏死”という言葉をキーワードに再構築するべきだと思う。はからずも町医者の分際でこのような医学雑誌に半年間にもわたり“平穏死”の連載をさせて頂いた編集部に深く感謝申し上げて、平穏死シリーズを閉じたい。

このたびURLを下記に変更しました。
お気に入り等に登録されている方は、新URLへの変更をお願いします。
新URL http://blog.drnagao.com
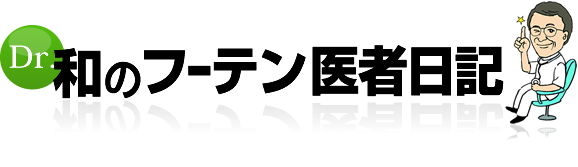


 応援クリックお願い致します!
応援クリックお願い致します!




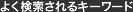
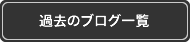
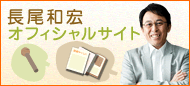
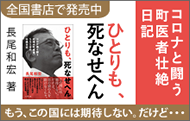
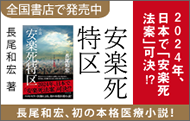
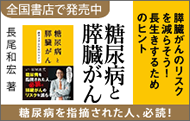
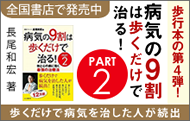
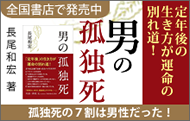
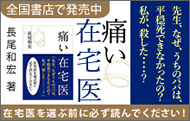

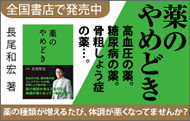
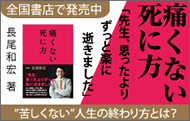
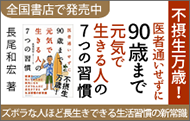
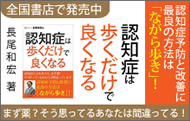
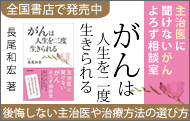
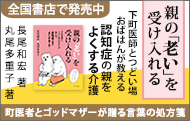
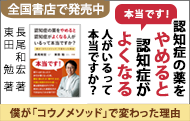


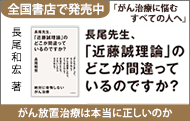
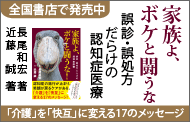
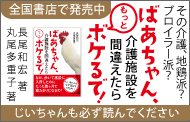

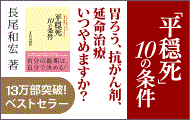
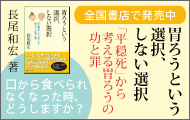


コメントする
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL: