- << 鹿児島は深い
- HOME
- 鹿児島県医師会の懐の深さ >>
このたびURLを下記に変更しました。
お気に入り等に登録されている方は、新URLへの変更をお願いします。
新URL http://blog.drnagao.com

ドイツの家庭医と専門医、研修医制度
2014年06月01日(日)
家庭医と専門医、研修医制度などについて、非常に多くのことを学んで帰られた。
日本も家庭医(かかりつけ医)が推進されているが、とても参考になる成果だ。
それを読んだので要点のみを転記させて頂く。
とっても興味深い内容だ。
当院にも数年前まで、ドイツの大学病院から直接当院に就職してくれた
外科医がおられたが、とってもいい先生だった。(開業されてご活躍されている)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
以下、梅村聡先生の記事より抜粋
2014年4月27日~5月9日の日程で
「日本医師会・民間病院医療福祉調査団」の一員としてドイツに行ってきました。
この調査団の団長は、厚生労働省の中央社会保険医療協議会の委員でもある
日本医師会常任理事の鈴木邦彦先生が務められ、
日本国内の研究者、医療関係者など、多数が参加しました。
毎年、一つの国を決めて集中的に視察・調査・研究を行っており、今年はドイツの年でした。
私は、参議院議員在職時は国会日程の関係上、一度も参加することができなかったのですが、
今回初参加しました。
参加者各自がそれぞれテーマを持って調査したのですが、私のテーマは
「ドイツにおける専門医制度と保険医契約、医師偏在への取り組み」でした。
これから3~4回に分けて報告したいと思います。
「臨床研修」は2004年に廃止
まずドイツの医師を取り巻く環境ですが、全人口約8000万人に対して医師数は約45万人。
実際に職に就いている医師数は約34万2000人、
職に就いていない医師が約10万7000人になります(いずれも2011年データ)。
職に就いていない医師の大半は年金生活者。
2007年まで、ドイツにおいては開業医(保険医)に対して「68歳定年制」が存在したため、
68歳になれば自動的に「引退」していた。
なぜ2007年に「68歳定年制」がなくなったかについては次回以降に。
約34万2000人の現役医師のうち、開業医が約14万3000人、勤務医が約17万人、
主に行政や研究などに携わる医師が約2万~3万人となっている。
そしてこの約45万人の医師全員が「医師会」に所属する。
これは「医療職法」という法律で定められている「医師の義務」になる。
ですからドイツ国内の医師は必ず「州医師会」に所属しなければならない。
ちなみに日本と異なり、「ドイツ連邦医師会」とは各州医師会が出資してつくった
「連合体」であり、活動主体はあくまで「州医師会」である。
よって、医師に課せられている義務は「州医師会」への加盟となる。
医学部は日本と同じく6年間の教育となっている。
2004年までは大学2年次と6年次に2回の国家試験を受け、
合格すれば医師免許が与えられ、卒業後18カ月の「臨床研修」を受けるという制度だった。
しかし、2004年にこの「臨床研修」は廃止された。
現在では、大学2年次と5年次に国家試験(筆記テスト)を受け、
それに合格すれば1年間(6年次)の「臨床実習」を受ける。
そして、大学6年修了時に3回目の国家試験(口頭試問)を受け、合格すれば
医師免許が授与され、直ちに卒後研修(専門医研修)に入る。
新臨床研修制度がスタートした日本とは逆の動きとなっている。
ドイツで「臨床研修」が廃止されたのは2004年、
日本で新臨床研修制度がスタートしたのも2004年。
偶然の一致だとは思いますが興味深い。
この点について関係者に話を聞くと、「できるだけ早い時期に実際の臨床現場で患者さんの近くで
働き始めることは、ヨーロッパ全体の医学教育の中ではコンセンサスが得られつつある。
その流れにドイツが乗ったということ」という答えが返ってきた。
卒後研修の実施、医師の質の保証は医師会の役割
卒後研修(専門医研修)のカリキュラム作成、専門医試験実施、
専門医認定はすべて州医師会の役割になる。
ここは、各学会がそれぞれに行っている日本との大きな相違点。
この点を指摘するとドイツの医師会関係者からの回答は、
「学会の役割はあくまで学術。卒後研修(専門医教育)を行い、質を保証し、
国民へ専門医療の提供を行う責任と資格を有するのは医師会である」でした。
専門医資格取得までの期間はおおむね5~7年。
例えば内科であればベースとなる「内科専門医」を取得するまでは5年間、
そこからさらに細かい専門医(例えば消化器、循環器、呼吸器など)を
取得するのに1~2年程度かかります。
気になる専門医取得の難易度ですが、「研修に入れば、よほどのことがない限り
取得できるものと考えてよい」とのこと。
卒後研修(専門医研修)は、専門医教育認定医療機関で、専門医指導医の下で
受ける必要がある。
専門医教育認定医療機関と専門医指導医の認定も各州医師会の仕事。
この卒後研修(専門医研修)の合否は、上司(専門医指導医)の内申書と医師会館で行われる
約30分間の口頭試問で決まる。
医学部卒業後の臨床医は全員が以上のような卒後研修(専門医研修)を受けるのです。
では、専門医を取ることで何が変わるのでしょうか。
勤務医の場合は、「専門医取得→専門医指導医→部長」となっていくことで
待遇がかなり上がっていきます。
開業医の場合は、医師会とは別組織である「保険医協会」というところに属し、
保険医協会との間で「保険医契約」を結ぶことで開業が可能となる。
ドイツ国民は約9割が「公的医療保険」、約1割は「民間医療保険」に入っている。
このうち、「公的医療保険」を取り扱うための開業医の契約が「保険医契約」。
ですので、「民間医療保険」だけを扱う開業医はこの「保険医契約」を行う必要はないが、
それだけで食べていける開業医はまずいないので、結果として「保険医契約」を結ぶことに。
医師全員に医師会加入義務があるのと同じように、
公的医療保険を扱う開業医全員に保険医協会加入義務がある。
専門科ごとに開業医の定員制
この「保険医契約」を結ぶ際に、さきほどお話しした「専門医資格」を使うことになる。
要するに「○○科で開業します」という契約を、「○○科専門医」という資格を使って
保険医協会との間で結ぶ。
しかし注意すべきは、それぞれの地域で、専門科ごとに開業医の定員制があり、
定員を超えている地域では「保険医契約を結べない」=「開業できない」のです。
定員の約45%が「家庭医」に割り振られていて、
その他、「内科」「循環器科」「整形外科」「眼科」「産婦人科」「皮膚科」……など、
合計20の診療科目でそれぞれ細かく開業医定員が決まっている。
「家庭医」以外の診療科医師のことを「専門医」と呼びます。
ちなみに「家庭医」として契約できるのは「一般医学」「内科」「小児科」のいずれかの
専門医資格を持っている医師に限られる。
現実には、都市部では「専門医」として契約して開業することはほぼ不可能のよう。
都市部では「専門医」は余っていて、都市部で開業するためには「家庭医」として契約するしかない。
地方では、「専門医」の空きが比較的出やすく、「家庭医」には空席が多くある。
以上のような方法で開業医の量的コントロールが行われている。
では、「家庭医」とはどのようなものか。
その内容については、次回お伝えしていきます。

- << 鹿児島は深い
- HOME
- 鹿児島県医師会の懐の深さ >>
このたびURLを下記に変更しました。
お気に入り等に登録されている方は、新URLへの変更をお願いします。
新URL http://blog.drnagao.com
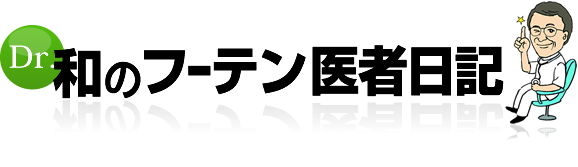


 応援クリックお願い致します!
応援クリックお願い致します!




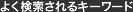
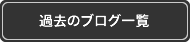
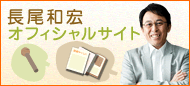
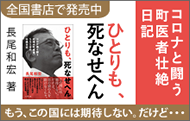
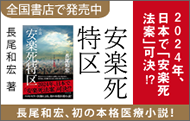
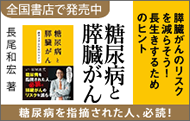
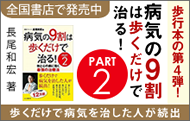
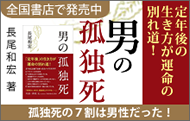
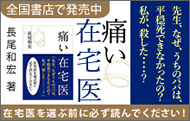

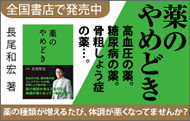
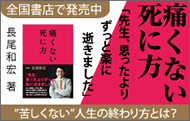
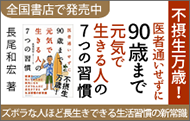
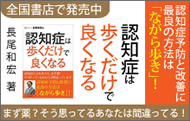
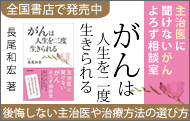
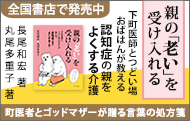
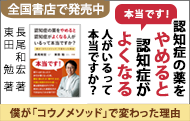


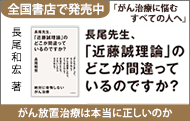
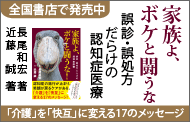
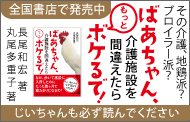

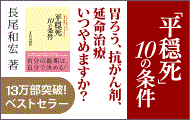
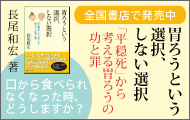

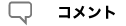
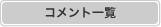

この記事へのコメント
梅村元参議院議員も、お元気で、良かったです。
ドイツの介護状況も勉強になります。
Posted by 大谷佳子 at 2014年06月06日 03:29 | 返信
すみません。
お医者さんの、教育と資格のお話でした。
第二段のドイツの在宅医療のお話をお待ちしています。
Posted by 大谷佳子 at 2014年06月07日 03:18 | 返信
コメントする
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL: