- << 知られざる 大国フランスの真実
- HOME
- 開業医はこんな感じ >>
このたびURLを下記に変更しました。
お気に入り等に登録されている方は、新URLへの変更をお願いします。
新URL http://blog.drnagao.com

警察届出減少と医師法20、21条
2014年06月07日(土)
東京女子医大で子供さんが亡くなられたという報道を見た方は多いだろう。
その中で責任者が医師法21条をまったく誤解した会見をしていて、ビックリ仰天した。
おりしも今日発売の日本医事新報には「警察届出減少と医師法20、21条」で書いた。
その中で責任者が医師法21条をまったく誤解した会見をしていて、ビックリ仰天した。
おりしも今日発売の日本医事新報には「警察届出減少と医師法20、21条」で書いた。
「日本医事新報」No.4702 2014/6/7 6月1週号16-17頁
「警察届出減少と医師法20条、21条」
尼崎発 長尾和宏の町医者でいこう!! 連載第39回に、今日掲載された小文。
一般の方には、難しいのでパスして頂いても構いません。
しかし医師の方は、是非とも以下をコピーして周囲の医師に配布して下さい!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
日本医事新報6月号 警察届出減少と医師法20条と21条 長尾和宏
石原論文への反論
本誌5月3日号のOPINION欄に掲載されたに「なぜ警察取り扱い死体数が減ったのか」と題した千葉大学法医学教室の石原憲治氏らの論文を拝読した。法医学の立場から医師法の解釈によって異状死体届け出数が減少した現状を危惧した論評である。法的解釈に関する好意的な受け止めをした医療現場の声(MRICにおける私自身の発言)も紹介する一方、「多くの 臨床医が届け出義務に対する考えを改め、従来届けて来た事案、特に診療関連死を含む病院内の事案について届け出をしなくなった可能性は否定できない」と指摘していることに強く違和感を覚えた。今回、反論を述べるとともに若干の考察を加えたい。
石原氏は2003年に13万3922体だった警察取り扱い死体は増加し続け、一昨年には17万3933体と最高数を記録したが昨年は16万9047体と前年比で2.8%減少したことを問題視し、「従来届けていいたものが、医師法20条と21条の解釈により届け出されなくなったと見るのが妥当だろう」と推論している。しかし果たしてそうなのだろうか。私は「従来届けなくてもよかったものを届けていたのが、届けなくなっただけ」ではないかと考えた。少なくともそういう解釈も当然成り立つはずである。
また、「欧米諸国の全死体に対する法医学解剖率は概ね5%から20%であるのに対し、我が国の約1.6%は異常に低い」との指摘に、門外漢の自分は驚いた。それは「欧米の数字が異常に高い」のではないかと直感したのだ。さらに石原氏は昨年の司法解剖数の前年比1.9%減や行政解剖を含む法医解剖数の0.9%減などの微減なども問題視している。しかしあまりにも短絡的な見方ではないか。私はこれらの数字の微減は、医師法20条、21条の“誤った解釈”に基づいた警察届出数が減った結果ではないかと考えている。
医師法21条は「異状死」の法律ではない
医師法21条を巡る議論が続いている。医師法21条(異状死体等の届け出義務)とは、「医師は死体又は妊娠4ケ月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない」という刑罰法規である。この21条にある「検案」とは、広尾病院事件の最高裁判決(2004年4月13日)の要旨に「医師法21条にいう死体の検案とは、医師が死因等を判定するために死体の体表を検査することをいい、当該死体が自己の診察していた患者のものであるか否かを問わないと解するのが相当であり、これと同趣旨の原判断は正当として是認できる」と書かれている。従って「診療関連の死亡事故が発生したからといって体表を検査して異状がなければ医師が警察に届ける義務はない。死体の外表検査で異状を認めた場合に限り届出義務がある」という解釈となる。しかし1994年の日本法医学会「異状死ガイドライン」をはじめとする21条関連のいくつかのガイドラインにより「医療過誤によって死亡または障害が発生した場合もそれに含まれるのではないか」という“誤解”が医療界に、いまだ蔓延しているのではないか。その“誤解”のために“本来届ける必要の無かった事例”までが誤って届けられていた可能性が高いのではないだろうか。
そもそも医師法21条とは「異状死」の法律ではない。なぜならその文言の中に、「異状死」という文言はないからだ。従って「異状死」の定義も無いのでそのガイドラインも不要である。作成すべきは「異状死体検案届出ガイドライン」である。すなわち法律と最高裁判決を読む限り、警察に届けるべきは「検案」して異状を認める死体であり、異状死の場合ではない。繰り返しになるが現行の医師法には「異状死の届け出義務」という法律は存在せず、第21条に「異状死体等の届出義務」が存在するところである。今回の警察案件の減少の解釈として、ミスリードされた解釈からゆるやかに解放された結果、無用な警察届出が回避されつつあると考えたほうが合理的ではないだろうか。
「地域包括ケア改訂」と医師法20条
今春の改訂を、「地域包括ケア改訂」と勝手に命名させて頂いたが、医師法20条が土台になっていると考える。在宅やサ高住や介護施設での看取りに際しての最大の要件は、医師法20条の熟知であろう。すなわち2012年8月31日の医事課長通名で出された「医師法20条ただし書の適切な運用について」との通知である。すなわち「24時間経過した場合であっても、死亡後改めて診察を行い、生前に診療していた傷病に関連する死亡であると判定できる場合には、死亡診断書を交付することができる」との通知が出された。石原氏はこの通知が虐待などの犯罪や事故の見逃しに通じていないか、さらには死後1ケ月を超えた場合を引き合いに出して、医師法20条に関する課長通知を問題視している。しかし臨床医は、それが必要な場合にはちゃんと「検案」をしていると認識している。また死後1ケ月も経過しているような場合は警察に届けているであろうから、現実にはあり得ないような想定話ではないか。
ちなみに医師法20条が発効した昭和24年当時は、「死」はまだ地域にあった時代だ。8割以上の人が在宅で亡くなり、病院で死ぬ人は1割だった。すなわち両者の割合は現在と全く逆であった。在宅死と病院死の割合が逆転したのは1976年である。そして2000年代に入り介護保険ができて在宅医療が推進されてきた。2025年をピークとする多死社会を乗り切る最善の方策として、また人生の最終段階を尊厳をもって迎える場として「地域包括ケアシステム」が国策として推進されてきた。超高齢社会も「ALWAYS3丁目の夕陽」ではないが、昭和24年当時の人の生き方、死に方に重ね合わせることができれば、そう悪い時代とは言えないかもしれない。いずれにせよ、どこか牧歌的な香りがする医師法20条こそが、「地域包括ケアシステム」の守護神に思えてならない。このおおらかな法律に感謝しならが、「平穏死」を看取らせて頂く日々である。
医師法解釈と死因究明制度の構築は分けて議論すべき
看取りの場は、都市部においては多様化している。しかしいかなる場所で最期を迎えようと、法治国会である日本における看取りは、すべて法律に基づいて行われる。従って、医療職のみならず介護職にまず必要なことは正確な法律の知識であろう。その後ろ立てが無い限り、安心して地域で看取ることは現代では難しい。また死がそう遠くない患者にとって必要なのは、死亡診断書を書いてくれそうな“法律を知っているかかりつけ医”を見つけておくことである。そんな中、医師法20条の寛容さと広尾病院事件の最高裁判決の中で明らかにされている医師法21条の意義は、臨床医、在宅医にとっては極めて大きな意味を持っている。
一方、犯罪や事故の見逃しの防止や精度の高い死因究明制度の構築は、文明国にとってはいうまでもなく重要な課題である。しかし無用な警察届出が増えても、誰も幸福にならない。誤解→狼狽からの警察届出の増加が医療崩壊の一因であったことを振り返っても明らかだ。そんな中、医師法20条、21条議論と精度の高い死因究明制度は分けて論じるべきだろう。また医師法20条、21条は地域包括ケアの視点からも論じ、正しく啓発されるべきだろう。
そういった意味で今回、石原論文には実に興味深い数字を提供して頂いた点で感謝したい。医師法20条、21条議論は極めて大切なものであると認識しているので、是非多くの先生方のご意見もお伺いしたい。
「警察届出減少と医師法20条、21条」
尼崎発 長尾和宏の町医者でいこう!! 連載第39回に、今日掲載された小文。
一般の方には、難しいのでパスして頂いても構いません。
しかし医師の方は、是非とも以下をコピーして周囲の医師に配布して下さい!!!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
日本医事新報6月号 警察届出減少と医師法20条と21条 長尾和宏
石原論文への反論
本誌5月3日号のOPINION欄に掲載されたに「なぜ警察取り扱い死体数が減ったのか」と題した千葉大学法医学教室の石原憲治氏らの論文を拝読した。法医学の立場から医師法の解釈によって異状死体届け出数が減少した現状を危惧した論評である。法的解釈に関する好意的な受け止めをした医療現場の声(MRICにおける私自身の発言)も紹介する一方、「多くの 臨床医が届け出義務に対する考えを改め、従来届けて来た事案、特に診療関連死を含む病院内の事案について届け出をしなくなった可能性は否定できない」と指摘していることに強く違和感を覚えた。今回、反論を述べるとともに若干の考察を加えたい。
石原氏は2003年に13万3922体だった警察取り扱い死体は増加し続け、一昨年には17万3933体と最高数を記録したが昨年は16万9047体と前年比で2.8%減少したことを問題視し、「従来届けていいたものが、医師法20条と21条の解釈により届け出されなくなったと見るのが妥当だろう」と推論している。しかし果たしてそうなのだろうか。私は「従来届けなくてもよかったものを届けていたのが、届けなくなっただけ」ではないかと考えた。少なくともそういう解釈も当然成り立つはずである。
また、「欧米諸国の全死体に対する法医学解剖率は概ね5%から20%であるのに対し、我が国の約1.6%は異常に低い」との指摘に、門外漢の自分は驚いた。それは「欧米の数字が異常に高い」のではないかと直感したのだ。さらに石原氏は昨年の司法解剖数の前年比1.9%減や行政解剖を含む法医解剖数の0.9%減などの微減なども問題視している。しかしあまりにも短絡的な見方ではないか。私はこれらの数字の微減は、医師法20条、21条の“誤った解釈”に基づいた警察届出数が減った結果ではないかと考えている。
医師法21条は「異状死」の法律ではない
医師法21条を巡る議論が続いている。医師法21条(異状死体等の届け出義務)とは、「医師は死体又は妊娠4ケ月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、24時間以内に所轄警察署に届け出なければならない」という刑罰法規である。この21条にある「検案」とは、広尾病院事件の最高裁判決(2004年4月13日)の要旨に「医師法21条にいう死体の検案とは、医師が死因等を判定するために死体の体表を検査することをいい、当該死体が自己の診察していた患者のものであるか否かを問わないと解するのが相当であり、これと同趣旨の原判断は正当として是認できる」と書かれている。従って「診療関連の死亡事故が発生したからといって体表を検査して異状がなければ医師が警察に届ける義務はない。死体の外表検査で異状を認めた場合に限り届出義務がある」という解釈となる。しかし1994年の日本法医学会「異状死ガイドライン」をはじめとする21条関連のいくつかのガイドラインにより「医療過誤によって死亡または障害が発生した場合もそれに含まれるのではないか」という“誤解”が医療界に、いまだ蔓延しているのではないか。その“誤解”のために“本来届ける必要の無かった事例”までが誤って届けられていた可能性が高いのではないだろうか。
そもそも医師法21条とは「異状死」の法律ではない。なぜならその文言の中に、「異状死」という文言はないからだ。従って「異状死」の定義も無いのでそのガイドラインも不要である。作成すべきは「異状死体検案届出ガイドライン」である。すなわち法律と最高裁判決を読む限り、警察に届けるべきは「検案」して異状を認める死体であり、異状死の場合ではない。繰り返しになるが現行の医師法には「異状死の届け出義務」という法律は存在せず、第21条に「異状死体等の届出義務」が存在するところである。今回の警察案件の減少の解釈として、ミスリードされた解釈からゆるやかに解放された結果、無用な警察届出が回避されつつあると考えたほうが合理的ではないだろうか。
「地域包括ケア改訂」と医師法20条
今春の改訂を、「地域包括ケア改訂」と勝手に命名させて頂いたが、医師法20条が土台になっていると考える。在宅やサ高住や介護施設での看取りに際しての最大の要件は、医師法20条の熟知であろう。すなわち2012年8月31日の医事課長通名で出された「医師法20条ただし書の適切な運用について」との通知である。すなわち「24時間経過した場合であっても、死亡後改めて診察を行い、生前に診療していた傷病に関連する死亡であると判定できる場合には、死亡診断書を交付することができる」との通知が出された。石原氏はこの通知が虐待などの犯罪や事故の見逃しに通じていないか、さらには死後1ケ月を超えた場合を引き合いに出して、医師法20条に関する課長通知を問題視している。しかし臨床医は、それが必要な場合にはちゃんと「検案」をしていると認識している。また死後1ケ月も経過しているような場合は警察に届けているであろうから、現実にはあり得ないような想定話ではないか。
ちなみに医師法20条が発効した昭和24年当時は、「死」はまだ地域にあった時代だ。8割以上の人が在宅で亡くなり、病院で死ぬ人は1割だった。すなわち両者の割合は現在と全く逆であった。在宅死と病院死の割合が逆転したのは1976年である。そして2000年代に入り介護保険ができて在宅医療が推進されてきた。2025年をピークとする多死社会を乗り切る最善の方策として、また人生の最終段階を尊厳をもって迎える場として「地域包括ケアシステム」が国策として推進されてきた。超高齢社会も「ALWAYS3丁目の夕陽」ではないが、昭和24年当時の人の生き方、死に方に重ね合わせることができれば、そう悪い時代とは言えないかもしれない。いずれにせよ、どこか牧歌的な香りがする医師法20条こそが、「地域包括ケアシステム」の守護神に思えてならない。このおおらかな法律に感謝しならが、「平穏死」を看取らせて頂く日々である。
医師法解釈と死因究明制度の構築は分けて議論すべき
看取りの場は、都市部においては多様化している。しかしいかなる場所で最期を迎えようと、法治国会である日本における看取りは、すべて法律に基づいて行われる。従って、医療職のみならず介護職にまず必要なことは正確な法律の知識であろう。その後ろ立てが無い限り、安心して地域で看取ることは現代では難しい。また死がそう遠くない患者にとって必要なのは、死亡診断書を書いてくれそうな“法律を知っているかかりつけ医”を見つけておくことである。そんな中、医師法20条の寛容さと広尾病院事件の最高裁判決の中で明らかにされている医師法21条の意義は、臨床医、在宅医にとっては極めて大きな意味を持っている。
一方、犯罪や事故の見逃しの防止や精度の高い死因究明制度の構築は、文明国にとってはいうまでもなく重要な課題である。しかし無用な警察届出が増えても、誰も幸福にならない。誤解→狼狽からの警察届出の増加が医療崩壊の一因であったことを振り返っても明らかだ。そんな中、医師法20条、21条議論と精度の高い死因究明制度は分けて論じるべきだろう。また医師法20条、21条は地域包括ケアの視点からも論じ、正しく啓発されるべきだろう。
そういった意味で今回、石原論文には実に興味深い数字を提供して頂いた点で感謝したい。医師法20条、21条議論は極めて大切なものであると認識しているので、是非多くの先生方のご意見もお伺いしたい。

- << 知られざる 大国フランスの真実
- HOME
- 開業医はこんな感じ >>
このたびURLを下記に変更しました。
お気に入り等に登録されている方は、新URLへの変更をお願いします。
新URL http://blog.drnagao.com
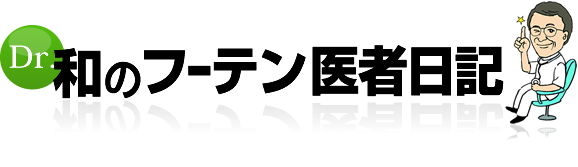


 応援クリックお願い致します!
応援クリックお願い致します!




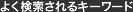




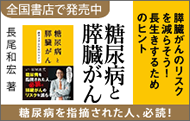







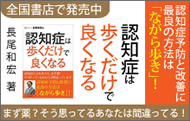

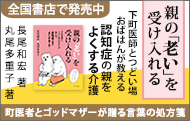
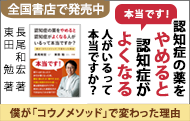


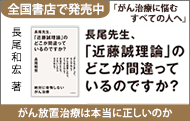
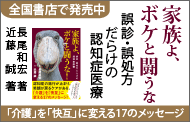
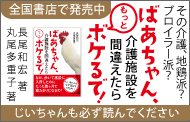

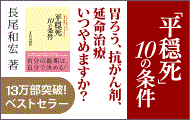
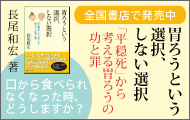

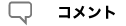


この記事へのコメント
在宅死やひとり死の時代となりました。
死亡の診断や検案をめぐる問題は、半世紀前に一度身近に経験したものの、長尾先生のような簡易で明解な認識などなく、病死のはずが、かかりつけ医による警察通報で、検視となってしまいました。
東京女子大の事例では、小児禁止薬剤の投与、火葬後の異常死届け出など、一般人には理解不能です。
かたや東京大学の治験を巡る数々の研究不正事件は、氷山の一角なのでしょう。
ここ1年だけでなく、過去の治験も大丈夫なのでしょうか?
大学は事件を解明する気はさらさらないようですね。現役医学生が実名で投書していましたが。
STAP問題でよく登場する(取材費を稼いでいる)某特任教授。専門は医療ガバナンスだそうですが、灯台元は追及しないんでしょうね。
このような医療界の自己愛性パーソナリティ障害(人格障害)の現状を、あの占い師兼精神科医にも分析願いたいものです。
医師法20条.21条の問題に、家族虐待や医療過誤などの問題を複雑にからめないでほしいですね。
平穏死の問題(また羊水検査の問題も)。尊厳死協会の一会員としては、難病や障害者を家族や友人にもつ者としても、納得できる生と死を見つめ、穏やかに考えていきたいと思います。
Posted by 鍵山いさお at 2014年06月08日 01:45 | 返信
コメントする
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL: