- << 小学校の猫「たま」 忘れないよ
- HOME
- 所沢市・航空公園 >>
このたびURLを下記に変更しました。
お気に入り等に登録されている方は、新URLへの変更をお願いします。
新URL http://blog.drnagao.com

救急搬送のはずが死亡搬送に
2017年03月09日(木)
死亡搬送が増え、全国各地で看取りのトラブルがおきているという。
在宅医や勤務医だけでなく救急隊や警察が看取りに関する法律を
知らないばかりか、4者の連携がまったく無いことが根底にある。
在宅医や勤務医だけでなく救急隊や警察が看取りに関する法律を
知らないばかりか、4者の連携がまったく無いことが根底にある。
医学教育の中に、看取りの教育が無い。
医師になってからの生涯教育の中にもほとんど無い。
死をタブーにするのは、あたらめるべきだ。
警察や救急は、救急病院だけでなく、「在宅」に少しでも
興味を持って欲しいと強く願う。
たとえば、こんな事例があったとしよう。
救急搬送のはずが死亡搬送になった例。
1 21時に老衰の在宅患者(95歳)さんが「吐血している」と電話あり。
主治医は「30分後に行くから待つように」と返答し、患家に向かう。
2 しかし待てない家族は、自己判断で救急搬送を依頼した。
往診途上の在宅主治医に他の家族から電話連絡が入る。
3 救急センターに死亡到着となり、心肺蘇生のあと死亡確認となる。
救急医は 「これは死亡診断書を書けないケース」と警察を呼ぶ。
4 警察の事情聴取、自宅に帰り現場検証が終わったのは午前3時。
93歳の奥さんは過労で倒れてしまった。
5 警察は、在宅医に「病院の霊安室に往診して、死体検案書を書く」
ことを要請し、一方、病院の若い医師は、診断書記載を拒否した。
結局、
・看取りの法律を知らない
・怖いので待てない
この2点に要約される。
そこで・・・
3月14日(火)の国立(こくりゅう)かいご学院は、今年最後の授業。→こちら
ここで看取りや死亡搬送などについて、しっかり解説する。
終了証書授与のあと、恒例の懇親会もある。
初めてだという人もぜひ、授業を聞きに来て欲しい。
地域の介護職が対象であるが、遠方の人も歓迎だ。

- << 小学校の猫「たま」 忘れないよ
- HOME
- 所沢市・航空公園 >>
このたびURLを下記に変更しました。
お気に入り等に登録されている方は、新URLへの変更をお願いします。
新URL http://blog.drnagao.com
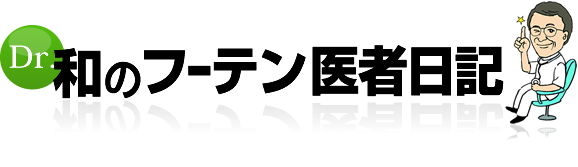


 応援クリックお願い致します!
応援クリックお願い致します!




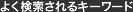
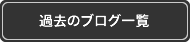
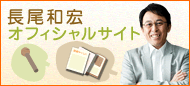
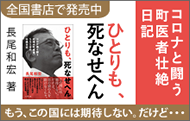
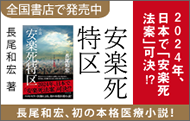
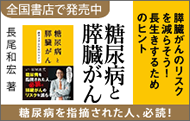
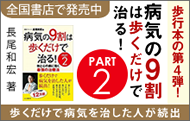
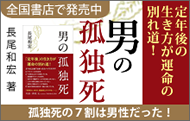
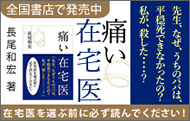

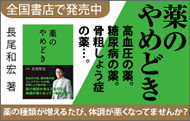
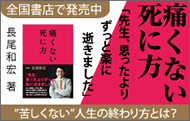
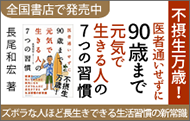
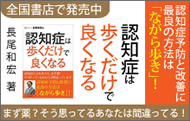
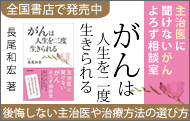
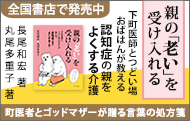
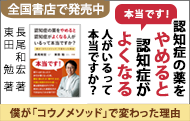


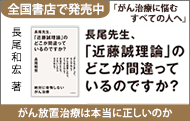
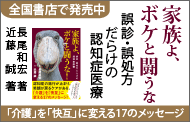
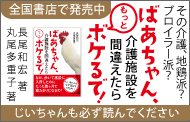

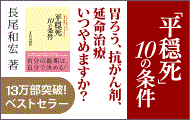
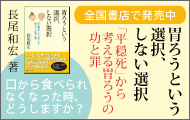

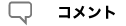
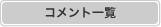

この記事へのコメント
医療、介護、教育、この三つは、当事者にならない限り、わからないことだらけ。
自分が病人になったり、親が骨折して歩けなくなったとか、子供が保育所でケガばかりしているとか、
実際に自分あるいは自分の家族に絡む問題が生じて初めて、税金で賄われて盤石であるはずの「国家ビジネス」が、スカスカで穴だらけである現実を知る。
私は、今後、もっと悪くなると、確信的に予測している。
そう感じる一番の理由は、日本人の意思疎通能力がガクンと低下しているからだ。
そこへ、グローバル化。外国人労働者の参入。
もっと、バラバラになると思います。
Posted by 匿名 at 2017年03月09日 02:48 | 返信
医学教育の中に、看取りの教育が無く、死をタブーにしている理由は、「死」は、医療にとって儲からないからです。葬式屋と坊主は儲かるけど、医者もクスリ屋も儲からない。ビジネスにならない。死亡確認と死亡診断書を書く作業だけではカネにならない。
だから、国も、力を注がない。厚労省は「長尾あたりに言わせておけ」程度なのだろう。
現政権は、医療産業を国策にしている。現政権は、医療でカネを作りたいのだ。日本の医療を輸出したいのだ。
「死」に、医療やクスリが必要なら、現政権もリキを入れるかもしれない。だから、メディアが「安楽死」を派手に取り上げるのかも・・・・・そのうち、日本は安楽死のメッカになるかもしれないね。日本に行けば、いいおクスリがあるからハッピーに死ねるだ、って、ね。
Posted by 匿名 at 2017年03月09日 03:32 | 返信
在宅での看取りに関する手引き
Posted by ロモラオ at 2017年03月09日 10:26 | 返信
長尾先生、パンフレット見せていただきました。一つ気になったので。大阪第2内科、これは大阪大学第2内科ですよね。
Posted by 加藤 伴親 at 2017年03月09日 11:09 | 返信
「吐血」なさったと聞いて、ググると「大量の吐血、下血タール便」は食道静脈瘤。「物が呑み込めない、嘔吐、胸痛」は食道がん。「繰り返す嘔吐後の吐血下血」は、マロリーワイス症候群、「突然の上腹部痛」は急性粘膜病変。」コーヒー残りかす様の吐物、タール便は胃.十二指腸潰瘍、胃がん。「胸部不快感、下血」は胃粘膜下腫瘍
と書いて有りました。
小説家永井荷風も胃がんで吐血して亡くなったそうです。鈴木俊彦とかいう経済評論家が永井荷風を良く評価して太平洋戦争中の日本の風俗や経済状況を写実的にと描いて、下町の水商売の女性を愛情深く描いていると評価しています。空襲でも疎開せずに東京で頑張って一人で生きていたのに、吐血して亡くなっているところを発見されたそうです。
長尾先生の患者さんの件は、ご家族が動揺してケアマネジャーに相談したのでしょうか?
まあそれは、しょうがないですね。病院の態度が、長尾先生に「死体検案書を書け」だなんて、イチャモンつけてるようですね。
介護保険って医療と介護と社会福祉がどうかかわって良いのかよくわかりません。
介護支援専門員は県の老人課が管轄みたいです。そのくせ講演会には厚生労働省の役人を読んで説明してもらいます。厚労省の管轄なのかと思うとそうでもない。
和洋折衷と言うか、ぴこ太郎の「アナプルペン」みたいな適当にくっつけて意味不明みたいな感じですね。
でも介護保険のサービスを受けるためには「主治医の意見書」に基づいてケアマネジャーや介護関係者が担当会議を開いてサービスを提供するのですから、医療が先行するのだと思います。
医療関係で3ヶ月働いただけなので、よくわかりませんけれど。
Posted by 匿名 at 2017年03月10日 01:35 | 返信
先日はメールのやりとりありがとうございました。
さて、事例を拝見した限り、医師が診察をした上で警察に通報したのであれば、介護の側にいるものとしては、これはしょうがないのかな?と思いました。消防署サイドが警察へ通報であれば問題ですが。
また、コメント欄で「在宅での看取りに関する手引き」の文言に、以前私が取り組んだことを思い出しました。平成25年3月に山形県村山保健所が「在宅及び高齢者施設等における看取り」の手引きを作成しています。そのなかで「救急搬送時の情報提供書」を提示することで心肺蘇生を不要とする意思表示ができる、とありますが「消防署サイドは現場も見ずに警察に通報する」前提との説明に対し、それはいくらなんでもおかしいのでは?と問題提起をしたところ、平成26年3月に改訂版を出していただいた経緯があります。
しかし、改訂版を出した時点で、平成26年2月に消防庁が出した「消防救第36号通知」との整合性が取れないものであり、再度指摘をした上で三訂版を出すべきでは?と問題提起をしたものの、いまだに出されていません。確かに「看取りの法律を知らない」という先生の指摘はおっしゃる通りかと思います。
Posted by 匿名 at 2017年03月10日 02:09 | 返信
死亡確認をした医師は、診断書の作成を断れないはず。検案書になるかも知れないが……。
医師法で、診察した場合診断書の発行は、義務付けられていると思ったけど。
Posted by 小関 洋 at 2017年03月11日 06:53 | 返信
コメントする
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL: