このたびURLを下記に変更しました。
お気に入り等に登録されている方は、新URLへの変更をお願いします。
新URL http://blog.drnagao.com

高齢者の肺炎は自宅で治療し自立度を保て!
2018年10月14日(日)
在宅療養支援診療所連絡会・会長の新田國男先生が言われたことなので、ご紹介したい。
私自身も高齢者の肺炎の9割は、外来ないし在宅で治療していて、入院ケースは少ない。
以下、日経メデイカルから引用
自宅・外来で可能な静注抗菌薬治療法活用のススメ
高齢者の肺炎じ自宅で治療し自立度を保て!
2018/10/12
今回は非常に典型的な誤嚥性肺炎を繰り返した症例を紹介しつつ、
高齢者が肺炎を生じた際も、できるだけ在宅で治療することが、
患者・家族の負担が少ないだけでなく、患者の自立度の維持にも貢献する
というお話をしたいと思います。
では、まず症例です。
症例 87歳男性
アルツハイマー病。既往として、心筋梗塞(ステント留置後)、
甲状腺機能低下症、高血圧、陳旧性脳梗塞、てんかんを有する。
訪問診療開始前 陳旧性脳梗塞・てんかんで総合病院の循環器内科、脳神経内科に通院。
1年ほど前から徐々に咳・痰が増加(特に夜間)。
訪問診療開始時 86歳のとき、発熱・喀痰増加で往診の依頼を受ける。SpO2が低下し、
炎症所見(CRP12.0mg/dL)も認めたことから、軽度の肺炎と診断。自宅にて抗菌薬
(セフトリアキソン)の1日1回静注療法を実施したところ、炎症所見は改善。
ただし、痰がらみは改善せず。
1カ月後 喀痰がさらに増加。右肺でラ音を聴取。SpO2は91%に低下し、C
RPは17.5mg/dLに上昇。肺炎と診断し、自宅にて抗菌薬(セフトリアキソン)の静注療法を2週間実施。肺炎は改善。
2カ月後 発熱、CRP23.0mg/dLとなり、自宅にて抗菌薬(セフトリアキソン)の静注療法を16日間実施。その結果、肺炎は改善。
誤嚥性肺炎を繰り返していると考えられたため、症状の改善を待った上で、
自宅にて嚥下内視鏡検査による摂食嚥下評価を実施しました。その結果、
喉頭蓋谷と梨状陥凹の食物貯留、咽頭クリアランス不良、咳反射不良を認め、
経口摂取は困難なレベルと判断しました。
栄養状態を良くすることで嚥下機能が改善する可能性もあることから、
経鼻経管栄養を開始しましたが、経鼻チューブ挿入時に強い拒否反応を生じ、
また自己抜去などの問題も多かったため、胃瘻造設を提案し、
患者・家族の了承を得て胃瘻を造設しました。
その時点での患者の状態は、室内を伝い歩きでき、時折、笑顔も見られ、
アルツハイマー病の病期は中等症レベルで、脳血管性認知症との合併型と判断しました。
すなわち、嚥下障害はアルツハイマー病の進行によるものではなく、
脳梗塞(ラクナ)梗塞が生じたためではないかと考えています。
胃瘻造設後は肺炎を生じることはなく、ちょうど1年が経過したところです。
現在は、好物(ゼリーや豆腐など)は経口で摂取し、必要な栄養は胃瘻から取っています。
今回、この症例を介してお伝えしたいこと、まず1点目は、多くの肺炎は入院させずに治療できるということです。
日本呼吸器学会による『成人肺炎診療ガイドライン2017』は、軽症から中等症の市中肺炎(CAP)は外来で
治療するというアルゴリズムを作成していますね。
また、院内肺炎(HAP)・医療介護関連肺炎(NHCAP)では、易反復性の誤嚥性肺炎や、
疾患終末期や老衰の場合は、本人の意思やQOLを考慮した治療やケアを行うことを新たに明記しています(
関連記事:高齢者肺炎にも緩和ケアの概念を)。
「本人の意思やQOLを考慮した治療やケア」とはどのようなものだと思われますか。私は、住み慣れた自宅で過ごしたいという患者さんや家族に、在宅診療を続けることがその1つの解だと思っています。
また、繰り返す誤嚥性肺炎であっても、終末期に至っていない患者さんであれば、
きちんと治癒させることができるのです。
面白い研究成果があります。元、国立長寿医療研究センター研究所長で、現在、
桜美林大学大学院老年学研究科老年学専攻教授の鈴木隆雄氏らによるもので、
1000人以上の在宅患者を対象とし、在宅診療の継続もしくは中断に関連する因子を検討した研究成果の一部です
(「在宅医療の継続要因に関する科学的根拠構築のための研究」)。
この調査では、肺炎などで38℃以上の発熱を生じた在宅患者37人のその後の経過をフォローしています。
そして、入院させるよりも在宅診療を継続した方が日常生活自立度の低下が少ないという傾向を示しています。
ただし、N数が少なく、病院に比べた在宅の優位性を示した結果とまではいえません。
とはいえ、私は、肺癌や慢性閉塞性肺疾患(COPD)など肺の合併症を有さず、
SpO2が90%以上の患者であれば、在宅での治療で対応できると考えています。もちろん、
「痰づまり」が生じるとたいへんですので、同居家族がいて喀痰吸引もできるなどの条件はあります。
肺炎を在宅で診れるかどうかは、医療というよりも介護の問題だとすら思うのです。
今回紹介した症例の介護者は、高齢の妻と高次脳機能障害を有する息子さんだったので、
夜間であっても必要時に訪問看護ができるよう準備していましたが、喀痰吸引は問題なく家族でできていました。
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
本人や家族が入院を希望すれば、その願いに従っている。
何十回も入院し、そのうち3回は短期間の人工呼吸器管理をした人もいた。
すなわち、肺炎での入退院を何十回も繰り返したが、最期は自宅で亡くなった。
いろんなケースがある。
高齢者の肺炎は常によく話し合いを行うことが大切だと思う。

このたびURLを下記に変更しました。
お気に入り等に登録されている方は、新URLへの変更をお願いします。
新URL http://blog.drnagao.com
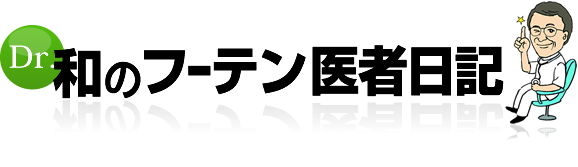


 応援クリックお願い致します!
応援クリックお願い致します!




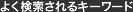
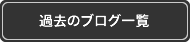
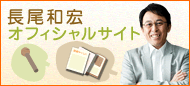
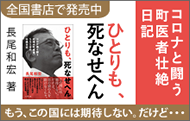
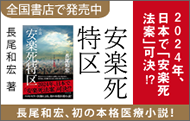
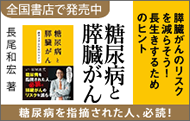
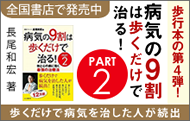
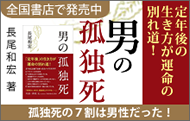
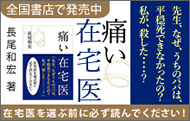

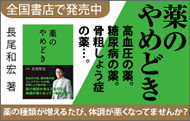
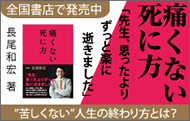
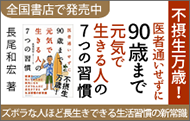
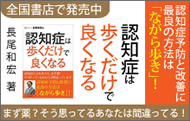
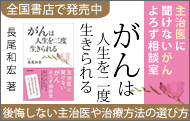
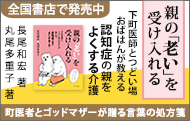
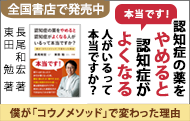


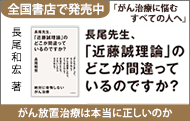
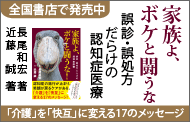
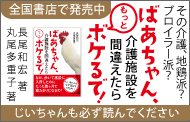

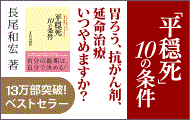
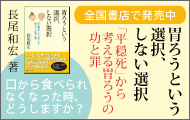

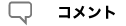
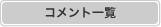

この記事へのコメント
私の父の場合は、担当在宅医が、突然何の予告も無くスキー旅行に行って終って、看護婦長(母親)が「熱が、下がっても二度めの点滴が大切だったのだ。そんな事も分からないのか!裁判で訴えたらだめだよ。こっち(医療機関側)が勝つに決まってるんだ。」と捲し立てた。
父の熱が39度を下らないので、「どうしたら良いのか?」と聞くと「病院へ行け」とのご託宣で入院となった。入院した時は「インフルエンザの検査結果は出なかった。誤嚥性肺炎だ」と言われた。尿道カテーテルを入れられた。10日して電話が掛かって来て「あんたのお父さん、MRSAに罹患してるよ」と言われた。「大丈夫ですか?」と聞くと「大丈夫です」と答えた。病院に行ってみると尿道カテーテルは引き抜かれて、70歳代の男性と、80歳代の女性と同室に入れられていた。父は2週間苦しんで死んだ。
死亡診断書を貰いに行った。「肺炎で死んだ」と書いてあった。「MRSAで死んだと書いて下さい」と言うと、若い女性事務員が「そんな事言うのだったら死亡診断書、書かんよ」と言った。
看護ステーションにお礼に言ったら看護師が「私達は全員、MRSAの保菌者なんです。でも発病なんかしませんよ」と笑顔で言った。50日祭の法事が終わってから、保険所に報告に行った。
しばらくして「肺炎球菌ワクチンを打つように」と、お触れが出た。母の担当医は医師会に入るときに、虐められたので医師会に入って居なかった。母は、肺炎球菌ワクチンだけ近所の医師会に入って居るお医者さんに、頼んで打って貰った。母は大動脈解離で死んだ。私は今年肺炎球菌ワクチンの無料券が、送られてきた。早く打て貰わなきゃと思いながら、医師会に入っているお医者さんに頼まなければいけないので、まだ打ってない。
Posted by にゃんにゃん at 2018年10月15日 04:29 | 返信
コメントする
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL: