- << 在宅療養シリーズ最終回
- HOME
- 日本プライマリケア連合学会イン福岡 >>
このたびURLを下記に変更しました。
お気に入り等に登録されている方は、新URLへの変更をお願いします。
新URL http://blog.drnagao.com

医師不足と女医問題
2012年09月01日(土)
医師不足が叫ばれているが、女医さんにもっと頑張ってもらえるのではないか。
そんな気がして今日発売の「日本医事新報」に女医問題について書かせて頂いた。
よく病院の当直が問題だと言う。
男性医師も気を遣うし、女医さんも気を使う。
クリニックならそんなことはまずない。
女医さんの職場として、病院以外にクリニックにも目を向けるばきでないか。
プライマリケアの時代だ。
さらに言うなら在宅医療の時代だ。
女医さんと診療所は相性がいい。
気が付いていない人が多いと思い提言させていただいた。
以下、日本医事新報から、一部、転載させていただく。
雑誌に載っているのはもう少しちゃんと推敲された文章だ。
日本医事新報を是非、お読みください。
この雑誌は凄い。
プライマリケアの教科書。
当院ではこれをテキストにして勉強会を重ねている。
看護師さん、ケアマネさんにも是非お勧めしたい雑誌だ。
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
町医者で行こう8月 子育て女医さんと在宅医療 長尾和宏
医師不足と、いわゆる女医問題
医師不足が指摘されている。その要因として都市部への偏在、過度な専門分化が指摘されている。また、いわゆる女医問題もその一因として挙げられている。結婚、出産を契機に医療現場から離れる女性医師が少なくない。せっかくの医師免許が活かされないと、マクロで見ても大きな社会的損失となる。女性医師の離職後の復職プログラムや再教育は、いまだ不十分である。
一方、ある医学部では入学定員の半数以上が女子であると聞いた。表には出にくい話だが、首脳部が頭を悩ませている医学部もある。そうなると、いわゆる女医問題をマイナス思考ではなく、プラス思考に転化していくという視点が必要ではないか。
女性医師が選択する診療科として、皮膚科、眼科などが多いと聞く。人の生死に関係する診療科はどうしても敬遠されがちだと。これらは専門医志向の中での選択であろう。しかし超高齢社会を前に、プライマリケア/総合診療の時代への転換点がすぐそこに来ている。病院の専門科に勤務する以外にも、プライマリケアや家庭医療、さらには在宅医療という分野でも多くの女性医師が活躍しているという事実に、もっと目を向けるべきではないだろうか。
女性医師を取り巻く労働環境
帝京大学公衆衛生大学院准教授の野村恭子氏は、第85回日本産業衛生学会において「女性医師における妊娠時労働時間と妊娠の異常との関連」を報告している。医師不足により医師を取り巻く就労環境は劣悪で、特に病院勤務医においては長時間、頻回の当直業務が問題となっている。女性医師の妊娠時における労働時間と妊娠の異状との関連が報告されている。全国私立医科大学13校の女性医師同窓生1684名を対象とした研究によると、女性医師の妊娠時の異常は妊娠発覚時の労働時間と有意に関連を認めたという。つまり労働時間が長いと妊娠の異常の割合が多く、母体保護の観点から女性医師の妊娠時の労働時間は法定労働時間内にとどめるべきである、と野村氏は提言している。
そこで筑波大学附属病院では、平成19年度の文部科学省「地域医療等社会的ニーズに対応した質の高い医療人養成推進プログラム」に「女性医師看護師キャリアアップ支援システム」が採択され、女性医師・看護師の離職防止、復職支援を積極的に行っているという。365日保育可能な病院保育所の開設に加えて、育児のための短時間勤務制度を子供が小学校3年生まで利用でき、いわゆる「小学1年生の壁」にも対応できるように環境整備を行っているそうだ。
こうした統計を見る限り、女性医師を取り巻く労働環境の改善は普遍的かつ長期的課題であるようだ。しかし以上の統計は、あくまで「勤務医」としての女性医師を取り巻くものであるともいえよう。私は診療所に勤務する女性医師の統計を知りたい。「勤務医か診療所医師か」というカテゴリーしかないのが現状だろうが、そろそろ「診療所勤務医」というカテゴリーが注目される時代ではないだろうか。
女性医師と在宅医療の相性
開業医は二分化してきている。在宅医療に従事する診療所と従事しない診療所。前者は、もし在宅療養支援診療所(在支診)登録をしていれば、「24時間365日対応」が義務づけられている。既にこうした診療所が全国に1万2千軒もある。ひとくちに「24時間365日対応」というが、もし一人の医師でこれをやるのは実際には大変な労働量となることは容易に想像できる。そう考えると在支診の流れは必然的に複数医師制に向かっている。常勤にせよ非常勤にせよ、「一馬力」での在支診運営は長期的に見ればかなり厳しい労働環境になるのは必至。ひと昔前の開業医のような24時間対応を、これからの医師に求めるのは現実的ではないと思う。
一方、今春から機能強化型の在支診制度が新設された。常勤医3名以上という条件を満たす医療機関は極めて少数であろう。多くは他院との連携による「連携型・機能強化型在支診」を指向している。3つ以上の診療所や病院が連携して24時間365日対応」という要件をクリアーしようと全国各地で模索されている。しかしいくらグループを組んで連携するといっても、可能であれば自院内で完結したいと考えるのは当然だろう。
基本的なことで恐縮だが、在宅医療とは訪問診療プラス往診から成り立っている。病院と同じように複数医師で対応すると考えれば、在宅も複数医師で対応するのは自然なこと。実は当院では以前より累計で数名の女性医師に訪問診療をお願いしてきた。結論からいえば、女性医師と在宅医療の相性は、良い。主に生活を診るのが在宅医療であるので、女性医師の方が適性があると感じている。
子育て世代こそ在宅医療へ
子育て世代の女性医師という群をひとつの社会資源として見た場合、これをいかに有効活用すべきかは極めて大きな戦略と言えよう。前述した女性医師の勤務体制改善は、あくまで病院勤務医を想定している。当院では現在、子育て世代の女医さんが2名、訪問診療に従事している。患者さんの評判は極めて良い。子育て世代であるので、当然、子供の急病や行事による急な欠勤が生じる。しかし訪問診療であれば、外来診療より日程変更など、まだ融通が効き易いと感じている。
6月の本稿で「在宅医療から地域包括ケアへ」と書いた。実際は訪問看護師さんが頑張ってくれるので、医師の負担はそれほど重くはならない。また子育て世代の女医さんには時間外対応の携帯電話は持たせないので、完全なパートタイマー勤務が可能である。
これまでの経験から、私は子育て世代の女医さんこそ在宅医療に向いている、と確信している。「地域包括ケアシステムの中での在宅医療」という概念を、大変柔軟に理解して頂ける。日々の業務連絡はメーリングリストで行っているので、たとえ変則勤務であっても、ITの恩恵でそれを補うことが可能な時代にいる。
「子育てしながら在宅医療」という選択肢もあることを、今回提案させて頂く。地域包括ケア時代を子育て中の女医さんと協働するという選択肢がある。医学部新設議論と並行して、子育て中の女医さんの活用問題も議論すべき時だと考える。

- << 在宅療養シリーズ最終回
- HOME
- 日本プライマリケア連合学会イン福岡 >>
このたびURLを下記に変更しました。
お気に入り等に登録されている方は、新URLへの変更をお願いします。
新URL http://blog.drnagao.com
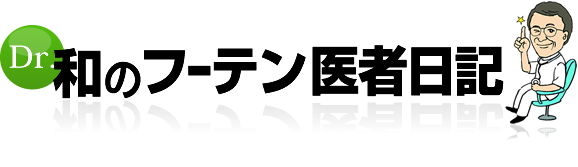


 応援クリックお願い致します!
応援クリックお願い致します!




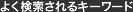
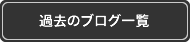
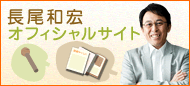
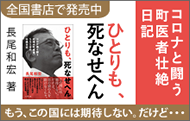
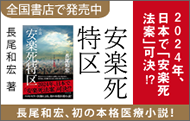
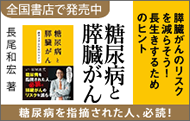
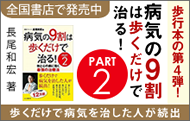
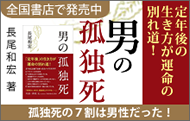
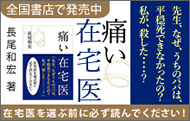

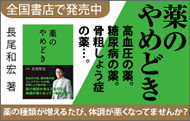
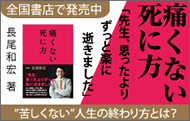
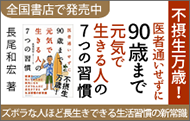
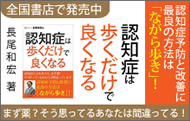
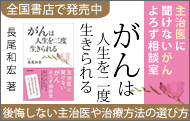
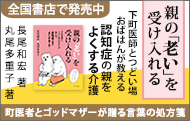
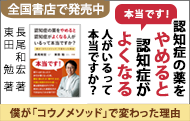


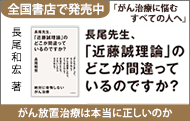
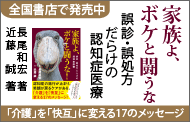
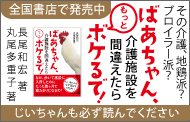

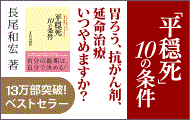
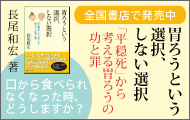


コメントする
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL: