- << 危機一髪
- HOME
- 自宅に届ける施設サービス >>
このたびURLを下記に変更しました。
お気に入り等に登録されている方は、新URLへの変更をお願いします。
新URL http://blog.drnagao.com

今、なぜ死の授業なのか?
2015年04月08日(水)
いのちの授業、なら耳ざわりがいい。
しかし、死の授業、というと怖い、知りたくない、と言う人が多い。
日本医事新報4月4日号の連載に、「死の授業」について書いた。
しかし、死の授業、というと怖い、知りたくない、と言う人が多い。
日本医事新報4月4日号の連載に、「死の授業」について書いた。
医者に説法、とはまさにこのこと。
しかし、医者の中にも、死に疎い医者も増えている。→こちら
日本医事新報4月号 今、なぜ“死の授業”なのか? 長尾和宏
死を見たことがない人が増えている
先日、東大救急救命部の矢作直樹教授が書かれた「人は死なない」という本を拝読した。医師は哲学や死生観を持たねばならないとの意を強くした。もちろん人は肉体的には必ず死ぬ。しかし高齢者のなかにも「私は生まれてこのかた一度も死を見たことがない」という人が時々おられる。病院死が在宅死を上回ったのは約40年前のこと。前期高齢者の世代は、「病院の時代」を生きてきたので、幸か不幸か「死」を見ずに生きてこられた方がいる。一方、特別養護老人ホームなどの介護施設でさえ最期は全員、救急車で病院送りなので看取りを一度も経験したことがない所がある。「死」が地域から病院に隔離されるようになって40年。多死社会を迎えるというのに「死」を見たことがない人が増えている。
在宅看取りが増えないのは何故だろう。市民やマスコミが「死」をタブー視することも理由のひとつだろう。「死が怖い」と看取りを嫌がる人も多い。一方医学界においても「死」はタブーだと思う。死生学講座がある医学部がどれだけあるのか。老年医学講座でさえ全国80の大学の4分の1にしか無いのが現実だ。
死は縁起が悪いからできるだけ避けて通りたい話題だと言われている。しかし年間の死亡者数が現在の120万人から2025年には160~170万人にまで増加する多死社会を前に増加する40~50万人の死に場所が国家的課題である。私は死をテーマとした本を数冊書いたが、市民よりも医療者のほうが死についての関心が薄いことが気になっている。
昨年、台湾を2回訪問した。GWに2000年の尊厳死法成立の立役者である成功大学の超可式教授を訪問した。救急救命部や緩和ケア病棟での尊厳死が行われていた。もちろん死生学に熱心に取り組んでいた。次いでお盆には、「死亡体験カリキュラム」がある仁徳医専を訪ねた。台湾文科省が多額の投資をした立派な納棺体験館が大学構内に建っていた。専門の教官たちが18歳の子供たちに死の体験学習をしていた。仁徳医専での医学・看護教育はいきなり死の教育から始まる。このアーリーエクスポージャーで全員大泣きする。一方、日本では死生学の講座を持つ医学部・看護学部はまだほとんど無い。
米国29歳女性の「安楽死」を「尊厳死」と誤報した理由
一方、欧米では安楽死議論が活発化している。米国の29歳女性の安楽死は記憶に新しい。脳腫瘍で余命半年と宣告されて半年経過したがまだ元気で旅行を楽しんでいた。しかし「恋人の名前が言えなくなる前に死にたい」と、安楽死ができるオレゴン州に移住。医師から処方された自殺薬をネット動画での予告通りに飲んで亡くなった。安楽死とは医師が薬剤を用いて寿命を縮める行為だが、2種類あると言われている。医者が患者に直接注射や点滴をして死に至らしめる場合と、彼女のように死ぬ錠剤を処方する場合だ。前者は100%死ぬがが、後者は錠剤をもらっても実際には飲むのは半数とのこと。オランダやスイスや米国のいくつかの州では安楽死が法律で認められている。今回、多くのメデイアは、彼女の「安楽死(ないし自殺)」を「尊厳死」と誤報したが、なぜだろうか。
そうした記事を書いた記者はこう告白した。「私は死を見たこともなければ、考えたことも無い」。そんな記者が書いているのだから、誤報するのも仕方が無い。そもそも「尊厳死」と「安楽死」はまったく別物だ。「尊厳死」とは自然の経過に任した先にある死。私が数冊書いた「平穏死」や「自然死」とほぼ同義だ。一方、「安楽死」とは薬物を用いて人工的に死期を早める死を言う。「尊厳死とは待つ死」であり、「安楽死とは待てない死」と言い換えてもいいだろう。現在の日本では「尊厳死」は、医学会のガイドラインでは容認されているが、法律的にはグレーゾーンである。たとえ本人がその希望を書面(リビングウイル:LW)に記していても、家族が反対すれば叶わない場合があるのが日本の現状だ。仮に医師が家族の反対を押し切ってその患者さんの意志を尊重して尊厳死させた場合、家族がその医師を訴える可能性がある。そうした理由から防衛医療、そして過剰医療となる傾向が指摘されている。
死を巡る国内外の動向
欧米では日本でいう「安楽死」のことを「Death with dignity」と言う。Dignityを直訳すると「尊厳」となるので、多くメデイアは「尊厳死」と誤報したのだろう。しかし日本国内でこれまで「尊厳死」として報道されてきた内容は明らかに平穏死・自然死のことだ。今回の「安楽死」は「尊厳死」と全く違うものであることは繰り返し強調しておきたい。
「死」のタブー視は国会においても同様だ。たとえばLWの法的担保を考える議員連盟での議論は10年間、ほとんど進んでいない。「LWが法的に担保されていない、つまり尊厳死が認められていない」国は、先進国の中で日本だけである。欧米では「尊厳死」は当たり前なので、特にそのような言葉はない。
一方、欧米での議論といえば「安楽死」だ。昨年、シカゴで開催された「死の権利・世界連合」に参加し、「日本では誰でも自宅で平穏死できる」という内容の講演をした。日本では安楽死の必要が無いことをアピールしたつもりだが、宗教や医療制度などの土台が全く異なる状況の中で死の在り方を論じても意味が無いかもしれない。ちなみにシカゴ大会では「認知症における安楽死」が世界の注目を集めていた。我が国では「認知症になっても住み慣れた地域でそのひとらしく生きる」ための街造りがスローガンになっているが、欧米では反対を向いている。そもそも自己決定の文化なので、もし自己決定できなくなるならその前に死んでしまいたい(=安楽死)と本気で考える人が増えている。
東大の医学生に“死の授業”
米国の29歳女性の安楽死報道で意外だったのは、多くの若者が反応したことだ。ある調査によるとなんと7割が安楽死に賛成、と答えた。さらにネット上には「僕も安楽死したい」、「なぜ日本では安楽死できないのか」との書き込みが殺到した。日本では安楽死は殺人罪で、尊厳死さえ法的にはグレーであることを彼らは知らない。いずれにせよこれまで「死」といえば、終活に代表される高齢者の話題だったものが、今回は若い世代が反応したのだ。
そこで昨年末、若者たちを対象に都内で「死の授業」を行ってみた。米国29歳女性の安楽死をどう思うか。尊厳死、安楽死、平穏死の違いについてどう思うかなど、自由に語りあった。その様子は「長尾和宏の死の授業」(ブックマン社)という本になり世に出た。これまで「いのちの授業」と銘打った本はあったがズバリ「死の授業」という本は初めてではないか。そして3月、東京大学の医学生に「死の授業」を行う機会があった。「死ぬ人は増えているか?減っているか?」という冒頭の質問の正答率はなんと100%だった。急性期病院や高度医療病院での正答率は半分以下だったので驚いた。あとで聞くと日常的にそのような教育がなされているそうだ。「君は死を見たことがあるか?」から始まる対話は楽しかった。若者の自由な発想に、私のほうが勉強させて頂いた。
しかし最近よく同業者から「長尾先生、死の本を書いて何が面白いの?」と聞かれる。面白いとかではなく、私は医療者にとって大切なテーマだと思っているだけだ。欧米や台湾と比較して、日本社会に決定的に欠けているものは、「死生学」ではないか。これは医療者も市民も同じ。そうした土台の議論が無いままに社会保障や医療制度を論じることに違和感を持っている。
医学部に死生学講座が増えることを願っている。今後、人文系の大学や高校でも“死の授業”を行う予定である。死の話の対象者は高齢者とは限らない。そもそも「死」に年齢は関係ない。老いも若きも「死」をタブー視せずに語りあう時代であると思う。
しかし、医者の中にも、死に疎い医者も増えている。→こちら
日本医事新報4月号 今、なぜ“死の授業”なのか? 長尾和宏
死を見たことがない人が増えている
先日、東大救急救命部の矢作直樹教授が書かれた「人は死なない」という本を拝読した。医師は哲学や死生観を持たねばならないとの意を強くした。もちろん人は肉体的には必ず死ぬ。しかし高齢者のなかにも「私は生まれてこのかた一度も死を見たことがない」という人が時々おられる。病院死が在宅死を上回ったのは約40年前のこと。前期高齢者の世代は、「病院の時代」を生きてきたので、幸か不幸か「死」を見ずに生きてこられた方がいる。一方、特別養護老人ホームなどの介護施設でさえ最期は全員、救急車で病院送りなので看取りを一度も経験したことがない所がある。「死」が地域から病院に隔離されるようになって40年。多死社会を迎えるというのに「死」を見たことがない人が増えている。
在宅看取りが増えないのは何故だろう。市民やマスコミが「死」をタブー視することも理由のひとつだろう。「死が怖い」と看取りを嫌がる人も多い。一方医学界においても「死」はタブーだと思う。死生学講座がある医学部がどれだけあるのか。老年医学講座でさえ全国80の大学の4分の1にしか無いのが現実だ。
死は縁起が悪いからできるだけ避けて通りたい話題だと言われている。しかし年間の死亡者数が現在の120万人から2025年には160~170万人にまで増加する多死社会を前に増加する40~50万人の死に場所が国家的課題である。私は死をテーマとした本を数冊書いたが、市民よりも医療者のほうが死についての関心が薄いことが気になっている。
昨年、台湾を2回訪問した。GWに2000年の尊厳死法成立の立役者である成功大学の超可式教授を訪問した。救急救命部や緩和ケア病棟での尊厳死が行われていた。もちろん死生学に熱心に取り組んでいた。次いでお盆には、「死亡体験カリキュラム」がある仁徳医専を訪ねた。台湾文科省が多額の投資をした立派な納棺体験館が大学構内に建っていた。専門の教官たちが18歳の子供たちに死の体験学習をしていた。仁徳医専での医学・看護教育はいきなり死の教育から始まる。このアーリーエクスポージャーで全員大泣きする。一方、日本では死生学の講座を持つ医学部・看護学部はまだほとんど無い。
米国29歳女性の「安楽死」を「尊厳死」と誤報した理由
一方、欧米では安楽死議論が活発化している。米国の29歳女性の安楽死は記憶に新しい。脳腫瘍で余命半年と宣告されて半年経過したがまだ元気で旅行を楽しんでいた。しかし「恋人の名前が言えなくなる前に死にたい」と、安楽死ができるオレゴン州に移住。医師から処方された自殺薬をネット動画での予告通りに飲んで亡くなった。安楽死とは医師が薬剤を用いて寿命を縮める行為だが、2種類あると言われている。医者が患者に直接注射や点滴をして死に至らしめる場合と、彼女のように死ぬ錠剤を処方する場合だ。前者は100%死ぬがが、後者は錠剤をもらっても実際には飲むのは半数とのこと。オランダやスイスや米国のいくつかの州では安楽死が法律で認められている。今回、多くのメデイアは、彼女の「安楽死(ないし自殺)」を「尊厳死」と誤報したが、なぜだろうか。
そうした記事を書いた記者はこう告白した。「私は死を見たこともなければ、考えたことも無い」。そんな記者が書いているのだから、誤報するのも仕方が無い。そもそも「尊厳死」と「安楽死」はまったく別物だ。「尊厳死」とは自然の経過に任した先にある死。私が数冊書いた「平穏死」や「自然死」とほぼ同義だ。一方、「安楽死」とは薬物を用いて人工的に死期を早める死を言う。「尊厳死とは待つ死」であり、「安楽死とは待てない死」と言い換えてもいいだろう。現在の日本では「尊厳死」は、医学会のガイドラインでは容認されているが、法律的にはグレーゾーンである。たとえ本人がその希望を書面(リビングウイル:LW)に記していても、家族が反対すれば叶わない場合があるのが日本の現状だ。仮に医師が家族の反対を押し切ってその患者さんの意志を尊重して尊厳死させた場合、家族がその医師を訴える可能性がある。そうした理由から防衛医療、そして過剰医療となる傾向が指摘されている。
死を巡る国内外の動向
欧米では日本でいう「安楽死」のことを「Death with dignity」と言う。Dignityを直訳すると「尊厳」となるので、多くメデイアは「尊厳死」と誤報したのだろう。しかし日本国内でこれまで「尊厳死」として報道されてきた内容は明らかに平穏死・自然死のことだ。今回の「安楽死」は「尊厳死」と全く違うものであることは繰り返し強調しておきたい。
「死」のタブー視は国会においても同様だ。たとえばLWの法的担保を考える議員連盟での議論は10年間、ほとんど進んでいない。「LWが法的に担保されていない、つまり尊厳死が認められていない」国は、先進国の中で日本だけである。欧米では「尊厳死」は当たり前なので、特にそのような言葉はない。
一方、欧米での議論といえば「安楽死」だ。昨年、シカゴで開催された「死の権利・世界連合」に参加し、「日本では誰でも自宅で平穏死できる」という内容の講演をした。日本では安楽死の必要が無いことをアピールしたつもりだが、宗教や医療制度などの土台が全く異なる状況の中で死の在り方を論じても意味が無いかもしれない。ちなみにシカゴ大会では「認知症における安楽死」が世界の注目を集めていた。我が国では「認知症になっても住み慣れた地域でそのひとらしく生きる」ための街造りがスローガンになっているが、欧米では反対を向いている。そもそも自己決定の文化なので、もし自己決定できなくなるならその前に死んでしまいたい(=安楽死)と本気で考える人が増えている。
東大の医学生に“死の授業”
米国の29歳女性の安楽死報道で意外だったのは、多くの若者が反応したことだ。ある調査によるとなんと7割が安楽死に賛成、と答えた。さらにネット上には「僕も安楽死したい」、「なぜ日本では安楽死できないのか」との書き込みが殺到した。日本では安楽死は殺人罪で、尊厳死さえ法的にはグレーであることを彼らは知らない。いずれにせよこれまで「死」といえば、終活に代表される高齢者の話題だったものが、今回は若い世代が反応したのだ。
そこで昨年末、若者たちを対象に都内で「死の授業」を行ってみた。米国29歳女性の安楽死をどう思うか。尊厳死、安楽死、平穏死の違いについてどう思うかなど、自由に語りあった。その様子は「長尾和宏の死の授業」(ブックマン社)という本になり世に出た。これまで「いのちの授業」と銘打った本はあったがズバリ「死の授業」という本は初めてではないか。そして3月、東京大学の医学生に「死の授業」を行う機会があった。「死ぬ人は増えているか?減っているか?」という冒頭の質問の正答率はなんと100%だった。急性期病院や高度医療病院での正答率は半分以下だったので驚いた。あとで聞くと日常的にそのような教育がなされているそうだ。「君は死を見たことがあるか?」から始まる対話は楽しかった。若者の自由な発想に、私のほうが勉強させて頂いた。
しかし最近よく同業者から「長尾先生、死の本を書いて何が面白いの?」と聞かれる。面白いとかではなく、私は医療者にとって大切なテーマだと思っているだけだ。欧米や台湾と比較して、日本社会に決定的に欠けているものは、「死生学」ではないか。これは医療者も市民も同じ。そうした土台の議論が無いままに社会保障や医療制度を論じることに違和感を持っている。
医学部に死生学講座が増えることを願っている。今後、人文系の大学や高校でも“死の授業”を行う予定である。死の話の対象者は高齢者とは限らない。そもそも「死」に年齢は関係ない。老いも若きも「死」をタブー視せずに語りあう時代であると思う。

- << 危機一髪
- HOME
- 自宅に届ける施設サービス >>
このたびURLを下記に変更しました。
お気に入り等に登録されている方は、新URLへの変更をお願いします。
新URL http://blog.drnagao.com
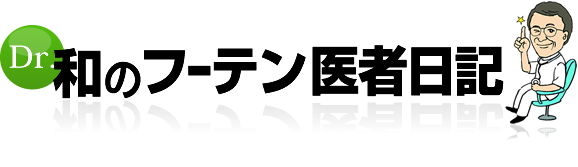


 応援クリックお願い致します!
応援クリックお願い致します!




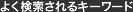




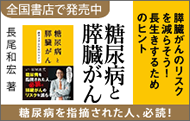







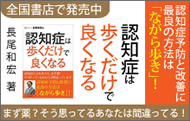

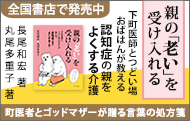
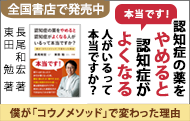


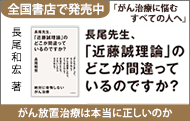
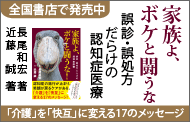
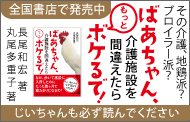

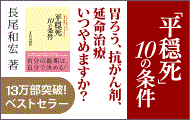
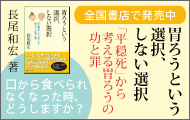

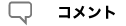


この記事へのコメント
「死の授業」を著された長尾先生だからこそ、「命の授業」もぜひ書いて欲しい気がします。
贅沢でしょうか?
Posted by 匿名 at 2015年04月08日 04:05 | 返信
人の誕生に立ち合う産婦人科の医師と、人生の終末期に立ち合う医師には、倫理観、哲学、死生観を持った医師こそ相応しいと考えています。
科学技術〔産業技術や生産技術も含む〕の進歩が、自然界の不思議を解き明かし、人々の生活の質を向上させてきたことは間違いないところと思いますが、人の誕生と死〔生命の誕生と死〕について、科学は万人が納得する説明が出来ないでいます。 哲学や倫理、宗教が力を失わない理由はそこにあると思います。
医師は医療知識や医療技術は学んでいると思いますが、人の出生時と入滅時に立ち合う医師には、倫理観や死生観をしっかりと持った人に関わって欲しいと念願しています。
医療が医術と算術のみに偏重していると、1分1秒でも永く生かしておくことのみが正しいことのようになってしまうと危惧しています。
人であれば、やはり生活の質〔QOL〕の視点からの判断が必要な場面が何度か生じるように思います。 その時に動じずに穏当な判断が下せるように、医師には幅広い分野の勉強をお願いしたいと希望しています。
人の生き死については、複雑で今後多くの議論を重ねて日本社会なりの共通認識を醸成して行く必要があると思うので、それなりの時間がかかることと思います。
それより単純で喫緊の課題として、高齢者への医療の介入過剰? の方が気になっています。
高齢者が医師の診察を受けると、歳相応の機能低下でけっして病態ではない場合でも、いろいろと病名がつき病気と判断されます。
単なる老化でも、□□病と診断され、薬が処方され、リハビリが指示され、なんとか病気を治そうとする努力が始まります。老化は老化と診断し、なんでもかんでも病気と位置づける現代の風潮が改められ、薬漬けとならない穏やかな日本社会を取り戻すことは出来ないのでしょうか?
Posted by 小林 文夫 at 2015年04月08日 10:37 | 返信
今や懐かしい、ラジオから流れる「訪ね人」の時間。
「忘却とは忘れ去ることなり。忘れえずして‥‥」の時代でした。
今年91歳の外山滋比古は、「忘れる力」こそ、老人だけでなく、人間にとって大事、と力説しています。
その『訪ね人の時間』で芥川賞をとった人こそ、新井満。
「千の風」の訳詞・作曲者で、講演の際、歌手としての熱唱も、拝聴したがあります。
なんともいえない、和声千の風でした。
この人が、5年前、『死の授業』を出していたことを、今日知りました。
大学の「死生学」担当先生の、堅苦しい講座集とは、なにか、ちがっていました。
「大地は稲妻状にひび割れ、どす黒い地下水が噴き出てきました。
原油タンク群は爆発、炎上。
火に追いかけられ、水に追いかけながら、
私は死に物狂いで逃げ回りました。」
この時、新井は、突然将来が見えた、私の顔から憂鬱の陰が消えたと、
中2の生徒に、語りかけています。
新井が母校の中学校でおこなった授業は、
「大切な人々やものを絵に描いてもらって、それを自分の手で燃やして灰にする」
という、とんでもない死の疑似体験でした。
もしその時のTV番組を時下で見ていたら、どう感じたことでしょう。
新井も言っています。
「私は授業をしながら彼らを見ていて、もっとも多感な年ごろで、
一歩間違えたら取り返しがつかない状態にもなりかねないと考えていました。
そこでひとりひとりとじっくりカウンセリングをすることにしたのです。」
どうも、新井さんの本の紹介ばかりになりそうですね。
長尾先生の医学生への授業、との対比ともなりました。
Posted by 鍵山いさお at 2015年04月14日 02:15 | 返信
コメントする
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL: