- << 市民フォーラムの感想文
- HOME
- 人間より動物に癒される >>
このたびURLを下記に変更しました。
お気に入り等に登録されている方は、新URLへの変更をお願いします。
新URL http://blog.drnagao.com

20年後の医療
2015年05月27日(水)
尊敬する小松秀樹先生がMRICに20年後の医療について書かれた。
介護の充実や混合診療など、かなり現実的な提言が述べられている。
特に、16.17、18あたりが大切であると思った。
介護の充実や混合診療など、かなり現実的な提言が述べられている。
特に、16.17、18あたりが大切であると思った。
********************************************
20年後の医療介護についての提言
亀田総合病院地域医療学講座
プログラムディレクター 小松秀樹
2015年5月26日 MRIC by 医療ガバナンス学会 発行 http://medg.jp
---------------------------------------------------------------------
1.日本の壊滅的衰退を防ぐために、たとえ社会保障給付が削減されたとしても、医療介護での雇用を維持拡大する
若者の収入を増やし、出生率を高めなければ、支え手が減少して、社会保障を維持できなくなる。結果として、少子化がさらに進む。社会保障を維持するために、子育て支援を含めて若者の支援に予算を振り向ける。職業教育を施し、若者の就労を支援する。
高度成長期、公共事業と工場生産が地方の雇用を支えた。財政赤字、生産拠点の海外移転により、公共事業、工場生産で今後、雇用が大きく増えるとは考えにくい。大きな利益を生んでいるのはヘッドクォーターと開発部門であり、大都市に集中している。大企業全体として利益が積み上がっているが、給与を支払うべき労働者は多くない。
一方で、高齢化の進行に伴い、医療介護は膨大な雇用を生み、特に地方での雇用を支えている。社会保障給付を下げるにしても、医療介護の雇用を維持しなければ、地方の貧困化がさらに進む。地方の若者を東京に吸引し続ければ、都会の出生率が極めて低いため、少子化がさらに進み、日本は壊滅的に衰退する。
2.医療介護なかでも介護には切実な需要がある
後期高齢者の爆発的な増加、独居高齢者の増加により医療介護の需要が大きくなっている。高齢者の頻回の再診、薬剤の多剤投与など、抑制が必要な部分は多いが、医療介護には切実な需要がある。自動車産業やIT産業よりはるかに人々の幸福に直結している。
家族の介護のために、年間10万人が職を離れている。生産現場から労働力が奪われる。長期間の家族介護は、家族を経済的、精神的に疲弊させる。家族介護での虐待発生は決してまれなことではなく、条件によっては誰にでも生じうる。相対危険度は介護者が男性の場合に高く、続柄によっては、妻による介護の数十倍になる。犯罪として糾弾しても、有効な対策にはならない。
3.医学モデルから生活モデルのケアへの大転換が必要
100年前まで、医師の感覚としては1945年まで、病気は治せるものではなかった。抗生剤の登場によって、病気を治せるという認識が、医学に対する畏怖と過大な期待を伴って広まった。病気の状態からそうでない状態に戻す営為が治療である。病院が治療の場であり、病院が健康に関わる主体になった(猪飼周平『病院の世紀の理論』有斐閣)。しかし、生命維持を最大の目的とする大病院には、気持ちよく人生の最期を迎える機能が希薄である。しかも、加齢に伴う身体機能の衰えと生活の質の低下に対し、医学はほとんど無力である。
予防の試みも、期待と結果を混同する「メタボ検診」の規範的言説が社会を惑わしたが、個人の行動変容が難しく成果を残せていない。
一方で、1980年代以後、障害者福祉の世界では、障害を前提に生活の質を改善する生活モデルの考え方が主流になった。高齢者のケアについても、多くの人々が、医学モデルより生活モデルのケアを、望ましいケアであると感じるようになった(猪飼周平:地域包括ケアの歴史的必然性. 『地域包括ケアの課題と未来―看取り方と看取られ方』近刊予定)。
4.目指すべきは身体的健康より精神的健康や社会的健康
「健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることをいいます(WHO憲章)。」
「死の近くにいる人たちの健康を、身体的健康のみを指すとすれば、それを守ることはほぼ不可能だということが死亡率だけを見ても明らかなのです。そういった中で私の頭をよぎるのは、身体機能の維持だけにしゃかりにきなっている現在の医療や介護、特に『予防』の取り組みが虚しい努力ではないのかという疑問です。私の経験で言わせていただければ、高齢者は、自発的努力があれば体の機能の維持や改善がなされることがありますが、外部からの指導にはほとんど効果がありません。そして、恐らく彼らの健康を私たちが守れるとすれば、それは身体的健康よりも精神的健康や社会的健康のほうが遥かにその可能性が大きいと思うのです(小野沢滋:メタボ検診より虐待検診を. 『地域包括ケアの課題と未来―看取り方と看取られ方』近刊予定)。」
5.人々の健康を改善するのに、保健活動より、権力、金、資源の公平な分配が重要
3つの行動原則
(1) 人々の日常生活条件を改善せよ
(2) 権力、金、資源の不公平な分配に立ち向かえ
(3) 問題を定量的に解析して理解し、行動してその影響を評価せよ
「WHO健康の社会的決定要因に関する委員会最終報告書 1世代の間に格差をなくそう」より
6.医療介護サービスの個人負担部分を拡大する
現在の日本で、北欧のような高福祉高負担が受け入れられるとは思えない。しかも、日本は膨大な財政赤字を抱えている。医療介護の個人負担部分を拡大しない限り、医療介護による雇用の維持は望めない。
日本の医師は、高血圧学会の有名医師に見られるように、製薬メーカーの拡販攻勢に弱い。同じ薬効でも高価な薬を使おうとする。2014年度、薬剤売上ランキングのトップは、抗血栓症薬プラビックス1288億円だった。1人1日分282.7円で、同じ目的で使われるバイアスピリン5.6円の50倍である。値段差は大きいが、心血管イベントの予防効果の差はごくわずかでしかない。バイアスピリンとの差額の相当部分を患者負担にしてはどうか。
7.費用対効果の悪い医療を保険診療から外し、混合診療を認める
現在、医療保険で認められていない診療と保険診療の併用は原則として禁止されており、併用するとすべて自費で支払わなければならない。
最近発売されている新薬は高価なものが多い。例えば、進行前立腺がん患者に使われるジェブタナという薬剤は、1バイアル60万円で3週間に1回投与される。ほとんどの患者に有害事象が発生する。ジェブタナ投与群の生存期間の中央値が15.1か月、対照群は12.7か月とその差はわずかである。外国で開発されているので、薬剤費として使われた金の多くは外国に流れる。医療費の総額を抑えるため、人に対する費用が削られる。
発作性夜間血色素尿症(PNH)に対するソリリスという薬剤は、年間で4000万円もの費用がかかる。高額療養費になるので、ほとんどの費用が、健康保険の財源から支払われている。溶血の抑制効果があるが、治癒するわけではない。生存期間が延長されるかどうかは不明とのこと。この薬剤が純粋なPNH ではなく、骨髄異形成症候群に合併したPNHに使われることが多い。イギリスやニュージーランドでは、費用に見合った効果がないとして、公的保険でカバーされていない。
費用が大きい割にわずかな効果しか期待できない薬剤は、保険診療から外す。混合診療とする。
8.官民役割分担の原則を打ち立てる
「民間公益法人の存在は、社会保障という営為の中に、公権力にしか担えない部分と、公権力でなくとも担える部分があることを示している。前者はルールの設定と監視というアンパイアが担うべき部分であり、後者はサービスの提供というプレイヤーが担うべき部分である。アンパイアとプレイヤーに求められる資質は異なり、アンパイアがプレイヤーを兼ねると試合の公正が損なわれる。アンパイアはアンパイアの役割に専念し、プレイヤーはプレイヤーの役割に専念すべきである(小松俊平:官民役割分担の原則. 『地域包括ケアの課題と未来―看取り方と看取られ方』近刊予定)。」
9.財政規律を守るために、自治体病院と民間病院を公平に扱う
「継続的に他会計繰入金を補助金として投入することが、病院経営における費用削減のインセンティブを低下させ、結果的に経常費用を増加させてしまうというメカニズムが生じてしまうのである。つまりモラルハザードの一つである。」(大島誠、石田和之:自治体病院の経営に他会計繰入金や政策医療が与える影響についてのパネルデータ分析. 徳島大学社会科学研究, 24, 1-12, 2011.)
大病院の予算規模は巨大である。病院の赤字は自治体そのものの財政を破綻させかねない。自治体病院全体として、日本の財政悪化の原因の一つである。政策医療は民間病院でも提供している。他会計繰入、補助金、交付金を可能な限りなくす。採算のとれない政策医療に補助金を出す場合にも、民間病院を公平に扱い、裁量の余地のない定量的な方法で、補助金額を決定すべきである。
10.有償ワンストップ相談サービスを業務として確立する
医療介護、生活支援サービスの円滑な利用、生活上の大きな意思決定の支援のためのコーディネーターを職業として確立する。中間層以上を対象に、有償ワンストップ相談サービスを業務として立ち上げる。これには公費を入れない。ソーシャルワーカーが、高齢者のあらゆる相談に応じて、必要なサービスにつなぐ。生活上の大きな分岐点での判断、意思決定の支援が最大の役割になる。
高齢者の財産管理も規格化で迅速に対応する。複数の立場が相互監視をして、金銭的被害には刑事罰と保険で対応する。
11.自費による医療介護サービスの体系化と民間保険との連動
中間層以上に対する医療介護の自費サービスを体系化し、民間保険と連動させる。民間保険は非営利ベースとする。ただし、非営利法人が株のすべてを所有していれば、株式会社でも可能とする。
12.生計困難者に対する総合相談サービスを拡充する
貧困そのものが健康を蝕む。また、ギリギリの生活を送っている人たちは病気をきっかけに生活が破綻する。貧困問題の大きな部分が健康問題である。生計困難者に対する総合相談サービスは、医療介護、生活支援サービスのコーディネイトを業務とするが、既存の公的な福祉サービスにつなぐことが大きな業務になる。既存の福祉サービスが申請主義の壁に阻まれて、活用されていないからである。本人からの申し立てだけでなく、無料低額診療、権利擁護、生活支援センター、民生委員、保健師、学校からの通報などあらゆる情報を受けて、相談を開始する。公費で行うが、行政と利益相反が生じるので、民間が担当する。市町村の福祉担当職員は、しばしば予算を使わないことが行動目的になっており、クライアントのニーズに応えようとしないからである。従来、行政、社会福祉協議会が行ってきた同様の業務も、民間に委託すべきである。
13.生計困難者に対するきめ細かなサービスの設定
生計困難者は単一ではなく、複合的な問題を抱えている。膨大な資金をかけた大きな制度より、きめ細かな支援が必要である。セイフティネットの底の部分である生活保護についても、第三者による搾取と本人の無駄使いを防ぐために、金銭でなくサービスの直接給付を増やすなど、細かな見直しが必要である。
14.将来の生計困難者を支援する
コミュニケーションが不得意で社会に適応できないことが生計困難者の特徴でもある。小学校、中学校にソーシャルワーカーを派遣し、こうした子供を支援する。最終的には就労とその継続を支援する。
15.医療介護サービスの規格化と「安心使い切り保険」
規格とは、合理性に基づく行為の標準化であり、非権力的枠組みで社会課題の解決を図ろうとするものである。解決方法を検証、再現、共有可能な形で提示することで、質の保障と向上に寄与する。
規格を現場で活用するには、単独施設で導入する、あるいは、相手のあるものについては、契約や協定による。規格によっては、利用者の信頼のために、認証システムを用意する必要がある。
医療介護サービスの規格化で、サービスが予見できるようになれば、規格が適応される範囲で「安心使い切り保険」を設定する。高齢者に人生の終末期を快適に暮らすために、財産を使いきってもらう。
16.日本型IHN (Integrated Healthcare Network 統合医療ネットワーク)を創設する
米国では近年、医療・介護事業の統合化が進んでいる。医療・介護の提供のみならず、メディカルスクールでの医師養成、医師の卒後教育、研究開発、医療保険まで活動範囲に含めている。大きいものは年間事業規模1兆円を超える。大小さまざまなIHNが全米を覆い、もうけ主義で評判の悪かった保険会社主導の医療が後退しつつある。米国のIHNの特徴は、政府から独立した純民間の非営利法人であり、活動の自由度が大きいことにある。行政が活動内容に細かな指示を出すわけではない。
日本の大学医学部の古めかしい体質と水準の低さ、医療費抑制政策、混合診療禁止原理主義、二次医療圏の面積の狭さと人口の少なさ、医療に対する規制の多さは、日本の医療の活力を削ぎガラパゴス化させている。日本の医療が世界をリードできるようにするために、メディカルスクールの創設を含めて、日本版IHNを創設する。医療、介護の自費部分の民間保険はIHNが担当する。
17.社会保障制度改革国民会議報告書(平成25年8月6日)とそれに基づく統制医療政策を廃棄する
報告書は「強制力」を強める方向を強く打ち出した。都道府県の権限を強め、「病床機能報告制度」と「地域医療ビジョン」によって、かつての共産圏の統制経済のように、行政が医療の需要と供給量を決める。一方で、消費税増収分を活用した基金を創設した。病院の購入する物品やサービスに消費税がかかっているにもかかわらず、診療報酬に消費税がかけられていない。消費税率引き上げ分が診療報酬に十分に反映されていないことを合わせると、この基金は、病院の収益の一部を取り上げ、それを、支配の道具に使う制度であり、再投資の判断を経営者から行政が奪い取るものである。
中間行政機関である県の無責任な行動、信義則の欠如、補助金の不適切な使い方は目に余るものがある。医療行政における都道府県の権限を可能な限り縮小させる必要がある。
18.医療に消費税を課税する
2014年4月の消費税率引き上げによって病院の財務状況が急速に悪化した。診療報酬で税率上昇を調整しようとしても、多額の投資を必要とする病院と、開業医を同じ診療報酬で調整できるはずがない。病院によっても、投資は大きく異なる。本来、政治の絡む問題ではなく、単純計算の世界である。医療にも消費税を課税し、病院が購入した物品、サービスにかかる消費税を控除した残りを国庫に納めるようにすべきである。
20年後の医療介護についての提言
亀田総合病院地域医療学講座
プログラムディレクター 小松秀樹
2015年5月26日 MRIC by 医療ガバナンス学会 発行 http://medg.jp
---------------------------------------------------------------------
1.日本の壊滅的衰退を防ぐために、たとえ社会保障給付が削減されたとしても、医療介護での雇用を維持拡大する
若者の収入を増やし、出生率を高めなければ、支え手が減少して、社会保障を維持できなくなる。結果として、少子化がさらに進む。社会保障を維持するために、子育て支援を含めて若者の支援に予算を振り向ける。職業教育を施し、若者の就労を支援する。
高度成長期、公共事業と工場生産が地方の雇用を支えた。財政赤字、生産拠点の海外移転により、公共事業、工場生産で今後、雇用が大きく増えるとは考えにくい。大きな利益を生んでいるのはヘッドクォーターと開発部門であり、大都市に集中している。大企業全体として利益が積み上がっているが、給与を支払うべき労働者は多くない。
一方で、高齢化の進行に伴い、医療介護は膨大な雇用を生み、特に地方での雇用を支えている。社会保障給付を下げるにしても、医療介護の雇用を維持しなければ、地方の貧困化がさらに進む。地方の若者を東京に吸引し続ければ、都会の出生率が極めて低いため、少子化がさらに進み、日本は壊滅的に衰退する。
2.医療介護なかでも介護には切実な需要がある
後期高齢者の爆発的な増加、独居高齢者の増加により医療介護の需要が大きくなっている。高齢者の頻回の再診、薬剤の多剤投与など、抑制が必要な部分は多いが、医療介護には切実な需要がある。自動車産業やIT産業よりはるかに人々の幸福に直結している。
家族の介護のために、年間10万人が職を離れている。生産現場から労働力が奪われる。長期間の家族介護は、家族を経済的、精神的に疲弊させる。家族介護での虐待発生は決してまれなことではなく、条件によっては誰にでも生じうる。相対危険度は介護者が男性の場合に高く、続柄によっては、妻による介護の数十倍になる。犯罪として糾弾しても、有効な対策にはならない。
3.医学モデルから生活モデルのケアへの大転換が必要
100年前まで、医師の感覚としては1945年まで、病気は治せるものではなかった。抗生剤の登場によって、病気を治せるという認識が、医学に対する畏怖と過大な期待を伴って広まった。病気の状態からそうでない状態に戻す営為が治療である。病院が治療の場であり、病院が健康に関わる主体になった(猪飼周平『病院の世紀の理論』有斐閣)。しかし、生命維持を最大の目的とする大病院には、気持ちよく人生の最期を迎える機能が希薄である。しかも、加齢に伴う身体機能の衰えと生活の質の低下に対し、医学はほとんど無力である。
予防の試みも、期待と結果を混同する「メタボ検診」の規範的言説が社会を惑わしたが、個人の行動変容が難しく成果を残せていない。
一方で、1980年代以後、障害者福祉の世界では、障害を前提に生活の質を改善する生活モデルの考え方が主流になった。高齢者のケアについても、多くの人々が、医学モデルより生活モデルのケアを、望ましいケアであると感じるようになった(猪飼周平:地域包括ケアの歴史的必然性. 『地域包括ケアの課題と未来―看取り方と看取られ方』近刊予定)。
4.目指すべきは身体的健康より精神的健康や社会的健康
「健康とは、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることをいいます(WHO憲章)。」
「死の近くにいる人たちの健康を、身体的健康のみを指すとすれば、それを守ることはほぼ不可能だということが死亡率だけを見ても明らかなのです。そういった中で私の頭をよぎるのは、身体機能の維持だけにしゃかりにきなっている現在の医療や介護、特に『予防』の取り組みが虚しい努力ではないのかという疑問です。私の経験で言わせていただければ、高齢者は、自発的努力があれば体の機能の維持や改善がなされることがありますが、外部からの指導にはほとんど効果がありません。そして、恐らく彼らの健康を私たちが守れるとすれば、それは身体的健康よりも精神的健康や社会的健康のほうが遥かにその可能性が大きいと思うのです(小野沢滋:メタボ検診より虐待検診を. 『地域包括ケアの課題と未来―看取り方と看取られ方』近刊予定)。」
5.人々の健康を改善するのに、保健活動より、権力、金、資源の公平な分配が重要
3つの行動原則
(1) 人々の日常生活条件を改善せよ
(2) 権力、金、資源の不公平な分配に立ち向かえ
(3) 問題を定量的に解析して理解し、行動してその影響を評価せよ
「WHO健康の社会的決定要因に関する委員会最終報告書 1世代の間に格差をなくそう」より
6.医療介護サービスの個人負担部分を拡大する
現在の日本で、北欧のような高福祉高負担が受け入れられるとは思えない。しかも、日本は膨大な財政赤字を抱えている。医療介護の個人負担部分を拡大しない限り、医療介護による雇用の維持は望めない。
日本の医師は、高血圧学会の有名医師に見られるように、製薬メーカーの拡販攻勢に弱い。同じ薬効でも高価な薬を使おうとする。2014年度、薬剤売上ランキングのトップは、抗血栓症薬プラビックス1288億円だった。1人1日分282.7円で、同じ目的で使われるバイアスピリン5.6円の50倍である。値段差は大きいが、心血管イベントの予防効果の差はごくわずかでしかない。バイアスピリンとの差額の相当部分を患者負担にしてはどうか。
7.費用対効果の悪い医療を保険診療から外し、混合診療を認める
現在、医療保険で認められていない診療と保険診療の併用は原則として禁止されており、併用するとすべて自費で支払わなければならない。
最近発売されている新薬は高価なものが多い。例えば、進行前立腺がん患者に使われるジェブタナという薬剤は、1バイアル60万円で3週間に1回投与される。ほとんどの患者に有害事象が発生する。ジェブタナ投与群の生存期間の中央値が15.1か月、対照群は12.7か月とその差はわずかである。外国で開発されているので、薬剤費として使われた金の多くは外国に流れる。医療費の総額を抑えるため、人に対する費用が削られる。
発作性夜間血色素尿症(PNH)に対するソリリスという薬剤は、年間で4000万円もの費用がかかる。高額療養費になるので、ほとんどの費用が、健康保険の財源から支払われている。溶血の抑制効果があるが、治癒するわけではない。生存期間が延長されるかどうかは不明とのこと。この薬剤が純粋なPNH ではなく、骨髄異形成症候群に合併したPNHに使われることが多い。イギリスやニュージーランドでは、費用に見合った効果がないとして、公的保険でカバーされていない。
費用が大きい割にわずかな効果しか期待できない薬剤は、保険診療から外す。混合診療とする。
8.官民役割分担の原則を打ち立てる
「民間公益法人の存在は、社会保障という営為の中に、公権力にしか担えない部分と、公権力でなくとも担える部分があることを示している。前者はルールの設定と監視というアンパイアが担うべき部分であり、後者はサービスの提供というプレイヤーが担うべき部分である。アンパイアとプレイヤーに求められる資質は異なり、アンパイアがプレイヤーを兼ねると試合の公正が損なわれる。アンパイアはアンパイアの役割に専念し、プレイヤーはプレイヤーの役割に専念すべきである(小松俊平:官民役割分担の原則. 『地域包括ケアの課題と未来―看取り方と看取られ方』近刊予定)。」
9.財政規律を守るために、自治体病院と民間病院を公平に扱う
「継続的に他会計繰入金を補助金として投入することが、病院経営における費用削減のインセンティブを低下させ、結果的に経常費用を増加させてしまうというメカニズムが生じてしまうのである。つまりモラルハザードの一つである。」(大島誠、石田和之:自治体病院の経営に他会計繰入金や政策医療が与える影響についてのパネルデータ分析. 徳島大学社会科学研究, 24, 1-12, 2011.)
大病院の予算規模は巨大である。病院の赤字は自治体そのものの財政を破綻させかねない。自治体病院全体として、日本の財政悪化の原因の一つである。政策医療は民間病院でも提供している。他会計繰入、補助金、交付金を可能な限りなくす。採算のとれない政策医療に補助金を出す場合にも、民間病院を公平に扱い、裁量の余地のない定量的な方法で、補助金額を決定すべきである。
10.有償ワンストップ相談サービスを業務として確立する
医療介護、生活支援サービスの円滑な利用、生活上の大きな意思決定の支援のためのコーディネーターを職業として確立する。中間層以上を対象に、有償ワンストップ相談サービスを業務として立ち上げる。これには公費を入れない。ソーシャルワーカーが、高齢者のあらゆる相談に応じて、必要なサービスにつなぐ。生活上の大きな分岐点での判断、意思決定の支援が最大の役割になる。
高齢者の財産管理も規格化で迅速に対応する。複数の立場が相互監視をして、金銭的被害には刑事罰と保険で対応する。
11.自費による医療介護サービスの体系化と民間保険との連動
中間層以上に対する医療介護の自費サービスを体系化し、民間保険と連動させる。民間保険は非営利ベースとする。ただし、非営利法人が株のすべてを所有していれば、株式会社でも可能とする。
12.生計困難者に対する総合相談サービスを拡充する
貧困そのものが健康を蝕む。また、ギリギリの生活を送っている人たちは病気をきっかけに生活が破綻する。貧困問題の大きな部分が健康問題である。生計困難者に対する総合相談サービスは、医療介護、生活支援サービスのコーディネイトを業務とするが、既存の公的な福祉サービスにつなぐことが大きな業務になる。既存の福祉サービスが申請主義の壁に阻まれて、活用されていないからである。本人からの申し立てだけでなく、無料低額診療、権利擁護、生活支援センター、民生委員、保健師、学校からの通報などあらゆる情報を受けて、相談を開始する。公費で行うが、行政と利益相反が生じるので、民間が担当する。市町村の福祉担当職員は、しばしば予算を使わないことが行動目的になっており、クライアントのニーズに応えようとしないからである。従来、行政、社会福祉協議会が行ってきた同様の業務も、民間に委託すべきである。
13.生計困難者に対するきめ細かなサービスの設定
生計困難者は単一ではなく、複合的な問題を抱えている。膨大な資金をかけた大きな制度より、きめ細かな支援が必要である。セイフティネットの底の部分である生活保護についても、第三者による搾取と本人の無駄使いを防ぐために、金銭でなくサービスの直接給付を増やすなど、細かな見直しが必要である。
14.将来の生計困難者を支援する
コミュニケーションが不得意で社会に適応できないことが生計困難者の特徴でもある。小学校、中学校にソーシャルワーカーを派遣し、こうした子供を支援する。最終的には就労とその継続を支援する。
15.医療介護サービスの規格化と「安心使い切り保険」
規格とは、合理性に基づく行為の標準化であり、非権力的枠組みで社会課題の解決を図ろうとするものである。解決方法を検証、再現、共有可能な形で提示することで、質の保障と向上に寄与する。
規格を現場で活用するには、単独施設で導入する、あるいは、相手のあるものについては、契約や協定による。規格によっては、利用者の信頼のために、認証システムを用意する必要がある。
医療介護サービスの規格化で、サービスが予見できるようになれば、規格が適応される範囲で「安心使い切り保険」を設定する。高齢者に人生の終末期を快適に暮らすために、財産を使いきってもらう。
16.日本型IHN (Integrated Healthcare Network 統合医療ネットワーク)を創設する
米国では近年、医療・介護事業の統合化が進んでいる。医療・介護の提供のみならず、メディカルスクールでの医師養成、医師の卒後教育、研究開発、医療保険まで活動範囲に含めている。大きいものは年間事業規模1兆円を超える。大小さまざまなIHNが全米を覆い、もうけ主義で評判の悪かった保険会社主導の医療が後退しつつある。米国のIHNの特徴は、政府から独立した純民間の非営利法人であり、活動の自由度が大きいことにある。行政が活動内容に細かな指示を出すわけではない。
日本の大学医学部の古めかしい体質と水準の低さ、医療費抑制政策、混合診療禁止原理主義、二次医療圏の面積の狭さと人口の少なさ、医療に対する規制の多さは、日本の医療の活力を削ぎガラパゴス化させている。日本の医療が世界をリードできるようにするために、メディカルスクールの創設を含めて、日本版IHNを創設する。医療、介護の自費部分の民間保険はIHNが担当する。
17.社会保障制度改革国民会議報告書(平成25年8月6日)とそれに基づく統制医療政策を廃棄する
報告書は「強制力」を強める方向を強く打ち出した。都道府県の権限を強め、「病床機能報告制度」と「地域医療ビジョン」によって、かつての共産圏の統制経済のように、行政が医療の需要と供給量を決める。一方で、消費税増収分を活用した基金を創設した。病院の購入する物品やサービスに消費税がかかっているにもかかわらず、診療報酬に消費税がかけられていない。消費税率引き上げ分が診療報酬に十分に反映されていないことを合わせると、この基金は、病院の収益の一部を取り上げ、それを、支配の道具に使う制度であり、再投資の判断を経営者から行政が奪い取るものである。
中間行政機関である県の無責任な行動、信義則の欠如、補助金の不適切な使い方は目に余るものがある。医療行政における都道府県の権限を可能な限り縮小させる必要がある。
18.医療に消費税を課税する
2014年4月の消費税率引き上げによって病院の財務状況が急速に悪化した。診療報酬で税率上昇を調整しようとしても、多額の投資を必要とする病院と、開業医を同じ診療報酬で調整できるはずがない。病院によっても、投資は大きく異なる。本来、政治の絡む問題ではなく、単純計算の世界である。医療にも消費税を課税し、病院が購入した物品、サービスにかかる消費税を控除した残りを国庫に納めるようにすべきである。

- << 市民フォーラムの感想文
- HOME
- 人間より動物に癒される >>
このたびURLを下記に変更しました。
お気に入り等に登録されている方は、新URLへの変更をお願いします。
新URL http://blog.drnagao.com
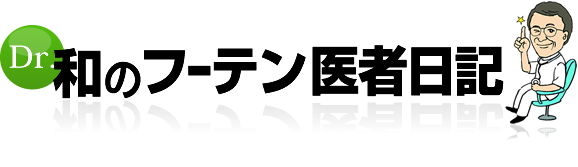


 応援クリックお願い致します!
応援クリックお願い致します!




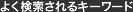
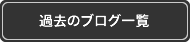
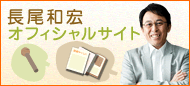
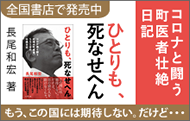
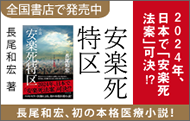
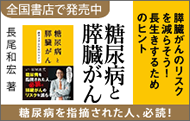
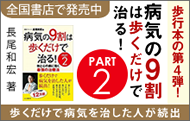
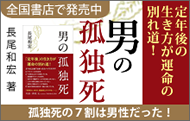
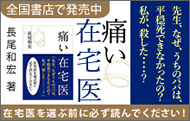

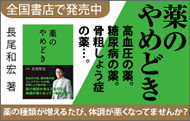
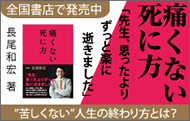
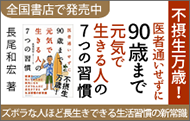
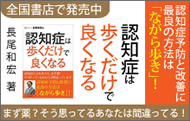
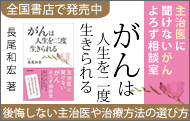
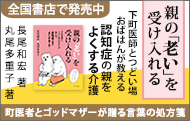
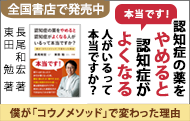


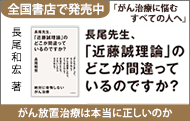
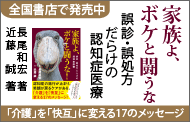
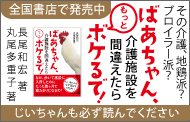

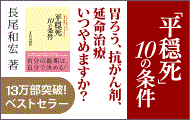
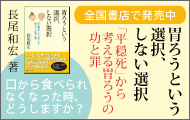

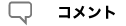
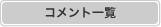

この記事へのコメント
とても 難しい内容で 私には 難しいです
診療報酬も 介護報酬も 消費税はかかりませんが
改正のたびに 振り回されます
ちなみに 今回の改正で
訪問看護30分以上60分未満の場合
834単位だったのが814単位に下がりました
つまり 約200円の減額でした
厳しいことだなと感じています
今度は 医療の改正になるので 同様のマイナス改正になるんでしょうか
何かが ヘンです
Posted by 訪問看護師 宮ちゃん at 2015年05月28日 09:19 | 返信
コメントする
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL: