- << 抗認知症薬による易怒性は副作用
- HOME
- 「ボケ」か、「認知症」か >>
このたびURLを下記に変更しました。
お気に入り等に登録されている方は、新URLへの変更をお願いします。
新URL http://blog.drnagao.com

月刊公論、9月号、10月号
2015年10月03日(土)
公論9月号 トヨタ女性役員の麻薬報道の余波
遅れている日本の緩和医療
トヨタ自動車の女性役員が、オキシコドン57錠を密輸した疑いで逮捕された事件は大きく報道された。役員を辞任し悪質では無いと判断され不起訴となり、一件落着したかのように見える。しかし本件の報道は医療現場に大きな影を落としている。つまり先進国でもっとも遅れていると言われている我が国の緩和医療に、さらに「麻薬は怖いもの」という冷や水を差した格好になった。強い痛みがあるのに医療用麻薬を拒否する患者さんが増えているのだ。今回、日本の医療用麻薬の現状と本事件の報道の余波について考えたい。
モルヒネの歴史と医療現場
現在、日本の医療現場ではモルヒネ、オキシコドン、フェンタニルの3種類の医療用麻薬が使われている。2012年の統計によると、日本の国民1人当たりの年間オキシコドン消費量は世界71ケ国中32位であった。世界平均が13.5mgに対し、日本は3.6mgとかなり少ない。一方、モルヒネ消費量でみても日本は世界158ケ国中42位と、先進国としては医療用麻薬の後進国である。ちなみにオキソコドン消費量の第一位は断トツで米国で、世界のオキシコドンの81%が米国で消費されている。米国では日本とは異なり、比較的容易にオキソコドンが入手できるため、痛みの治療以外に嗜好目的で使う人が多く依存症や慢性中毒が大きな社会問題となっている。マイケルジャクソンもオキソコドンを常用していた。
日本人の医療用麻薬の消費量が少ない原因には、我慢強い国民性もあるのかもしれない。しかしモルヒネや医療用麻薬への根強い誤解がある。その背景には、麻薬に関するさまざまな歴史があるのだろう。つまり、アヘン戦争というアヘンを巡り戦争にまで至った歴史やいろいろな戦争のたびに麻薬中毒者が発生した事実やアメリカでは麻薬中毒者が増えているという現実が、日本の医療用麻薬の誤解を増幅させている。モルヒネは医療用麻薬として適正に使われれば、薬物依存や慢性中毒にならず痛みを和らげる「良薬」で依存性は無いことが証明されている。痛みがある状態では脳内の報酬系の神経活動は抑えられているので依存にならない。日本においてはモルヒネをはじめとする医療用麻薬は厳しく管理されている。麻薬免許を持った医師しか処方できない。他人に譲渡したり不正使用すれば法律に触れ犯罪になる。処方されたモルヒネは薬だが他人に譲渡した時点で不正麻薬に変わるのだ。先のトヨタの女性役員は日本の法律に触れるので、対応は当然であろう。いずれにせよ麻薬の歴史を学び正しく理解することで、誤解を解きたいものだ。
遅れている日本の緩和医療
私が医師になった1984年、研修医として勤務した新大阪の野戦病院には大学病院に入りきれない末期のがん患者さんが、続々と搬送されてきた。しかし当時、痛みの治療としてモルヒネはまだあまり使われていなかった。ブロンプトンカクテルというモルヒネにワインを加えた水をわざわざ作ってもらっていた。1989年に、モルヒネの効果が12時間続く(1日2回で済む)「MSコンチン」という名前の医療用麻薬が発売された。コンチンとは、コンテイニュー(効果が持続する)という意味だが、この薬の登場は衝撃的だった。しかしそれから四半世紀経過しても日本はまだまだ緩和医療後進国である。
モルヒネと聞くと、反射的に眉をしかめる患者がほとんどだ。「中毒になる」、「死期を早める」、「最期に使う薬」というイメージらしい。こうした誤解は医師でさえ根強くあり大変残念なことだ。死期を早めるどころか、モルヒネで痛みを取ると食事が摂れて活動量も増えるので命を延ばす薬である。さらにがん以外の痛み、特に3ケ月以上続く慢性疼痛にも使えることを知る人は医師であっても多くはない。
先日のある夜、初診の患者さんの往診を依頼された。伺うと、がんの全身骨転移で七転八倒していた。かかりつけの病院や診療所から出ていた薬は、ロキソニンだけであった。翌朝一番にモルヒネを処方して1錠飲ませると、すぐに痛みが和らぎ、笑顔と冗談が出た。在宅ホスピス医として医療用麻薬で痛みや呼吸苦を取るととても感謝される。医師になって良かったと思う瞬間だ。「平穏死」や「尊厳死」と題した一般本を数冊書いているが、その根底には医療用麻薬を用いた緩和医療があることを忘れてはいけない。俳優の故・今井雅之さんは「モルヒネで安楽死したい」と述べた。気持ちは分かるが、モルヒネで安楽死することはない。種々の痛みは脳で感じるが、その感受性は人によって10倍、いや時には数百倍もの個人差がある。痛みが取れて笑顔と食欲が出るモルヒネの量は、少量から開始して徐々に増量しながら探るは、その作業をタイトレーション(至適容量設定)という。在宅医の役割はこうした緩和ケアの技術にある。
国立精神・神経医療研究センターの調査でモルヒネ中毒患者は現在、日本にはほとんどいない。モルヒネの大きな誤解と偏見を解いて、必要な人に必要な量だけ使えば大きな恵みとなる。日本はアメリカと違い医療用麻薬の規制が大変厳しいが、それはアメリカのように依存症や慢性中毒を出さないためだ。
せっかく、モルヒネやオキシコドンやフェンタニルといういい医療用麻薬が、非がんにも塩酸モルヒネ錠などが使える時代なのに、トヨタの女性役員の報道以降、その恩恵に預かれない患者さんが増えていることが大変残念である。誤解を解くことにかなりの時間を要する。今回の報道が、遅れている我が国のモルヒネなどを用いた緩和医療の啓発に水を差すことがないことを祈るばかりだ。
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
公論10月号 “がんもどき”はあるか?がんを放置するとどうなる?
“近藤誠理論”を検証する
がんは国民病だが自分だけは例外?
日本人は2人に1人が一生のうち一度はがんになる。そして3人に1人はがんで死んでいる。今、この記事を読んでいるみなさんも50%の確率でがんになる。あまり実感が無いかもしれないが紛れもない現実だ。がんは最もありふれた病気。珍しくもなんともない。しかし、いざ自分にがんが見つかったらみんな大騒ぎ。「どうして私だけが・・・」「なにも悪いことしていないのに・・・」「死ぬのかなあ・・・」と右往左往する。がんセンターの一番偉い先生でさえ、「がんセンターの医者ががんになって初めて分ったこと」みたいな本を書くが「じゃあなにかい、今まで患者の気持ちを分らずにやっていたの?」と突っ込みたくもなる。
人間は、なんでも自分だけは例外だと思っている。自分だけはがんにならないし、死なない。それくらい楽観的なので少々辛いことがあっても生きられる。しかしイザ、がんと言われた時に慌てないために、普段から多少はがんの基礎知識を備えておくべきであろう。
ステージⅣ=末期がん、ではない
研修医時代、末期がんが続々と搬送されてくる野戦病院でコマねずみのように働きながら、ひとつの疑問を抱えていた。「なぜ人は末期がんになると死ぬのか?」「もしかしたら末期がんのまま長く過ごす人もいるのではないか」など想像した。しかし末期がんの人はどんなに医療を施しても全員旅立たれて、悔し泣きしたこともあった。
そもそも末期がんとは何か?どんな状態なのか?末期がんとは、がんが、あちこちの臓器に転移してモリモリと増殖するとともに全身が徐々に衰弱してくる状態を指す。誤解してはいけないのは、アチコチに転移巣があるだけでは末期がんと言えないこと。たとえば乳がんが全身の骨に転移したままホルモン療法で10年近く元気に仕事をしていた女性がいた。彼女は骨シンチを撮ると全身にがんの転移だらけ。しかし10年近く転移巣はそのままで大きくならなかった。がん病巣はあちこちに散らばりそれなりの大きさになっても、ある時点から休眠モードに入ったのか。だから彼女は10年近く生きた。しかしある日から高熱が続いた。冬眠していただろう全身のがんが何故か一斉蜂起しはじめたのか。みるみる衰弱して、在宅医療に移行して2ケ月後に穏やかに旅立たれた。10年間も冬眠期間がありながら、たった2ケ月間の増殖期間を経て最期を迎えた。
がん細胞から体を弱らせる毒素のようなものが出るので全身が衰弱する。がん細胞の数が増えるほど毒素の量も増えて、筋肉は衰え、食事量は落ち、全身の機能が低下する。そんな状態を末期がんと呼ぶ。余命でいえば、医者が余命1~2ケ月だと判断する段階だ。
ステージⅣという言葉をよく聞くだろう。Ⅴは無いので、Ⅳとは原発巣から離れた臓器に転移がある状態だ。しかしステージⅣ=末期がん、ではない。ステージⅣから生還する人、つまりがんが完治する人は少なからずいる。特に大腸がんでは、肝臓や肺や脳にも転移していても完治する人もいる。大腸がんだけでなく、ステージⅣのスキルス胃がん(腹膜播種あり)でも、手術と抗がん剤で4年間生きている人もいる。
“近藤誠理論”のどこが間違っているのか?
さて、この3年ほど、「がんもどき」とか「がんは放置したほうがいい」という内容の本が軒並み売れている。すべて慶応大学・元講師の近藤誠医師が書かれた本だ。最近は「医者に殺される」、「薬に殺される」などとエスカレートすると、多くのメデイアが取りあげ市民の支持を得ている。現実にがんの宣告を受けた人はまずがんに関する知識を得ようと書店に駆け込み、がんに関する本を買い求めた。そこに並ぶ近藤誠氏が書かれた本を開くと、「がんもどき」や「がん放置療法」という言葉が繰り返し登場する。私のクリニックでがんが見つかっても「先生、私のがんはがんもどきですか?」とか「先生、私はがんを治療せずに放置します」という人が時々おられる。もう90歳を超えているのであれば、もう何でもアリだろうが、もし50歳代や60歳代で、充分助かる範囲のがんであれば、助かる命も助からなくなる。実に罪深い本だなと思うことがある。
“がんもどき”はあるか?そもそも“がんもどき”という言葉を使う人は世界中で一人しかいない。しかし仮に「がんではあるが、あまり悪さをしないがん」と定義するならば、結構ある。ゆっくりがん、のんびりがんは放っておいてもなかなか死なない。甲状腺がんや前立腺がんなどがその代表だ。一方、近藤氏は「本物のがん」という言葉も使う。初期の段階から全身のあちこち転移しているタチの悪いがんのことだそうだが、これもある。どちらもあるのだが、どちらかしかない、だから全てのがんは放置せよ、と言うから話がおかしくなる。実は両者の間がいくらでもある。“近藤誠理論”を、「がんもどき理論」に基づいた「がん放置療法」と定義してみよう。“近藤誠理論”を書いた本はベストセラーになっているが、医学論文としては発表されていないので医学界では一切認知されていない。
しかし強烈な国民的支持を得ている。それはがんの過剰医療に対する国民の怒りの表れであろう。私はこれを“近藤誠現象”と呼び、がん医療界は反省すべきだと訴えている。8月に“近藤誠理論”の真偽を分かり易く解説した本が世に出た。「長尾先生、近藤誠理論のどこが間違っているのですか?」(ブックマン社)。近藤誠理論の真偽を○X△で示し、後悔しないがんとの共存方法を解説した。発売2週間で3刷りになったが、興味のある方はご一読願いたい。
遅れている日本の緩和医療
トヨタ自動車の女性役員が、オキシコドン57錠を密輸した疑いで逮捕された事件は大きく報道された。役員を辞任し悪質では無いと判断され不起訴となり、一件落着したかのように見える。しかし本件の報道は医療現場に大きな影を落としている。つまり先進国でもっとも遅れていると言われている我が国の緩和医療に、さらに「麻薬は怖いもの」という冷や水を差した格好になった。強い痛みがあるのに医療用麻薬を拒否する患者さんが増えているのだ。今回、日本の医療用麻薬の現状と本事件の報道の余波について考えたい。
モルヒネの歴史と医療現場
現在、日本の医療現場ではモルヒネ、オキシコドン、フェンタニルの3種類の医療用麻薬が使われている。2012年の統計によると、日本の国民1人当たりの年間オキシコドン消費量は世界71ケ国中32位であった。世界平均が13.5mgに対し、日本は3.6mgとかなり少ない。一方、モルヒネ消費量でみても日本は世界158ケ国中42位と、先進国としては医療用麻薬の後進国である。ちなみにオキソコドン消費量の第一位は断トツで米国で、世界のオキシコドンの81%が米国で消費されている。米国では日本とは異なり、比較的容易にオキソコドンが入手できるため、痛みの治療以外に嗜好目的で使う人が多く依存症や慢性中毒が大きな社会問題となっている。マイケルジャクソンもオキソコドンを常用していた。
日本人の医療用麻薬の消費量が少ない原因には、我慢強い国民性もあるのかもしれない。しかしモルヒネや医療用麻薬への根強い誤解がある。その背景には、麻薬に関するさまざまな歴史があるのだろう。つまり、アヘン戦争というアヘンを巡り戦争にまで至った歴史やいろいろな戦争のたびに麻薬中毒者が発生した事実やアメリカでは麻薬中毒者が増えているという現実が、日本の医療用麻薬の誤解を増幅させている。モルヒネは医療用麻薬として適正に使われれば、薬物依存や慢性中毒にならず痛みを和らげる「良薬」で依存性は無いことが証明されている。痛みがある状態では脳内の報酬系の神経活動は抑えられているので依存にならない。日本においてはモルヒネをはじめとする医療用麻薬は厳しく管理されている。麻薬免許を持った医師しか処方できない。他人に譲渡したり不正使用すれば法律に触れ犯罪になる。処方されたモルヒネは薬だが他人に譲渡した時点で不正麻薬に変わるのだ。先のトヨタの女性役員は日本の法律に触れるので、対応は当然であろう。いずれにせよ麻薬の歴史を学び正しく理解することで、誤解を解きたいものだ。
遅れている日本の緩和医療
私が医師になった1984年、研修医として勤務した新大阪の野戦病院には大学病院に入りきれない末期のがん患者さんが、続々と搬送されてきた。しかし当時、痛みの治療としてモルヒネはまだあまり使われていなかった。ブロンプトンカクテルというモルヒネにワインを加えた水をわざわざ作ってもらっていた。1989年に、モルヒネの効果が12時間続く(1日2回で済む)「MSコンチン」という名前の医療用麻薬が発売された。コンチンとは、コンテイニュー(効果が持続する)という意味だが、この薬の登場は衝撃的だった。しかしそれから四半世紀経過しても日本はまだまだ緩和医療後進国である。
モルヒネと聞くと、反射的に眉をしかめる患者がほとんどだ。「中毒になる」、「死期を早める」、「最期に使う薬」というイメージらしい。こうした誤解は医師でさえ根強くあり大変残念なことだ。死期を早めるどころか、モルヒネで痛みを取ると食事が摂れて活動量も増えるので命を延ばす薬である。さらにがん以外の痛み、特に3ケ月以上続く慢性疼痛にも使えることを知る人は医師であっても多くはない。
先日のある夜、初診の患者さんの往診を依頼された。伺うと、がんの全身骨転移で七転八倒していた。かかりつけの病院や診療所から出ていた薬は、ロキソニンだけであった。翌朝一番にモルヒネを処方して1錠飲ませると、すぐに痛みが和らぎ、笑顔と冗談が出た。在宅ホスピス医として医療用麻薬で痛みや呼吸苦を取るととても感謝される。医師になって良かったと思う瞬間だ。「平穏死」や「尊厳死」と題した一般本を数冊書いているが、その根底には医療用麻薬を用いた緩和医療があることを忘れてはいけない。俳優の故・今井雅之さんは「モルヒネで安楽死したい」と述べた。気持ちは分かるが、モルヒネで安楽死することはない。種々の痛みは脳で感じるが、その感受性は人によって10倍、いや時には数百倍もの個人差がある。痛みが取れて笑顔と食欲が出るモルヒネの量は、少量から開始して徐々に増量しながら探るは、その作業をタイトレーション(至適容量設定)という。在宅医の役割はこうした緩和ケアの技術にある。
国立精神・神経医療研究センターの調査でモルヒネ中毒患者は現在、日本にはほとんどいない。モルヒネの大きな誤解と偏見を解いて、必要な人に必要な量だけ使えば大きな恵みとなる。日本はアメリカと違い医療用麻薬の規制が大変厳しいが、それはアメリカのように依存症や慢性中毒を出さないためだ。
せっかく、モルヒネやオキシコドンやフェンタニルといういい医療用麻薬が、非がんにも塩酸モルヒネ錠などが使える時代なのに、トヨタの女性役員の報道以降、その恩恵に預かれない患者さんが増えていることが大変残念である。誤解を解くことにかなりの時間を要する。今回の報道が、遅れている我が国のモルヒネなどを用いた緩和医療の啓発に水を差すことがないことを祈るばかりだ。
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
公論10月号 “がんもどき”はあるか?がんを放置するとどうなる?
“近藤誠理論”を検証する
がんは国民病だが自分だけは例外?
日本人は2人に1人が一生のうち一度はがんになる。そして3人に1人はがんで死んでいる。今、この記事を読んでいるみなさんも50%の確率でがんになる。あまり実感が無いかもしれないが紛れもない現実だ。がんは最もありふれた病気。珍しくもなんともない。しかし、いざ自分にがんが見つかったらみんな大騒ぎ。「どうして私だけが・・・」「なにも悪いことしていないのに・・・」「死ぬのかなあ・・・」と右往左往する。がんセンターの一番偉い先生でさえ、「がんセンターの医者ががんになって初めて分ったこと」みたいな本を書くが「じゃあなにかい、今まで患者の気持ちを分らずにやっていたの?」と突っ込みたくもなる。
人間は、なんでも自分だけは例外だと思っている。自分だけはがんにならないし、死なない。それくらい楽観的なので少々辛いことがあっても生きられる。しかしイザ、がんと言われた時に慌てないために、普段から多少はがんの基礎知識を備えておくべきであろう。
ステージⅣ=末期がん、ではない
研修医時代、末期がんが続々と搬送されてくる野戦病院でコマねずみのように働きながら、ひとつの疑問を抱えていた。「なぜ人は末期がんになると死ぬのか?」「もしかしたら末期がんのまま長く過ごす人もいるのではないか」など想像した。しかし末期がんの人はどんなに医療を施しても全員旅立たれて、悔し泣きしたこともあった。
そもそも末期がんとは何か?どんな状態なのか?末期がんとは、がんが、あちこちの臓器に転移してモリモリと増殖するとともに全身が徐々に衰弱してくる状態を指す。誤解してはいけないのは、アチコチに転移巣があるだけでは末期がんと言えないこと。たとえば乳がんが全身の骨に転移したままホルモン療法で10年近く元気に仕事をしていた女性がいた。彼女は骨シンチを撮ると全身にがんの転移だらけ。しかし10年近く転移巣はそのままで大きくならなかった。がん病巣はあちこちに散らばりそれなりの大きさになっても、ある時点から休眠モードに入ったのか。だから彼女は10年近く生きた。しかしある日から高熱が続いた。冬眠していただろう全身のがんが何故か一斉蜂起しはじめたのか。みるみる衰弱して、在宅医療に移行して2ケ月後に穏やかに旅立たれた。10年間も冬眠期間がありながら、たった2ケ月間の増殖期間を経て最期を迎えた。
がん細胞から体を弱らせる毒素のようなものが出るので全身が衰弱する。がん細胞の数が増えるほど毒素の量も増えて、筋肉は衰え、食事量は落ち、全身の機能が低下する。そんな状態を末期がんと呼ぶ。余命でいえば、医者が余命1~2ケ月だと判断する段階だ。
ステージⅣという言葉をよく聞くだろう。Ⅴは無いので、Ⅳとは原発巣から離れた臓器に転移がある状態だ。しかしステージⅣ=末期がん、ではない。ステージⅣから生還する人、つまりがんが完治する人は少なからずいる。特に大腸がんでは、肝臓や肺や脳にも転移していても完治する人もいる。大腸がんだけでなく、ステージⅣのスキルス胃がん(腹膜播種あり)でも、手術と抗がん剤で4年間生きている人もいる。
“近藤誠理論”のどこが間違っているのか?
さて、この3年ほど、「がんもどき」とか「がんは放置したほうがいい」という内容の本が軒並み売れている。すべて慶応大学・元講師の近藤誠医師が書かれた本だ。最近は「医者に殺される」、「薬に殺される」などとエスカレートすると、多くのメデイアが取りあげ市民の支持を得ている。現実にがんの宣告を受けた人はまずがんに関する知識を得ようと書店に駆け込み、がんに関する本を買い求めた。そこに並ぶ近藤誠氏が書かれた本を開くと、「がんもどき」や「がん放置療法」という言葉が繰り返し登場する。私のクリニックでがんが見つかっても「先生、私のがんはがんもどきですか?」とか「先生、私はがんを治療せずに放置します」という人が時々おられる。もう90歳を超えているのであれば、もう何でもアリだろうが、もし50歳代や60歳代で、充分助かる範囲のがんであれば、助かる命も助からなくなる。実に罪深い本だなと思うことがある。
“がんもどき”はあるか?そもそも“がんもどき”という言葉を使う人は世界中で一人しかいない。しかし仮に「がんではあるが、あまり悪さをしないがん」と定義するならば、結構ある。ゆっくりがん、のんびりがんは放っておいてもなかなか死なない。甲状腺がんや前立腺がんなどがその代表だ。一方、近藤氏は「本物のがん」という言葉も使う。初期の段階から全身のあちこち転移しているタチの悪いがんのことだそうだが、これもある。どちらもあるのだが、どちらかしかない、だから全てのがんは放置せよ、と言うから話がおかしくなる。実は両者の間がいくらでもある。“近藤誠理論”を、「がんもどき理論」に基づいた「がん放置療法」と定義してみよう。“近藤誠理論”を書いた本はベストセラーになっているが、医学論文としては発表されていないので医学界では一切認知されていない。
しかし強烈な国民的支持を得ている。それはがんの過剰医療に対する国民の怒りの表れであろう。私はこれを“近藤誠現象”と呼び、がん医療界は反省すべきだと訴えている。8月に“近藤誠理論”の真偽を分かり易く解説した本が世に出た。「長尾先生、近藤誠理論のどこが間違っているのですか?」(ブックマン社)。近藤誠理論の真偽を○X△で示し、後悔しないがんとの共存方法を解説した。発売2週間で3刷りになったが、興味のある方はご一読願いたい。

- << 抗認知症薬による易怒性は副作用
- HOME
- 「ボケ」か、「認知症」か >>
このたびURLを下記に変更しました。
お気に入り等に登録されている方は、新URLへの変更をお願いします。
新URL http://blog.drnagao.com
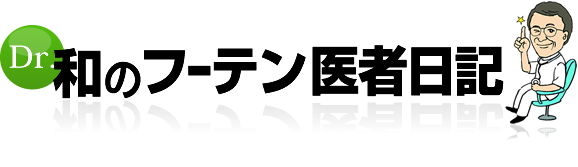


 応援クリックお願い致します!
応援クリックお願い致します!




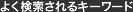




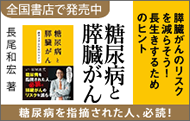







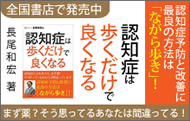

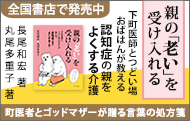
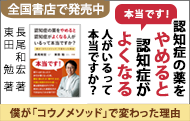


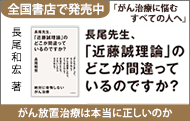
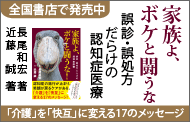
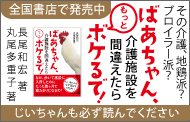

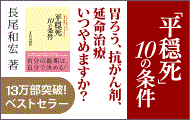
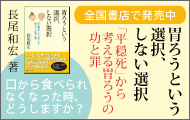


コメントする
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL: