- << 抗認知症薬の増量規定
- HOME
- 脳疲労概念は万病に通じる >>
このたびURLを下記に変更しました。
お気に入り等に登録されている方は、新URLへの変更をお願いします。
新URL http://blog.drnagao.com

最近の在宅医療の実態と展望
2016年01月14日(木)
日本医事新報1月号の連載は、「最近の看取りの実態と展望」について述べた。→こちら
とても偉そうに言える立場でもないのだが思っていることを自戒を込めて描いた。
在宅医療も年々変わっていく。しかし医療の本質は永遠に変わらないと信じている。
とても偉そうに言える立場でもないのだが思っていることを自戒を込めて描いた。
在宅医療も年々変わっていく。しかし医療の本質は永遠に変わらないと信じている。
日本医事新報1月号 最近の在宅医療・看取りの実態と今後の展望 長尾和宏
看取りの実態が公表される時代に
謹んで新年の御挨拶を申し上げます。2010年に始まったこの連載もはや6年目になりました。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。さて今回は、最近の在宅医療・看取りの実態と今後の展望について私見を述べさせて頂きます。
数年前、読売新聞本紙で在宅看取り数が公表された。しかしこれは新聞社が独自に行ったアンケート調査の集計報告であった。一方、2006年から在宅療養支援診療所制度が始まり今年で10年目を迎えた。それに登録した医療機関は毎年厚労省に1年間の看取りの実績を報告する義務がある。2年前、週刊朝日のムックがその届け出の数字をそのまま掲載したことで、各医療機関が届けた在宅看取りの数が世間に公表されることになった。昨年も最新版が公表されたが、厚労省に届け出た数字以外に週刊朝日が独自に割り出した「在宅看取り率」という数字までもが掲載された。しかしこの算出方式には問題がある。施設での看取りがまったく評価されていないのである。実は施設での看取りは、居宅での看取りより難しいことがよくある。そこで施設での看取りを軽視するのはおかしいとの指摘をした。その結果、11月に発売された週刊紙本体では首都圏と大阪・兵庫県のみではあるが、看取りの実績が年間5件以上ある医療機関のみが、在宅看取り率は取り消した形で転載された。つまり看取りの実績のある在宅療養支援診療所のリストが公表された。
こうした動きに異を唱える人も当然いる。しかし私はかねてより診療所機能も病院機能と同様に情報公開すべきであると主張してきたので異論は無い。むしろ医師会入会の有無や在宅療養支援診療所に登録していないが実績のある診療所、さらには看取りの実績のある訪問看護ステーションの公表なども視野に入れてもいいのではとさえ考えている。特別養護老人ホームや老人保健施設やグループホームやサービス付き高齢者向き賃貸住宅などの施設での看取りが謳われているが、実態調査を行うと施設間のばらつきが極めて大きい。やはり看取りの実態の公表は時代の流れだと思う。
増加する在宅医療へのクレーム
私は全国在宅療養支援診療所連絡会の世話人を拝命している関係もあるのか、講演時などに在宅医療へのクレームを耳にすることが年々増えている。そもそも在宅医療機関へのクレームには、医師会との関係性や経営状況に関する感情的なものも含まれるので、それらの因子を排除したクレームだけを抽出してみたい。一番多いのは、患者と在宅主治医と関係性に関するクレームである。以前は、臨床経験が豊富な医師が良好な関係性を構築していた。しかし最近は、利益追求型の営利法人がバックについている診療所の臨床経験が少ない医師へのクレームが増えている。在宅療養支援診療所は営利目的ではなく、地域貢献でなくてはいけない。そして充分な臨床経験がある医師こそが在宅医療を担う資格があると考える。
2番目に、緊急往診をしないとか看取りをしないというクレームである。たしかになにか変化があると全例救急車で病院搬送にする在宅医や看取りをはっきり嫌がる医師もいる。しかし厳密には在宅療養支援診療所制度の契約条項に違反しているので法的にも問題がある。前出の週刊紙には厚労省に届けられた年間の緊急往診の数も公表されているが、市民にはそのような数字の持つ意味を解説して在宅医療の啓発を行っている。
一方、在宅におけるリスクマネジメントにおいても病院同様、大きな課題を孕んでいる。密室性、閉鎖性があるが故、リスクマネジメントにはより透明性、公平性が期待される。在宅医療における医療訴訟はまだ表にはあまり出ていないが、今後増加するであろう。以下に述べる診療の質の評価に加えて、在宅におけるリスクマネッジメントも今後の大きな課題である。
在宅医療の質の評価
私は病院経営とは無縁であるが、御縁あって療養病床を中心とした日本慢性期医療協会(日慢協)の役員も拝命している。日慢協に入会されている慢性期病院における診療の質の評価システムは素晴らしいものがあることを知ることになった。協会で独自に調査項目を決めて自己採点して公表し、切磋琢磨しているのだ。一方、北海道のある地区のグループホーム協会では、300を超えるチェック項目をお互いに評価しあい、それを公表するという方法で介護の質の担保を行っている。このように医療の質や介護の質の評価は今後の課題である。翻って在宅医療の世界ではどうであろうか。従来からの閉鎖的、密室的という批難を真摯に受け止める時期に来ている気がする。国民の評価に耐えられる在宅医療の質の評価システムの構築は急務であろう。
ただ在宅医療の質の評価は難しい側面も多い。現在、年間看取り数と往診数だけで評価されているが、看取りはあくまで結果なので、その数字だけで評価することは適切ではない。ただし年間数例以上の看取りがあれば、とりあえず看取りの実績がある診療所であると言えよう。しかしがんと非がんでは看取りまでの期間や看取り率に大きな差がある。私の診療所においては、年間90人の看取りのうちがんと非がんが半数ずつであるが、在宅看取り率でみると前者は90%であるのに対し、後者は40%程度である。
以上から、年間の看取り数はがんと非がんに分けて報告するようにしてはどうだろうか。また居宅と施設に分けてそれぞれの在宅看取り数と看取り率を記載してはどうか。その診療所の機能がよく分かる。さらに地域の医師会などが主催する多職種連携の会への参加実績も届け出項目に加えるべきであろう。今後は地域包括ケアや研修医教育などにどれだけ参画しているかも数値化して「質の評価」に加えるべきであろう。それを満たしてはじめて機能強化型と呼べるのであろう。
在宅医療から地域包括ケアへ
この3年間、全国各地で在宅医療の講演を行ってきた。そして「在宅医療という言葉はもう古い。これからは地域包括ケアだ」と言い続けてきた。在宅療養支援診療所の重大な責務のひとつはまさに地域包括ケアへの参画である。一方、高い診療報酬だけを取っている在宅療養支援診療所がある。
今春の診療報酬改訂は地域包括ケアという国策を実現するための改定にして欲しい。蛇足であるが多剤投与に関しても開業医にいくらペナルテイを課しても解決にはならない。病院から10種類以上の投薬が書かれた紹介状を持ってこられることは日常であるからだ。一方、患者への地域包括ケアの啓発も急務だ。医療機関に有利な改定は、当然患者側から見れば不利な内容でなる。目先の損得勘定ではなく患者側から見ても公平感のある改訂が望まれる。
介護保険との同時改定を待てない項目もある。たとえば10年前から書籍や雑誌等で指摘し続けている訪問看護の診療報酬体系である。訪問看護は依然として医療保険と介護保険の狭間に落ちたままである。いくら在宅推進という旗を掲げても、ケアマネが介護保険下の訪問看護を拒むといいう歪んだ実態が一部では続いている。こう言うと必ず「特別指示書に逃げればいいではないか」と言われるが、抜本的な制度改変が本筋であると考える。すべての訪問看護を医療保険下に戻して頂かないと、そして医療保険下のみなし訪問看護もさらに活用できるような仕組みにしないと地域包括ケアの推進は期待できない。訪問看護制度の改善こそが、医療と介護の連携を促進させると思う。しかし制度自体が足かせになっている現状は、2025年問題を乗り越えるのは困難ではないか。在宅医の24時間対応に関しても地域の慢性期病院との連携強化で乗り切るという考え方はどうか。そのほうが合理的ではないか。大病院や急性期病院が軽症者や慢性期医療の対象者の受け皿になっている。だから慢性期病院がそこに入れない重症患者の受け皿になっている、といった悪循環を直視すべきだろう。以上、お屠蘇気分で私見を書かせて頂いたが半分でも実現すれば嬉しい。
看取りの実態が公表される時代に
謹んで新年の御挨拶を申し上げます。2010年に始まったこの連載もはや6年目になりました。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。さて今回は、最近の在宅医療・看取りの実態と今後の展望について私見を述べさせて頂きます。
数年前、読売新聞本紙で在宅看取り数が公表された。しかしこれは新聞社が独自に行ったアンケート調査の集計報告であった。一方、2006年から在宅療養支援診療所制度が始まり今年で10年目を迎えた。それに登録した医療機関は毎年厚労省に1年間の看取りの実績を報告する義務がある。2年前、週刊朝日のムックがその届け出の数字をそのまま掲載したことで、各医療機関が届けた在宅看取りの数が世間に公表されることになった。昨年も最新版が公表されたが、厚労省に届け出た数字以外に週刊朝日が独自に割り出した「在宅看取り率」という数字までもが掲載された。しかしこの算出方式には問題がある。施設での看取りがまったく評価されていないのである。実は施設での看取りは、居宅での看取りより難しいことがよくある。そこで施設での看取りを軽視するのはおかしいとの指摘をした。その結果、11月に発売された週刊紙本体では首都圏と大阪・兵庫県のみではあるが、看取りの実績が年間5件以上ある医療機関のみが、在宅看取り率は取り消した形で転載された。つまり看取りの実績のある在宅療養支援診療所のリストが公表された。
こうした動きに異を唱える人も当然いる。しかし私はかねてより診療所機能も病院機能と同様に情報公開すべきであると主張してきたので異論は無い。むしろ医師会入会の有無や在宅療養支援診療所に登録していないが実績のある診療所、さらには看取りの実績のある訪問看護ステーションの公表なども視野に入れてもいいのではとさえ考えている。特別養護老人ホームや老人保健施設やグループホームやサービス付き高齢者向き賃貸住宅などの施設での看取りが謳われているが、実態調査を行うと施設間のばらつきが極めて大きい。やはり看取りの実態の公表は時代の流れだと思う。
増加する在宅医療へのクレーム
私は全国在宅療養支援診療所連絡会の世話人を拝命している関係もあるのか、講演時などに在宅医療へのクレームを耳にすることが年々増えている。そもそも在宅医療機関へのクレームには、医師会との関係性や経営状況に関する感情的なものも含まれるので、それらの因子を排除したクレームだけを抽出してみたい。一番多いのは、患者と在宅主治医と関係性に関するクレームである。以前は、臨床経験が豊富な医師が良好な関係性を構築していた。しかし最近は、利益追求型の営利法人がバックについている診療所の臨床経験が少ない医師へのクレームが増えている。在宅療養支援診療所は営利目的ではなく、地域貢献でなくてはいけない。そして充分な臨床経験がある医師こそが在宅医療を担う資格があると考える。
2番目に、緊急往診をしないとか看取りをしないというクレームである。たしかになにか変化があると全例救急車で病院搬送にする在宅医や看取りをはっきり嫌がる医師もいる。しかし厳密には在宅療養支援診療所制度の契約条項に違反しているので法的にも問題がある。前出の週刊紙には厚労省に届けられた年間の緊急往診の数も公表されているが、市民にはそのような数字の持つ意味を解説して在宅医療の啓発を行っている。
一方、在宅におけるリスクマネジメントにおいても病院同様、大きな課題を孕んでいる。密室性、閉鎖性があるが故、リスクマネジメントにはより透明性、公平性が期待される。在宅医療における医療訴訟はまだ表にはあまり出ていないが、今後増加するであろう。以下に述べる診療の質の評価に加えて、在宅におけるリスクマネッジメントも今後の大きな課題である。
在宅医療の質の評価
私は病院経営とは無縁であるが、御縁あって療養病床を中心とした日本慢性期医療協会(日慢協)の役員も拝命している。日慢協に入会されている慢性期病院における診療の質の評価システムは素晴らしいものがあることを知ることになった。協会で独自に調査項目を決めて自己採点して公表し、切磋琢磨しているのだ。一方、北海道のある地区のグループホーム協会では、300を超えるチェック項目をお互いに評価しあい、それを公表するという方法で介護の質の担保を行っている。このように医療の質や介護の質の評価は今後の課題である。翻って在宅医療の世界ではどうであろうか。従来からの閉鎖的、密室的という批難を真摯に受け止める時期に来ている気がする。国民の評価に耐えられる在宅医療の質の評価システムの構築は急務であろう。
ただ在宅医療の質の評価は難しい側面も多い。現在、年間看取り数と往診数だけで評価されているが、看取りはあくまで結果なので、その数字だけで評価することは適切ではない。ただし年間数例以上の看取りがあれば、とりあえず看取りの実績がある診療所であると言えよう。しかしがんと非がんでは看取りまでの期間や看取り率に大きな差がある。私の診療所においては、年間90人の看取りのうちがんと非がんが半数ずつであるが、在宅看取り率でみると前者は90%であるのに対し、後者は40%程度である。
以上から、年間の看取り数はがんと非がんに分けて報告するようにしてはどうだろうか。また居宅と施設に分けてそれぞれの在宅看取り数と看取り率を記載してはどうか。その診療所の機能がよく分かる。さらに地域の医師会などが主催する多職種連携の会への参加実績も届け出項目に加えるべきであろう。今後は地域包括ケアや研修医教育などにどれだけ参画しているかも数値化して「質の評価」に加えるべきであろう。それを満たしてはじめて機能強化型と呼べるのであろう。
在宅医療から地域包括ケアへ
この3年間、全国各地で在宅医療の講演を行ってきた。そして「在宅医療という言葉はもう古い。これからは地域包括ケアだ」と言い続けてきた。在宅療養支援診療所の重大な責務のひとつはまさに地域包括ケアへの参画である。一方、高い診療報酬だけを取っている在宅療養支援診療所がある。
今春の診療報酬改訂は地域包括ケアという国策を実現するための改定にして欲しい。蛇足であるが多剤投与に関しても開業医にいくらペナルテイを課しても解決にはならない。病院から10種類以上の投薬が書かれた紹介状を持ってこられることは日常であるからだ。一方、患者への地域包括ケアの啓発も急務だ。医療機関に有利な改定は、当然患者側から見れば不利な内容でなる。目先の損得勘定ではなく患者側から見ても公平感のある改訂が望まれる。
介護保険との同時改定を待てない項目もある。たとえば10年前から書籍や雑誌等で指摘し続けている訪問看護の診療報酬体系である。訪問看護は依然として医療保険と介護保険の狭間に落ちたままである。いくら在宅推進という旗を掲げても、ケアマネが介護保険下の訪問看護を拒むといいう歪んだ実態が一部では続いている。こう言うと必ず「特別指示書に逃げればいいではないか」と言われるが、抜本的な制度改変が本筋であると考える。すべての訪問看護を医療保険下に戻して頂かないと、そして医療保険下のみなし訪問看護もさらに活用できるような仕組みにしないと地域包括ケアの推進は期待できない。訪問看護制度の改善こそが、医療と介護の連携を促進させると思う。しかし制度自体が足かせになっている現状は、2025年問題を乗り越えるのは困難ではないか。在宅医の24時間対応に関しても地域の慢性期病院との連携強化で乗り切るという考え方はどうか。そのほうが合理的ではないか。大病院や急性期病院が軽症者や慢性期医療の対象者の受け皿になっている。だから慢性期病院がそこに入れない重症患者の受け皿になっている、といった悪循環を直視すべきだろう。以上、お屠蘇気分で私見を書かせて頂いたが半分でも実現すれば嬉しい。

- << 抗認知症薬の増量規定
- HOME
- 脳疲労概念は万病に通じる >>
このたびURLを下記に変更しました。
お気に入り等に登録されている方は、新URLへの変更をお願いします。
新URL http://blog.drnagao.com
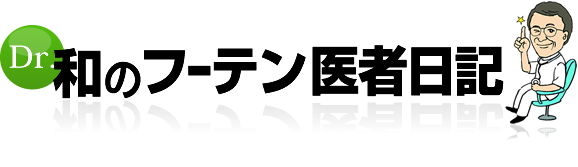


 応援クリックお願い致します!
応援クリックお願い致します!




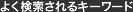
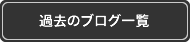
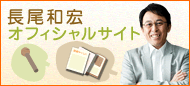
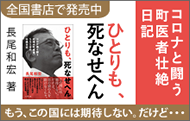
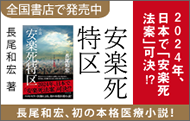
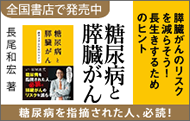
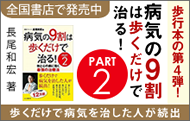
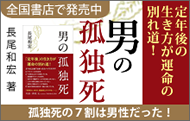
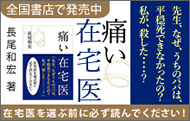

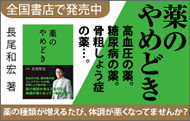
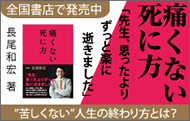
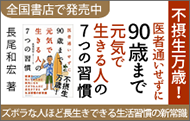
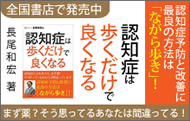
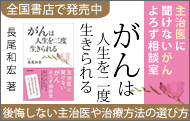
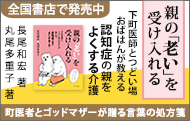
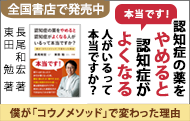


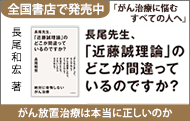
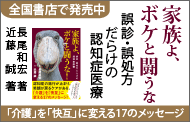
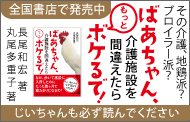

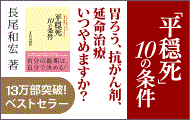
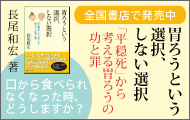

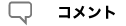
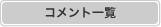

この記事へのコメント
最近の在宅医療の実態と展望 ・・・・・・ を読んで
お屠蘇気分で私見を ・・・・、という下りを読んで
人間お酒が入ると本音〔本性〕が出ることが多い
ので、ブログの内容に期待が膨らみました。
まず最初に長尾先生の“在宅医療も年々変わっていく。
しかし医療の本質は永遠に変わらないと信じている”
という記述が目に飛び込んできて、長尾先生のお考え
になっている“医療の本質”を知りたいと思いました。
長尾先生は、医療は、“老病死”の全てを診て、各人の
QoL〔或いは、DoL〕の維持・支援を行うことと考えら
れておられるのでしょうか?
なお、“在宅療養支援診療所は営利目的ではなく、地域
貢献でなくてはいけない。 そして充分な臨床経験がある
医師こそが在宅医療を担う資格があると考える”と言う
記述を拝見して、そうであったら嬉しいと感じました。
でも、在宅療養支援診療所の本務が地域貢献であること
は望ましいのですが、営利目的ではいけないんでしょう
か? 医療行為は算術が主になってはいけないとは思い
ますが、質の高いサービスを継続して提供し続けるため
には、適度の利益が確保される必要があることも現実と
思います。
理想は高く掲げ、そしてその理想の実現に向けて活動
して行くことが、より良い医療に繋がると思っています。
多職種連携、地域組織との関わりが進み、在宅医療が
より良い方向に進んで、結果として“地域包括ケア”
の枠組みが出来上がると理想的と思っています。
長尾先生の見られた“初夢”が、“正夢”となることを
心より祈念したいと思います。
Posted by 小林 文夫 at 2016年01月14日 10:39 | 返信
本来、我々一般人が手にする機会は殆ど無いような、医療者向け出版物への御寄稿を当たり前の
ように、毎日ブログ掲載して下さり、読むことが出来るという情報公開の有難さを、ふと思いました。
長尾先生のオープンマインドにより、医療従事者向けに限った内容ではなく、広く国民にも共有の
理解を求める内容となっていて、地域医療従事者に情報公開の必要性を求め、円滑な地域包括ケア
システムの構築、前進を願う思いが伝わりました。
一誌完結な内容ではなく、出版物のタイトルこそ異なれど、連続性の意味ある趣旨、構成になって
いるように読み受けました。
長尾先生の思いに「節目」を意識なさっておられるのを感じる昨今です。新春号だからでしょうか。
それとも、その気配を感じるのは、「刹那」の空気感なのでしょうか。
Posted by もも at 2016年01月14日 10:19 | 返信
私の母のケアマネジャーは、大学卒の社協傘下の社会福祉士ですけど、訪問看護師をサービスの中に入れてくれました。
母の友達(女性)の時は、社会福祉士のケアマネジャーでしたけど、その時は、女性利用者の知り合いの開業医師の奥さんが、何故か主導権を握ってしまって、まるで自分がケアマネジャーであるかのように、女性利用者を、隣町の老健に入れようとしました。偶然女性利用者が病院に入院中に、転倒骨折して、老健が受け入れ拒否したので、死んだ主人の姪が出て来て、財産を全部盗んで、結局安い施設に入れられましたけど。
ケアマネジャーの資格が無いのに、ケアマネジャーの如くに指導権を握る人もいます。
善意からそうなるのだとは、分かるのですけど、ちょっと困ります。
Posted by 匿名 at 2016年01月17日 12:56 | 返信
コメントする
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL: