- << 効果的なペナルテイとは
- HOME
- 認知症「放置療法」 >>
このたびURLを下記に変更しました。
お気に入り等に登録されている方は、新URLへの変更をお願いします。
新URL http://blog.drnagao.com

医療における「家族という病」
2016年01月27日(水)
公論2月号 医療における“家族という病 ” 長尾和宏
医療においても、最大の課題は「家族という病」
昨年の年間ベストセラーの第二位は「家族という病」(下重著)であった。これは個人が家族という枠に縛られることなく、もっと自由に生きてもいいのではないかという提言であると理解した。今回、医療現場も「家族という病」に苦しんでいることをお話ししたい。
病院においても診療所においても、ましてや在宅医療においてもエネルギーの多くの割合は家族への対応に費やされている。いわゆるクレーマー家族だけでなくもはや意思表示ができなくなった認知症の人の意思決定の場面では、大半のエネルギーが家族に費やされている。こういう現実は、意外に市民に知られることはない。高齢者に偶然見つかったがんの手術をするかしないのか、そして抗がん剤治療をするかしないのか、その意思決定はみんな家族に委ねられることになる。その結果、家族から訴えられないための医療、すなわち“デフェンス・メデイシン”になりがちである。それが医療費を押し上げている一因であることはあまり知られていない。
本人と家族の想いが相反する時
終末期医療においては、本人の意思と家族の意思が相反することが稀ではない。それどころか一致することはあまり無い、と言ってもいい。高齢者への胃ろう造設が何十万人にも増えたのは医者が延命治療が好きとは限らない。家族の希望に逆らいきれなかった一面もある。マスコミ報道で「胃ろう=悪」と刷り込まれると、今度は「胃ろうは良くないらしいから鼻からチューブにしてくれ」と希望する家族が増えている。本人の希望や尊厳より、家族の意思に従わないと訴えられる。これが日本の医療の特徴である。
もう少しで平穏死に至りそうだけど、もう少しだけ待っていてね。在宅医療で看取りをする前にそう願う時がある。しかし現代社会において「待つ」ということは、医療職にとっても家族にとっても大変な技である。終末期以降は「待つ」ことが最大の緩和ケアである。そう言っても理解できる家族は少ない。
「あなたさえいなければ・・」。そう叫びたくなる時がある。最後の最後に見たことがない遠くの長男・長女がいきなり現れて、ちゃぶ台返しをした時だ。患者さん自身といくら懇意になりその人に寄り添う医療をやろうとしても、家族にいとも簡単に切り捨てられる事がある。
終末期医療の意思決定
日本の終末期医療における最大の課題も家族の存在と言ってもいい。自己決定権が確立している欧米では、リビングウイルや事前指示書が普及しているため家族の問題は小さい。しかし我が国では、家族の権限があまりに大きい。2014年の調査によると、人生の最終段階の医療は、3分の2は家族が決めていたという結果であった。遠くの長男、遠くの親戚が終末期医療を決定している。たとえリビングウイルを書いていても法的担保が無いため、本人の意思が無視され家族の意思を優先せざるを得ない場合がある。あるいは、本人がリビングウイルを提示しても、医療者側が家族からの医療訴訟を恐れるため本人の意向に添えなかったことも少なからずある。(一般公益財団日本尊厳死協会の調査)
“おひとりさま”はどうだろう。日本は、核家族化が進み、単身世帯が増加している。いくら仲のいい夫婦でも2人同時に死ぬことはまずないので、“おひとりさま”が増加している。2014年の日本在宅医学会において「おひとりさまの看取り」というシンポジウムがあり、筆者も講演した。このシンポジウムの結論は「今後“おひとりさま”が増えるが、最期まで自宅で過ごすことは決して難しくない」であった。もちろん医師不足に悩む地方ではそうはいかない所もあるだろうが、在宅医療資源が豊富な都市部では充分可能であること分かっている。筆者も「おひとりさまの看取り」を普通に行っている。天涯孤独の“おひとりさま”の場合、本人がそれを望めば100%平穏死が叶うということを書籍や講演で啓発している。ただし口頭ないしできれば文書によるリビングウイルがあることが前提となる。
親の「老い」を受け止める
いくら偉大な親であっても必ず老いる。老いは、認知機能の低下や運動機能の低下をはじめ様々な形で表れる。それぞれの専門医を受診して回っても、いくつもの診断名と処方薬が重なるだけだ。どんなに医学を駆使しても老いには絶対に勝てない。本人は、「もうこれでいい」と言っていても、子供たちが「もっと、もっと」と医療を要求するケースをよく見かける。特に認知症において顕著である。認知症だから薬を、認知症だから施設を、と子供世代は必死で名医探しをする。認知症ケアで一番大切なはずの、本人の心地よい環境づくりが忘れられている。そんな気持ちで「ばあちゃん、介護施設を間違えたらもっとボケるで!」、そして「家族よ、ボケと闘うな!」(ブックマン社)の2冊を世に問うた。
私たちの世代(50代、60代)は、平和でそこそこ豊かな時代を享受してきた。同時に医学と医療の進歩も見てきた世代である。その一方、老いや死を見たことが無い、考えたこともないという人が少なくない。右肩上がりが当たり前の世代には、右肩下がりは受け止めることが難しい。認知症も平穏死も「老い」である。自分の親の「老い」を受け入れられない子供世代が増えている。しかし彼らがそれぞれの医療の意思決定の主導権を握っている。2年前からその事に気がつき子供世代に向けた本を数冊書いた。そして昨年末「親の老いを受け止める」丸尾多重子氏との共著、ブックマン社)が出版された。本書が世代を超えて「老い」を考えるきかっけになれば幸いである。
医療においても、最大の課題は「家族という病」
昨年の年間ベストセラーの第二位は「家族という病」(下重著)であった。これは個人が家族という枠に縛られることなく、もっと自由に生きてもいいのではないかという提言であると理解した。今回、医療現場も「家族という病」に苦しんでいることをお話ししたい。
病院においても診療所においても、ましてや在宅医療においてもエネルギーの多くの割合は家族への対応に費やされている。いわゆるクレーマー家族だけでなくもはや意思表示ができなくなった認知症の人の意思決定の場面では、大半のエネルギーが家族に費やされている。こういう現実は、意外に市民に知られることはない。高齢者に偶然見つかったがんの手術をするかしないのか、そして抗がん剤治療をするかしないのか、その意思決定はみんな家族に委ねられることになる。その結果、家族から訴えられないための医療、すなわち“デフェンス・メデイシン”になりがちである。それが医療費を押し上げている一因であることはあまり知られていない。
本人と家族の想いが相反する時
終末期医療においては、本人の意思と家族の意思が相反することが稀ではない。それどころか一致することはあまり無い、と言ってもいい。高齢者への胃ろう造設が何十万人にも増えたのは医者が延命治療が好きとは限らない。家族の希望に逆らいきれなかった一面もある。マスコミ報道で「胃ろう=悪」と刷り込まれると、今度は「胃ろうは良くないらしいから鼻からチューブにしてくれ」と希望する家族が増えている。本人の希望や尊厳より、家族の意思に従わないと訴えられる。これが日本の医療の特徴である。
もう少しで平穏死に至りそうだけど、もう少しだけ待っていてね。在宅医療で看取りをする前にそう願う時がある。しかし現代社会において「待つ」ということは、医療職にとっても家族にとっても大変な技である。終末期以降は「待つ」ことが最大の緩和ケアである。そう言っても理解できる家族は少ない。
「あなたさえいなければ・・」。そう叫びたくなる時がある。最後の最後に見たことがない遠くの長男・長女がいきなり現れて、ちゃぶ台返しをした時だ。患者さん自身といくら懇意になりその人に寄り添う医療をやろうとしても、家族にいとも簡単に切り捨てられる事がある。
終末期医療の意思決定
日本の終末期医療における最大の課題も家族の存在と言ってもいい。自己決定権が確立している欧米では、リビングウイルや事前指示書が普及しているため家族の問題は小さい。しかし我が国では、家族の権限があまりに大きい。2014年の調査によると、人生の最終段階の医療は、3分の2は家族が決めていたという結果であった。遠くの長男、遠くの親戚が終末期医療を決定している。たとえリビングウイルを書いていても法的担保が無いため、本人の意思が無視され家族の意思を優先せざるを得ない場合がある。あるいは、本人がリビングウイルを提示しても、医療者側が家族からの医療訴訟を恐れるため本人の意向に添えなかったことも少なからずある。(一般公益財団日本尊厳死協会の調査)
“おひとりさま”はどうだろう。日本は、核家族化が進み、単身世帯が増加している。いくら仲のいい夫婦でも2人同時に死ぬことはまずないので、“おひとりさま”が増加している。2014年の日本在宅医学会において「おひとりさまの看取り」というシンポジウムがあり、筆者も講演した。このシンポジウムの結論は「今後“おひとりさま”が増えるが、最期まで自宅で過ごすことは決して難しくない」であった。もちろん医師不足に悩む地方ではそうはいかない所もあるだろうが、在宅医療資源が豊富な都市部では充分可能であること分かっている。筆者も「おひとりさまの看取り」を普通に行っている。天涯孤独の“おひとりさま”の場合、本人がそれを望めば100%平穏死が叶うということを書籍や講演で啓発している。ただし口頭ないしできれば文書によるリビングウイルがあることが前提となる。
親の「老い」を受け止める
いくら偉大な親であっても必ず老いる。老いは、認知機能の低下や運動機能の低下をはじめ様々な形で表れる。それぞれの専門医を受診して回っても、いくつもの診断名と処方薬が重なるだけだ。どんなに医学を駆使しても老いには絶対に勝てない。本人は、「もうこれでいい」と言っていても、子供たちが「もっと、もっと」と医療を要求するケースをよく見かける。特に認知症において顕著である。認知症だから薬を、認知症だから施設を、と子供世代は必死で名医探しをする。認知症ケアで一番大切なはずの、本人の心地よい環境づくりが忘れられている。そんな気持ちで「ばあちゃん、介護施設を間違えたらもっとボケるで!」、そして「家族よ、ボケと闘うな!」(ブックマン社)の2冊を世に問うた。
私たちの世代(50代、60代)は、平和でそこそこ豊かな時代を享受してきた。同時に医学と医療の進歩も見てきた世代である。その一方、老いや死を見たことが無い、考えたこともないという人が少なくない。右肩上がりが当たり前の世代には、右肩下がりは受け止めることが難しい。認知症も平穏死も「老い」である。自分の親の「老い」を受け入れられない子供世代が増えている。しかし彼らがそれぞれの医療の意思決定の主導権を握っている。2年前からその事に気がつき子供世代に向けた本を数冊書いた。そして昨年末「親の老いを受け止める」丸尾多重子氏との共著、ブックマン社)が出版された。本書が世代を超えて「老い」を考えるきかっけになれば幸いである。

- << 効果的なペナルテイとは
- HOME
- 認知症「放置療法」 >>
このたびURLを下記に変更しました。
お気に入り等に登録されている方は、新URLへの変更をお願いします。
新URL http://blog.drnagao.com
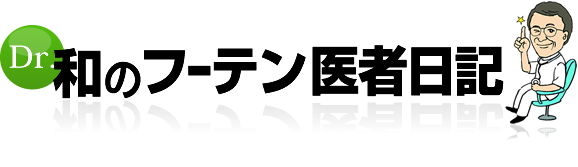


 応援クリックお願い致します!
応援クリックお願い致します!




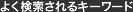




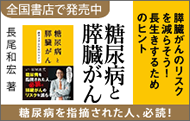







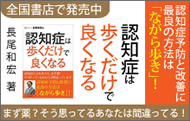

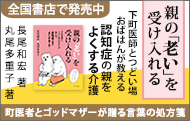
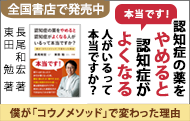


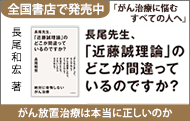
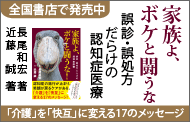
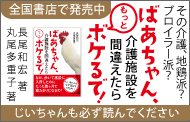

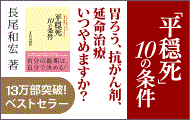
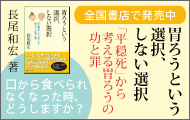

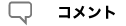


この記事へのコメント
認知症とクスリの関係について
今後10年間で高齢者の五人に一人は認知症になる、という報道がありますが、現在の認知症といわれている患者を含めて、投薬中心の医療制度が作り出した「認知症」が多いのではないでしょうか。
読売新聞のyomiDr.佐藤記者の「新・精神医療ルネサンス」に「高齢者の2割にベンゾ処方 118万人調査で判明」という記事が出ています。
http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=129472
日本人は専門職崇拝が強く医師はその頂点です。医師が処方したクスリはきちんと飲まなければいけません、といった考えが強いので、医師を信用して言われたとおりにクスリを服用し続けた人ほど、高齢になってから、認知症らしき症状を呈するようになるのではないでしょうか。
医療費削減目的で、受診するハードルが高くなって、たとえ受診しても処方される薬が減れば、認知症を筆頭に患者数も減るのではないかと思います。
Posted by 匿名 at 2016年01月27日 02:41 | 返信
日本で開発されたあの認知症治療薬が使われていなければ、認知症患者の多くは歩行困難〜寝たきりになっていなかったのではないかの思いますね。認知症治療薬を何も飲んでいなかった終末期アルツハイマーの患者が、まったくコミュニケーションできなくても元気でニコニコしてピンピンして普通に歩いていたのを思い出します。ベンゾも良くない薬だけどそれ以上にタチが悪い。この薬出されると、高い確率で例の統合失調症の治療薬が必要になる。相乗効果で早々に歩けなくなりますからね。
このような薬害がなければ胃瘻対象ケースも減るような気がします。
終末期医療の問題は本人が決めるべきですね。日本人の場合は本人の意志ではなく家族の都合で決められてしまうので、おかしな話です。家族に本人の運命を決める権利はないでしょう。
Posted by マッドネス at 2016年01月27日 07:37 | 返信
買い物から帰ったら、母が動かない状態で、脈もありませんでした。
主治医は丁度、研究会に参加して近くにいなかったので、電話で相談して消防署の救急車に来て貰いました。
救命措置をしながら、近くの救急病院に入院しましたが、心肺停止状態でした。
CTスキャンをかけたら、胸部動脈剥離でした。
死因が明確だったとお医者さんが診断して下さったので、警察の検視はありませんでした。
「多分痛みも苦しみも無かったと思いますよ。お顔も楽しそうなお顔です」とお医者さんに言って頂いたのがせめてもの救いでした。
へるぱーさんや訪問看護師さんや、主治医の先生や、その他大勢の方にお世話になって、自宅で平穏に死ねたことを、感謝しています。
母には親不幸な娘だったことを、詫びています。
Posted by 大谷佳子 at 2016年01月28日 12:14 | 返信
大谷様
御母上はきっと笑っておられます。「どうして詫びるの?」って。
心残りのない永久の別れは、有り得ないと思います。
私も、母との永久の別れに、たくさんの心残りがあります。
けれども、後悔は、していません。
それしか、できなかったから。
私は、母を過剰医療から守りましたが、自宅で世話をすることも、自宅で死なせることも、選択しませんでした。
父も、過剰医療からは私が守り抜きます。けれども、私が自宅で父を世話することはあり得ません。自宅で看取ることも、あり得ません。
そういう家族も、あるのです。
介護や看取りに、正解はありません。
介護や看取りに、ランクはありません、上下もありません、評価もありません、孝・不孝もありません。
どんな家族も、必死で、親とかかわりながら生きています。
大谷様のお世話で、納得できる終末期を過ごせて、御母上はお幸せでした。
どうか、御身大切に。
お元気で。
Posted by 鬼娘 at 2016年01月28日 03:19 | 返信
最近 思うこと…
緩和って 誰がやりたいの?…と
医師が考えた緩和ケアであって
家族が緩和されたいってことでしょうか
末期ガンの方…
在宅看取りでした
選ばれし者しか 在宅看取りはできません
在宅医が
オキファスト(医療用麻薬)の点滴指示を出してきた
本人が 「やってくれ!」と訴えたのか?
ご家族に聞くと
本人は やって欲しいとは 言っていない
見てるご家族が苦しそう 痛そうに見えるから…と
病院に入院であれば 中途半端なインフォードコンセントをして 麻薬の開始となります
在宅ならば
在宅だからこそ
ご本人に ご自分の最期を聞いてください
ご本人を無視して 方針を決めるなんて 許せません
薬でしか疼痛コントロールガできないと思っていらしゃるお医者さま…
危険です
Posted by 訪問看護師 宮ちゃん at 2016年01月29日 12:04 | 返信
『痛み』ほど、漠然としたものは無いような気もします。
痛い感覚は本人でしか感じる事はできないものです。患者が「痛い!」と訴えた時に画像や症例から
「こうであろう..」という診断が下るだけのものであって、実際に苦痛の表情と表現によって
事実か否かであるとか、その大小を推し量るものであると..文章にすると、そのようなものかな..と
思います。
けれども、実際に神経に触れる肉体の痛み以上に『心』が痛む時には、数値や経験値からは推測でき
ない「未知の痛み」が生じます。
それが「スピリチュアルペイン」の所以でしょうか..。
実際には、何かが肉体の神経に触れて激痛が走るという状態とは異なる、その症状の対処の方が
難解であり、これを理解できる医師を『名医』と称するのかも知れません。
Posted by もも at 2016年01月29日 12:47 | 返信
最近 思うこと…
緩和って 誰がやりたいの?…と
医師が考えた緩和ケアであって
家族が緩和されたいってことでしょうか
末期ガンの方…
在宅看取りでした
選ばれし者しか 在宅看取りはできません
在宅医が
オキファスト(医療用麻薬)の点滴指示を出してきた
本人が 「やってくれ!」と訴えたのか?
ご家族に聞くと
本人は やって欲しいとは 言っていない
見てるご家族が苦しそう 痛そうに見えるから…と
病院に入院であれば 中途半端なインフォードコンセントをして 麻薬の開始となります
在宅ならば
在宅だからこそ
ご本人に ご自分の最期を聞いてください
ご本人を無視して 方針を決めるなんて 許せません
薬でしか疼痛コントロールガできないと思っていらしゃるお医者さま…
危険です
Posted by 訪問看護師 宮ちゃん at 2016年01月29日 01:50 | 返信
長尾先生は本当に「中庸」なのだろうか。と時々思う。
Posted by もも at 2016年01月29日 06:12 | 返信
コメントする
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL: