このたびURLを下記に変更しました。
お気に入り等に登録されている方は、新URLへの変更をお願いします。
新URL http://blog.drnagao.com

糖尿病治療のやめどき
2016年09月30日(金)
糖尿病治療薬には、8系統ある。
でもいつまで飲むのか?打つのか?
やめどきがあるのか?無いのか?
でもいつまで飲むのか?打つのか?
やめどきがあるのか?無いのか?
ちゃんと答えられる医者はいないだろう。
では一生、やるのか?
まさかそんなことは無い(だろう)。
始める時があるなら、止める時もある。
産経新聞の連載にはそこまで書けないので
とりあえず、どんな薬があるのかだけ書いた。→こちら
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
産経新聞・糖尿病シリーズ第4回 2型糖尿病の薬
病態や重症度に応じて使い分ける
現在、糖尿病の治療に使われているお薬は大ざっぱに分けて、飲み薬が7種類とインスリン注射薬など合計8種類ほどあります。それぞれに特徴がありその人の糖尿病の病態や重症度に応じて使い分け、併用されることも多くあります。飲み薬は「インスリンの効きをよくする薬」と「インスリンの分泌を促す薬」と「糖の吸収や排出を調節する薬」の3つに大別されます。「インスリンの効き方をよくする薬」の代表は、主に肝臓に作用するビグアナイド系と主に脂肪組織に作用するチアゾリジン系があります。一方、「インスリンの分泌を促す薬」には、速効型インスリン分泌促進薬やスルホニル尿素剤(SU剤)やDPP-4阻害薬などがあります。速効型インスリン分泌促進薬はすぐに効いて効果もすぐに消えるので食後血糖が高い人に適しています。低血糖は起こしにくいのですが1日3回食前に飲むのが難しい人もいます。SU剤は膵臓に働いてインスリン分泌を促進しますが低血糖を起こし易いタイプになります。
DPP-4阻害薬は食後に小腸からブドウ糖が吸収されるとサインが出てインスリンが分泌されますが、そのサインを強める薬です。作用機序が生理的なので低血糖が起こりにくいのが最大の利点です。1日1回タイプが主流ですが2回タイプもあります。また最近は、週に1回だけ服用すればいいという便利な薬も登場しました。そして3番目の「糖の吸収や排出を調節する薬」としてαグルコシダーゼ阻害薬(αGI)があります。これは小腸からのブドウ糖の吸収を遅らせて食後の急激な血糖上昇を抑える薬です。また2014年に発売されたSGLT2阻害薬があります。これは血液中の糖分を尿へと排出を促す薬で、「やせる糖尿病薬」として大きな注目を集めています。ただし尿中の糖分が増えるので尿路感染症にかかりやすくなるという心配があります。また特に高齢者では脱水も懸念されます。従って比較的若くて体力があり肥満傾向の人に選択される薬剤です。そして最後にインスリン製剤があります。これも24時間効いている持効型から3~4時間ほどで効果が消える超速効型、そして速効型と中間型などをさまざまな割合で混ぜた混合製剤などさまざまなタイプのインスリンがあります。
思い起こせば私が医者になった時には3系統しかなかった薬が現在は8系統にまで増えました。ひとりひとりの病態に対応できるよう治療の幅が広がったことは糖尿病学の大きな進歩です。糖尿病と診断され2~3系統の薬を飲んでいる人は珍しくありません。あるいは飲み薬とインスリンを併用している人もたくさんいます。しかしどの系統の薬も長所と欠点があります。私が一番気にする副作用はなんといっても低血糖です。これを繰り返すと認知症になり易い。また意識レベルが低下して転倒すれば命に関わります。
糖尿病の薬を飲んでいる人は、自分が飲んでいる薬が3つの系統のどこに分類されている薬なのか、そしてどんな副作用があるのかをよく知っておく必要があります。医者任せのまま漫然と飲んでいては低血糖で痛い目に合うかもしれません。薬は納得して注意して使うべきです。そして薬は最終手段であることも決して忘れないでください。今日述べた2型糖尿病は生活習慣病ですから、やはり食事療法と運動療法のほうが薬より優先します。
キーワード 2型糖尿病
糖尿病には1型と2型がある。1型は膵臓のβ細胞が壊れてインスリンが全く出ないのでインスリン注射が欠かせない病態。一方2型は生活習慣の乱れからインスリン分泌が低下したり効きが悪くなる病態。
では一生、やるのか?
まさかそんなことは無い(だろう)。
始める時があるなら、止める時もある。
産経新聞の連載にはそこまで書けないので
とりあえず、どんな薬があるのかだけ書いた。→こちら
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
産経新聞・糖尿病シリーズ第4回 2型糖尿病の薬
病態や重症度に応じて使い分ける
現在、糖尿病の治療に使われているお薬は大ざっぱに分けて、飲み薬が7種類とインスリン注射薬など合計8種類ほどあります。それぞれに特徴がありその人の糖尿病の病態や重症度に応じて使い分け、併用されることも多くあります。飲み薬は「インスリンの効きをよくする薬」と「インスリンの分泌を促す薬」と「糖の吸収や排出を調節する薬」の3つに大別されます。「インスリンの効き方をよくする薬」の代表は、主に肝臓に作用するビグアナイド系と主に脂肪組織に作用するチアゾリジン系があります。一方、「インスリンの分泌を促す薬」には、速効型インスリン分泌促進薬やスルホニル尿素剤(SU剤)やDPP-4阻害薬などがあります。速効型インスリン分泌促進薬はすぐに効いて効果もすぐに消えるので食後血糖が高い人に適しています。低血糖は起こしにくいのですが1日3回食前に飲むのが難しい人もいます。SU剤は膵臓に働いてインスリン分泌を促進しますが低血糖を起こし易いタイプになります。
DPP-4阻害薬は食後に小腸からブドウ糖が吸収されるとサインが出てインスリンが分泌されますが、そのサインを強める薬です。作用機序が生理的なので低血糖が起こりにくいのが最大の利点です。1日1回タイプが主流ですが2回タイプもあります。また最近は、週に1回だけ服用すればいいという便利な薬も登場しました。そして3番目の「糖の吸収や排出を調節する薬」としてαグルコシダーゼ阻害薬(αGI)があります。これは小腸からのブドウ糖の吸収を遅らせて食後の急激な血糖上昇を抑える薬です。また2014年に発売されたSGLT2阻害薬があります。これは血液中の糖分を尿へと排出を促す薬で、「やせる糖尿病薬」として大きな注目を集めています。ただし尿中の糖分が増えるので尿路感染症にかかりやすくなるという心配があります。また特に高齢者では脱水も懸念されます。従って比較的若くて体力があり肥満傾向の人に選択される薬剤です。そして最後にインスリン製剤があります。これも24時間効いている持効型から3~4時間ほどで効果が消える超速効型、そして速効型と中間型などをさまざまな割合で混ぜた混合製剤などさまざまなタイプのインスリンがあります。
思い起こせば私が医者になった時には3系統しかなかった薬が現在は8系統にまで増えました。ひとりひとりの病態に対応できるよう治療の幅が広がったことは糖尿病学の大きな進歩です。糖尿病と診断され2~3系統の薬を飲んでいる人は珍しくありません。あるいは飲み薬とインスリンを併用している人もたくさんいます。しかしどの系統の薬も長所と欠点があります。私が一番気にする副作用はなんといっても低血糖です。これを繰り返すと認知症になり易い。また意識レベルが低下して転倒すれば命に関わります。
糖尿病の薬を飲んでいる人は、自分が飲んでいる薬が3つの系統のどこに分類されている薬なのか、そしてどんな副作用があるのかをよく知っておく必要があります。医者任せのまま漫然と飲んでいては低血糖で痛い目に合うかもしれません。薬は納得して注意して使うべきです。そして薬は最終手段であることも決して忘れないでください。今日述べた2型糖尿病は生活習慣病ですから、やはり食事療法と運動療法のほうが薬より優先します。
キーワード 2型糖尿病
糖尿病には1型と2型がある。1型は膵臓のβ細胞が壊れてインスリンが全く出ないのでインスリン注射が欠かせない病態。一方2型は生活習慣の乱れからインスリン分泌が低下したり効きが悪くなる病態。

このたびURLを下記に変更しました。
お気に入り等に登録されている方は、新URLへの変更をお願いします。
新URL http://blog.drnagao.com
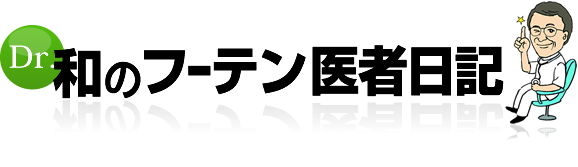


 応援クリックお願い致します!
応援クリックお願い致します!




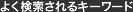
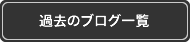
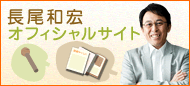
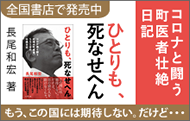
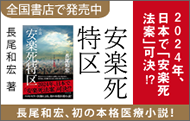
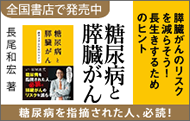
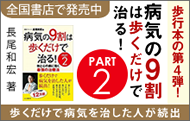
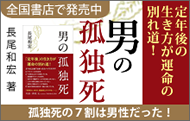
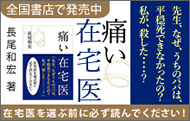

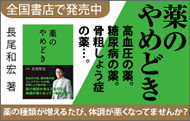
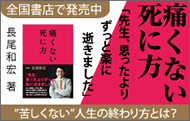
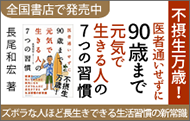
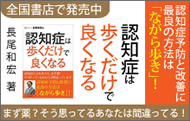
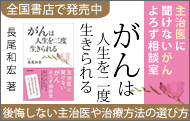
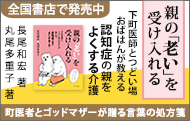
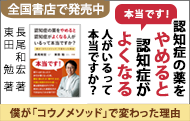


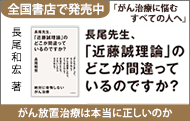
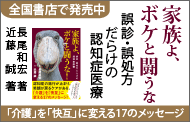
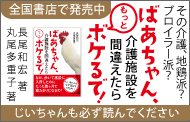

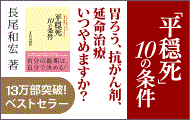
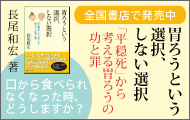

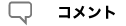
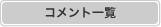

この記事へのコメント
止めとき、、
だれが、きめる。
おぎようこ
おこらんど
墨あそび詩あそび土あそび
Posted by おこ at 2016年09月30日 03:06 | 返信
「糖尿病になると、認知症になりやすい」というのは、お薬の影響で「低血糖になることを繰り返す」と認知症になりやすいのですね。すると、このお薬による低血糖を繰り返さないようにすれば、「認知症」になることは、ある程度予防できるかもしれませんね。少し安心できました。
Posted by 匿名 at 2016年09月30日 06:58 | 返信
コメントする
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL: