- << そもそも医師法21条とは
- HOME
- 自動車事故とてんかん >>
このたびURLを下記に変更しました。
お気に入り等に登録されている方は、新URLへの変更をお願いします。
新URL http://blog.drnagao.com

透析中止に関する偏向報道
2019年04月22日(月)
透析中止報道に賛意を示す人は、現場を知らないんだなあと思う。
続けたくても続けられない人や、導入を拒否される人もおられる。
一方的に医者を叩くだけのメデイアは、もはやメデイアではない。
続けたくても続けられない人や、導入を拒否される人もおられる。
一方的に医者を叩くだけのメデイアは、もはやメデイアではない。
信じられないほど酷い記事を、いくつか見かけた。
安楽死、殺人、逮捕、医師免許剥奪、裁判などなど。
これらはすべて医療現場を知らない人の誤解である。
あるいは、悪意のニセスクープででも新聞を売らんかな、か。
あるいは、終末期医療の現状を全く知らないのか。
透析で無限に生きられるわけではない。
44歳という年齢に動かされての偏向報道の嵐。
しかし44歳でも終末期であることはある。
そして患者や家族の希望も加わり中止せざるを得ないことも。
もしスキルス胃がんの末期の44歳の人が抗がん剤をやめたら・・・
はっきり言って意味不明の社説もある。→こちら
論理のおかしさの練習帳になるのでは。
一方、冷静なメデイアも、もちろんある。たとえば、
・「週刊新潮」4月11日号 「人口透析」中断死で渦中の院長が語った『高瀬舟』 →こちら
・「選択」4月号 「透析中止は悪ではない」 →こちら
・「読売新聞」4月10日 「終末期 透析続けますか」 →こちら
実情を知らない人がこれだけいるんだ、と驚かされた偏向報道。
日本医事新報4月号に、その歪みを書いてみた。→こちら
市民には、月刊公論5月号にも書いた。
「透析中止報道 問題の核心は何か」→こちら
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
日本医事新報4月号 透析中止報道に見るメデイアの自殺 長尾和宏
何が問題なのか
東京都福生市の公立福生病院で昨年8月、44歳の女性の人工透析を中止して亡くなったことを毎日新聞が3月7日の一面でスクープ記事として報じた。多くのメデイアも同様に「あるまじき行為」と大きく報じた。「医師は患者を死に至らしめる選択肢を提示していいのか」と。なかには「殺人だ」や「医師免許剥奪だ」と煽る報道もあった。今回、こうした一連の報道に感じたことを述べたい。
担当した外科医(50歳)は3月28日の会見で「透析続行のために必要な手術の準備をしていたが、女性に拒まれ、物理的に透析が不可能になった」と述べた。患者の意思を尊重したとし「できることは全部やらせてもらったつもりだ」と、問題はなかったとの認識を示した。院長もこの透析中止について倫理委員会を開くべきか事前に担当医から相談を受けた際、日本透析医学会の提言を参照した上で必要ないと判断した、とコメントした。死亡前日の本人からの透析再開の要請への対応も批難されている。しかし結果的に死亡前日の全身状態が不良だったなら透析を再開したくても、もはや透析ができない状態(ポイントオブノーリターン)だったのだろう。
私は当初から本例の何が問題なのか理解できなかった。独断で中止する透析医なんているわけない。やむをえず中止せざるを得ない状況だったに違いない。おそらく多くの医療者もそう感じたはずだ。透析をしたくても本人が強く拒否したり、高齢や全身状態が悪すぎたり家族の意向を受けて断念せざるを得ない事例が増えている。私自身も在宅で数例の非導入や中止例を経験している。
人工透析の非導入と中止
福生病院では過去4年間に149人の透析適応者がいて20人が非導入で5人が中止している。すなわち129人に透析が導入され、124人は死ぬまで続けたことになる。透析導入率は86%で、いったん導入後の完遂率は96%である。メデイアや有識者は「両方の数字とも100%でないといけない」、「一例でも完遂できなければ医者が殺した」と煽るが、単に現状を知らないだけではないのか。透析患者の高齢化や要介護度悪化が大きな社会問題になっている。そんななか「非導入は想定外」という日本透析医学会のコメントにもとても驚いた。
「シャントが詰まった=終末期」ではない。透析患者さんの終末期像とは全身状態が極めて悪く死期が近い、つまり多臓器不全と呼ばれる病態であろう。だからこの40代の女性の場合、シャントの閉塞とは関係なく本当に終末期であったのだろう。年齢に関係なく終末期になることはある。もしそうならば患者さんの意思を尊重した話し合いを繰り返した結果、中止に至ることはある。実際、中止の1週間後に亡くなっているので「終末期であった」と推定される。一方、もし終末期でなかったと判断されるならばそれはインフォームドコンセントの範疇なのか安楽死なのかについては議論の余地があろう。そもそも「透析をしなければ死に至る状態」であること自体が終末期だ、という考え方もある。
だから「透析中止 患者死亡」とか「20人非導入 全員死亡」という新聞の見出しに強い違和感を覚えた。透析治療は延命治療なので、中止すれば100%死ぬ。また導入しなければ100%死ぬ(はずだ)。当たり前である。もし死ななかったら、「不必要な透析だった」ことになり、そちらのほうが問題である。だから「重大事故が起きて全員死亡!」のような見出しは理解に苦しむ。透析をしてもしなくても誰にでも必ず「死」が訪れる、ということを知らない記者が書いているのだろうか。本人の意思を尊重して非導入や中止で大切な人の旅立ちを見守ったご遺族たちは今、どんな想いで一連の報道に接しているのか。その心中を案じる。
倫理委員会より人生会議を
亡くなった44歳女性の夫は「医師を恨んでいない」との手記を発表している。そもそも本例は事故でも事件でも裁判でもない。夫が「生きていて欲しかった」という悲嘆を記者に吐露しただけである。悲嘆といえば、昨年11月に「人生会議」という愛称が決まったACP(アドバンスケアプラニング)は本例においてどうだったのか。もし透析を中止したなら、2日後、3日後、4日後あたりの本来の透析日にも二度目、三度目の話し合い(人生会議)があったのだろう。
倫理委員会が開催されていないことを非難する報道も多いが、患者や家族抜きで第三者が別室で勝手に決めるほうが問題ではないのか。そもそも忙しい医療現場では開催は現実的でない。在宅でも非導入や中止で看取るケースが増えているが在宅には倫理委員会などない。在宅では非導入や中止の希望が出ればケアマネがケア会議に多職種を招集する。ご自宅で本人と家族の意向に耳を傾け多職種で何度も話し合って決めている。うつ病による自殺願望ではないことを確認して対話の積み重ねの中で決める。倫理委員会よりも人生会議である。
中止=死を待つことになるので、私の場合は本人意思を尊重し透析を中止した人は、毎日医師や看護師が訪問して、緩和ケアと並行して考えが変わらないか繰り返し確認している。また中止ではなく、透析導入を拒否して在宅看取りを希望される場合も同様である。中止後にどのような苦痛が予想されるのか、死に向かう過程と対処方法を説明する。報道は前日の再開希望メールへの対応を問題視しているが、その手前の中止後数日間の対応こそが重要である。死の前日、意識レベルが低下したせん妄状態に陥れば「苦しい、何とかして!」と訴えることがあるだろう。拙書『痛い在宅医』で描いたように「死の壁」の最中に打ったメールだったのかもしれない。その訴えは「再開」というよりも「苦痛から逃れたい」という緩和ケアの渇望のように感じた。予想される「死の壁」に対して私はモルヒネや安定剤の座薬で備えている。なによりも透析中止後の緩和ケアが重要であるが、それも提供されていたようだ。
患者さんを不幸にする偏向報道
人工透析患者数は年々増加し、2016年には約33万人いる。透析に至る原因の約4割は糖尿病性腎症だが、高齢化に伴う腎機能障害も増えている。年間医療費は約500万円かかるが公的助成制度でカバーされている。人工透析は医療機関側から見ると継続的安定的な患者が確保できるため一種の利権になったり安易な導入も指摘されている。一方、欧米では年齢制限がある国もある。また非導入・中止例は日常で、年々増加している。
そもそも透析をするかしないかの選択は、呼吸状態が悪化したときに人工呼吸器を装着するかどうか、食べられなくなったときに胃ろう栄養などの人工栄養を選択するかどうかと同じ話である。医師は、様々な選択肢があることを患者や家族に正しく説明する義務がある。その患者にとっての最善とは何かの対話するプロセスこそが重視されている。一緒に悩んで出た答えが正解なのだ。
それなのに今回のような煽り報道で多くの市民がミスリードされたことが残念である。偏向報道で不幸になるのは患者さんである。今後、「死ぬまでやめられないのなら最初からやめておこう」と迷っていた透析導入を拒否する患者さんが増えないだろうか。それが必要な人には提供するのが医療である。また倫理的に妥当な胃ろうの非開始や中止は減るのだろう。人生会議が国策となり慎重な対応を迫られているなか、医療現場の努力に水を差す偽善報道は有害である。透析関係者や医療界は世間の誤解を解くべきだ。塞翁が馬ではないが、今回のミスリードを正しい啓発に逆利用すべきだ。
そしてもし医者叩きで新聞を売るために書いているのであれば、まさにメデイアの自殺、新聞の終焉であろう。
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
ダイアモンドオンラインには、浅川さんの記事も流れている。
やっとまともな記事が出てきた。
透析中止事件で問われる「死の在り方」と「報道姿勢」
浅川澄一 2019/04/24 06:00
東京都福生市の公立福生病院での人工透析治療をめぐり、様々な疑問が浮上している。透析患者の死亡までの経過にとどまらず、
延命治療や終末期医療、腎臓移植、尊厳死、QOL(生活の質)、ACP(アドバンス・ケア・プランニング)など多くの検討課題が俎上に載ってきた。
「治療の中止」を許さない マスコミの報道姿勢への疑問
まず第1の問題といえるのが、報道姿勢が問われているメディアについて、だ。
3月7日の毎日新聞朝刊の「スクープ」が始まりだった。「医師、『死』の選択肢提示」「透析中止 患者死亡」「指針逸脱 都、立ち入り」という見出しを掲げる。前日に東京都が福生病院に立ち入り検査していた。
その日の夕刊で、読売新聞が「透析中止提示 患者が死亡」、日本経済新聞が「透析中止提案」とする見出しで追いかけた。翌日の朝刊では、朝日新聞が「人工透析を中止 女性死亡」「医師が選択肢提示」、産経新聞が「透析中止を提示 患者死亡」、東京新聞は「医師が『選択肢』提示」「医師の提案『倫理上問題』」とする見出しで掲載し、全国紙が一斉に取り上げることになった。
注目は、各新聞の見出しがほとんど同じこと。患者が死亡した原因は、医師が患者に透析の中止を提示したことで、問題だ、と訴えている。東京新聞の「倫理上問題」はその趣旨が最も分かりやすい見出しだ。
果たして、医師は透析の中止、その結果としての死について患者に説明してはいけないのだろうか、という疑問が真っ先に浮かんだ。医師は診察後に、あらゆる治療法を患者に説明すべきだろう。手術や服薬の種類など想定できる可能性は複数ある。そのうちのどれを選択するかは、患者の判断であろう。
提案できる選択肢の中に、「とことん治療する」「延命処置を望む」の一方、「治療をしない」あるいは「治療を中止、中断」して自然に任せる、という道が含まれてはいけないのだろうか。
この時の各紙は、医師から透析中止の提示を受けた患者は、医師に「誘導」されて死に追い込まれた、と読者に受け取らせるような論調であった。
終末期のがん患者に病名を告知しなかった時代に戻れ、と言わんばかりの論調には違和感がある。治療の拒絶から始まる緩和ケアなどはもってのほかになってしまう。死に方のひとつ、尊厳死を望む国民が少なからずいる時代に、なんと時代錯誤な見出しだろうか。
3月8日の毎日新聞は「本人に判断迫るのは酷」「透析中止問題で患者団体」と、東京腎臓病協議会の事務局長の談話を写真付きで載せ、中止の提示を問題視する。本文では「医師のさじ加減で意思決定を迫るのは、道徳的にも問題ではないか」という声を伝えた。
同日の東京新聞も同じ事務局長の話を掲載。「医師が患者に生きるか死ぬかを選ばせること自体が明らかに間違っている」「医師は患者を治すのが仕事。最後まで助けてあげようとは思わなかったのか」という内容である。
当事者の患者の言葉で、紙面造りの根拠を提示しているかのようだ。
だが、患者に対して医師が話すべきことの中に、治療の限界を含めてはならないのだろうか、と疑問が湧く。毎日新聞は7日の紙面の解説記事で「医療の枠組みの中で『死の選択』が行われていたことは驚きだ。医療機関は治療する場所なのだ」と記す。
果たして、一方的な治療だけが医療の役割だろうか。これまでの医療は「死」に向かい合わず、「敗北」としかとらえてこなかった。だが今や本人のQOLを尊重し、本人の意思決定が最優先される時代になりつつある。
人生の幕引きを本人と周りで考える 「人生会議」の重要性
高齢社会の到来で、死や終末期をめぐる議論がこの10年ほどで大きく進展している。2007年に厚労省が打ち出した「終末期医療の決定プロセスに関するガイドライン」は昨年3月、大幅に書き換えられて、そのタイトルも「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」となった。
医療だけでなく、ケアの現場スタッフも含めて、本人などとよく話し合うべきだとされ、ケアが加わった。このガイドラインには、海外で「普及しつつあるACPの概念を盛り込み」(ガイドラインの解説編)とある。ACPとは「これからの治療・ケアに関する話し合い(アドバンス・ケア・プランニング)」のことだ。11月30日にACPの愛称として「人生会議」が命名される。
誰もが迎える人生の幕引きに際して、医療だけに委ねるのではなく、本人を中心に生活を共にする人たちと一緒に考えましょう、というものだ。昨年の診療報酬改定で、終末期の態勢を取ることが要件として組み込まれたこともあり、今や各地で開かれる医療職の研修会などでは、テーマがほぼACP一色になるほど関心を呼んでいる。
そこで重要なのは、医療やケアの専門職から提案される様々な対応を本人がじっくり考えて、本人が選択すべきだが、本人の心は揺れ動くことを十分斟酌すべきとうたわれていること。本人の意思を尊重するためには、話し合いは早くから繰り返し行うことだという。その通りだろう。
今回の福生病院問題でも、このACPの在り方こそが問われるべきことだろう。医師が提示した透析中止は、透析の継続、あるいは継続方法と並ぶ「人生会議」の際の1つの選択肢である。それは当然の提案だ。むしろ、その選択肢を提示しないのであれば、それは専門職としての責任問題だろう。根幹は、患者本人の思いがどのように人生会議の場で伝わっていたのか、だ。
話し合いの中で、家族との意識の共有を目指す努力も欠かせない。だが今回、毎日新聞は患者の夫に取材し、3月7日の紙面で「治療を再開しなかった外科医に対する不信感は消えない」と本文で夫の心情を記す。夫の言葉では「医者は人の命を救う存在だ。『治療が嫌だ』と本人が言っても、本当にそうなのか何回も確認すべきだと思う」とある。家族と病院との意思疎通が十分ではなかったようだ。
今回の患者を含め同病院でこれまで死亡した24人の透析患者について、説明がきちんと記録されていなかったとして、立ち入り検査後の東京都は4月9日に同病院に改善指導した。
「患者が透析拒否」と病院が会見 メディアの報道内容に矛盾
第2の問題は3月28日に起きた。病院の担当医と院長が初めて共同記者会見に臨み「透析中止は患者の意思です。病院から透析中止の選択肢を示していない」と話し、それまでのメディアの報道を否定してしまったのである。
その深夜に時事通信と日本テレビが報じ、翌29日の朝刊で朝日新聞、東京新聞、産経新聞が伝えた。
では、なぜ患者は透析をやめることにしたのか。29日の朝日新聞によると、「外科医は首周辺に管を通す透析治療を提案したが、女性は『シャントがだめだったら透析をやめようと思っていた』と話し拒否した」という。あくまで患者本人から拒否の言葉が出たというのだ。続けて「外科医は透析をやめると2週間ぐらいで死に至ると説明、女性は『よくわかっている』と答えたという」とある。
さらに、患者とその夫を交えての話し合いの後、「透析からの離脱証明書に女性に署名してもらった」という経緯だと記してある。東京新聞、産経新聞もほぼ同様な記述だ。
共同会見だから同じ内容になるが、日本テレビでは以下のように伝えた。
「透析を継続するため、鎖骨付近からカテーテルを入れる新たな治療方法の提案を行ったものの、女性患者は『透析はやらない』などとして、同意が得られなかったと説明した。女性患者は、透析治療を中止する文書にも署名したという」
注目したいのは、会見の際の外科医の言葉だ。
「外科医は、『透析が可能な状況でこちらから中止を提示することはない』と説明。女性は中止の意志が固く『衝撃を受けた』と振り返った」
これは産経新聞の記事である。朝日新聞でも、外科医は「拒否したために透析ができなくなった特異なケース」と話しているとしている。
両紙から、患者の相当に強い意志がうかがえる。
読者は、これを読んで疑問に思わずにいられないだろう。3月7日、8日の時点では「病院が透析中止の選択肢を示した」と報じていたはず。違うではないか。どちらが事実なのか。
その内情を明かしたのは朝日新聞だけだった。同紙は「東京都は当初、外科医が透析をやめる選択肢を示した、と説明している」と言い訳を記した。つまり、東京都からの取材で、「透析中止を提示」と断定したことが分かる。当事者の医師の確認が取れていなかったのである。
一方、朝日新聞を除いたほかのメディアは、過去の記事との矛盾を説明しないままだ。その日の共同会見を病院から拒否された毎日新聞だが、翌日に「担当医『女性が手術拒否』」との見出しで報じた。患者が透析を断った経緯だけを記し、「病院は透析中止の選択肢を提示していない」という肝心な点には触れていない。
患者が臨終に至るまでが 「医師」と「夫」で食い違う
次に、第3の問題点は患者が亡くなった昨年8月16日の動きだ。
3月29日の朝日新聞は「未明に、女性は呼吸の苦しさや体の痛みを訴え、看護師に『こんなに苦しいなら透析した方がいい。撤回する』と発言したことが記録に残っている。しかし、16日昼前に女性の症状が落ち着き、外科医が呼吸の苦しさや体の痛みが軽減されればよいか、それとも透析の再開を望むかと尋ねると、『苦しさがとれればいい』と答えたという。外科医は女性の息子2人にも説明して理解を得たうえで鎮静剤を増やし、女性は同夕に亡くなった」と記す。
この記述は、3月7日の毎日新聞の記事とほとんど変わらない。同じ外科医への取材だからであろう。ところが、臨終の場面の内容は大きく違っている。
3月29日の東京新聞は、共同会見した外科医の話として「鎮静剤を増し、別の病気で入院していた夫と息子2人が見守る中、落ち着いた状態で同日午後5時11分に亡くなったとしている」と書く。これは上記の朝日新聞と同じだ。
一方、3月7日の毎日新聞では、患者の夫の話として「(昨年8月)16日、麻酔からさめると女性は既に冷たくなっていた」とあり、妻を見守る状態ではなかったと記す。事実は1つ、どちらかが間違えているのだろう。
人工透析だけではない対処法 「腎移植」という選択肢も
ここまで、新聞を中心に経緯を追ったが、腎臓病、腎不全への医療の対応法にも課題がありそうだ。これが第4の課題である。
日本の透析患者は、日本透析学会によると2017年末で33万4505人。平均年齢は68歳。1990年には10万3296人だったから年々増えている。
血液にたまる老廃物や余分な水分を除去するために受ける血液透析は、1回に4~5時間ベッドにじっと横たわりながら受ける。週3回必要で、やめてしまうと苦しみ、数週間内に亡くなるという。このため一生受け続けなければならない。
福生病院の女性患者は別の医療機関で長く透析を続けてきた。昨年8月9日の来院時に透析の「離脱証明書」に署名したが、16日の未明に呼吸が苦しくなり体の痛みを訴えたという。
血液透析の費用は月約40万円と高額だが、高額療養費制度があるため、患者の負担は月1万円強といわれる。医療機関にとって人工透析患者は、長期にわたる安定した「収入源」ともなっている。1人年間約500万円の医療費は、国全体では約1兆6000万円に及ぶ。
人口透析には、患者自身の腹膜を使って行う腹膜透析もある。透析液を自分で入れ替えられるので自宅でできる。だが、長期間は難しく、実行者は1万人に達しない。
実はもう1つの対応法がある。透析ではなく、腎臓そのものを取り換えてしまう根本的な治療法である。腎移植だ。
移植された腎臓による拒否反応が問題視された時代があった。だが、現在は移植された腎臓がきちんと機能する確率は極めて高い。移植手術は医療保険の対象なので自己負担はあまりない。
人工透析よりはるかに優れた理想的な治療法だが、残念ながら2017年には年間1742件しか実施されておらず、極めて少ない。欧米では、移植と人工透析の比率は大して変わらない。腎移植を待っている間だけ人工透析を、という考え方も強い。
ところが日本では、腎臓の提供者が少ないため、腎移植という発想がはじめからほとんどない。腎移植の9割近くは家族などからの生体腎。死後の臓器を活用する献腎は極めて少ない。そもそも臓器を提供する文化が日本では定着していないからだ。
健康保険証や運転免許証、それにマイナンバーカードには「臓器提供の意思表示」の欄があり、提供したい臓器を選ぶことができる。心臓や肺などと並んで腎臓も表記されている。2010年の臓器移植法改正で表記が始まった。臓器移植への関心を高めるにはいい手法だろう。「遺体にメスを入れたくない」ではなく、世のため人のための心意気の広がりに期待したい。
「治す」だけではなく人々の生活を「支える」医療の重要性
そして最後、第5の課題は、医療の果たす役割である。
高齢者の自宅や施設での看取りが増えてきている。2013年8月に社会保障制度改革国民会議(座長清家敦・慶應義塾大学塾長)がまとめた報告書で、新しい医療概念が打ち出された。
「QOL(クオリティ・オブ・ライフ)の維持・向上を目指す医療」「治し・支える医療」「人間の尊厳ある死を視野に入れたQOD(クオリティ・オブ・デス)を高める医療」とうたわれた。
医療は「治す」だけでなく、人々の日々の生活を「支える」ことが重要と訴え、誰もが迎える死にもQOLの概念を取り入れ、QODを高める医療を新たに提言した。QODが、政府関連の正式な文書に登場したのは初めて、画期的なことだった。
死は生活の延長線上にある。本人のQOL第一という発想から死を視野に入れた考え方である。森鴎外の孫で、埼玉県新座市で訪問診療を続けている小堀鴎一郎医師は、「日本は『生かす医療』はトップクラスであるが、『死なせる医療』は大きく立ち遅れている」(著書『死を生きた人々』から)と喝破している。「死なせる医療」とは名言だろう。
苦痛を免れない延命治療から、自然の摂理に委ねる自然死、尊厳死への転換が進んでいる。人口動態統計による死亡原因で、この数年「老衰死」の急増がその転換ぶりをよく示している。
「治療」だけが医療の役割という考え方は、過去のオールド・カルチャーになりつつある。福生病院の医師たちも、こうした社会の流れに合わせた対応を取ったと理解したい。
(福祉ジャーナリスト 浅川澄一)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@

- << そもそも医師法21条とは
- HOME
- 自動車事故とてんかん >>
このたびURLを下記に変更しました。
お気に入り等に登録されている方は、新URLへの変更をお願いします。
新URL http://blog.drnagao.com
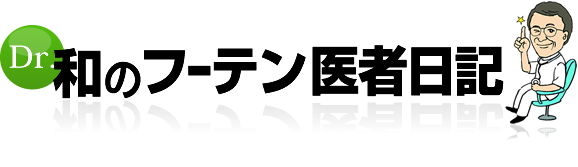


 応援クリックお願い致します!
応援クリックお願い致します!




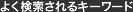




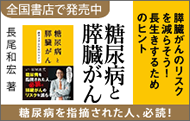







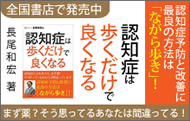

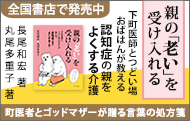
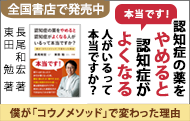


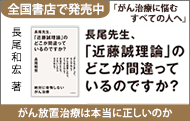
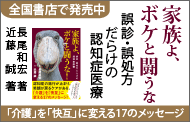
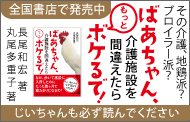

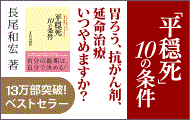
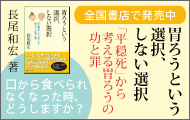

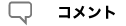


この記事へのコメント
「剃刀を抜いた兄の立場で考えてみるべきだ」(福生病院院長)。
ここに、『藪の中』の核心を解くカギがありそうだ。
8年前、「喜助が行ったのは積極的安楽死だったのか」と、問うた八戸在宅医(山名保則)がいた。
鴎外は『高瀬舟縁起』の中で、「死にかかっていて死なれずに苦しんでいる人を、死なせてやる」というテーマを喜助に託したという。「医療の中での安楽死、それも積極的な安楽死の前提として」。
これを、山名は医学的・解剖学的に検証を試みた。
・「息をいたすたびに、傷口がひゅうひゅうという音がいたす」という表現から、喜助の弟が自分の右手で気管を切ったのは間違いない。
・弟は総頸動脈を切ったのではなく、内頸静脈の外の皮膚・皮下組織を切ったものと思われる。
・喜助が「剃刀を抜いた」後に、切開創を直接圧迫止血していたら直接的な失血死は免れたかもしれない。
・喜助は「刀をまっすぐ抜こう」と思っており、とどめを刺そうという意思はなかったように思われる。
・とすると、少なくとも医学的・解剖学的には、鴎外が意図した積極的安楽死を構成する要件を満たさないことになる。
しかし、このような「深読み」は世間ではなされておらず、喜助は積極的安楽死、自死ほう助を行った善人とみなされている。
1年前、生まれて初めて救急救命の「医療現場」を経験したものとして、また「急性期脳梗塞患者の予後予測研究」に協力させていただいている「ひとり」として、『藪の中』は、気にかかる。
医療側と患者側、「終末期」と「涅槃期」。それぞれの見える風景は一様ではない。「通りすがり」と「1回限りのいのち」。
Posted by 鍵山いさお at 2019年04月25日 03:19 | 返信
コメントする
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL: