このたびURLを下記に変更しました。
お気に入り等に登録されている方は、新URLへの変更をお願いします。
新URL http://blog.drnagao.com

令和時代の「死」
2019年05月19日(日)
私は2つの方向性があると感じている。ひとつは、再生医療やAI医療による
「不死神話」でありもうひとつは「考えなくてもいい」という楽観論である。
一昨日、在宅医療のリーダーと国のリーダー70名による
「死」に関するグループワークは、結構、衝撃的だった。
みな私と同じような感覚を持っているのかと思っていたが
まったく違う意見も結構あり、いまもその余韻の中にいる。
「死はそんなに考えなくてもいい」
「考えないことはそんなに悪いのか」
「考えない、という権利もある」
「死ぬまで治療するのがなぜいけないのか」
「人間は死をそんなに考えないものだ」・・・
そう、私は考えすぎなのかもしれない。
でも多くの溺れ死にを視るのはとても辛い。
死を考えないで生きることはできない。
「考えるな!」と言われても考えるのが「死」。
グループワークに参加していたある尊敬する
医師はFBにこう書きこんだ。(一部を転載)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
死についてのグループワークの続き
―― 国民に対する「死に逝くことの啓発」が求められているか?
哲学的な意味で「死を自覚する」ことは大切かもしれませんが、あまり早く啓発する必要もないのではと思います。
たしかに、病院で仕事をしていると、「気づくのが遅すぎるんじゃないか」と感じることはあります。たとえば、90代で寝たきり、だんだん食べられなくなってきた・・・。自然な死へのプロセスにあるはずなのに、家族から「オバアが死ぬなんて考えたこともなかった」と驚かれたりします。
今度は、そのことに私たち医療者が驚かされるわけです。もっと早く、死を想定しておくべきじゃないのか? この段階になってもなお、どうして生き続けられると思うのか? 生き続けさせるのが当たり前だと思えるのか? 多くの疑問が沸き上がります。
ただし、これらは医療側からの視点にすぎません。私たちが「もっと早く、死を自覚しておいてほしい」と感じているとしても、その死に密接に関係する立場だからこその実感なんですね。つまり、このことについて、私たちは客観性を欠いているんです。
国民への「啓発」として、医療者は積極的に発言すべきだと思います。ただ、医療だけでなく、心理学、社会学、あるいは哲学など多様な側面からの分析を統合していく作業が求められているのではないでしょうか?
―― どのように「死に逝くことの啓発」を進めるべきか?
啓発の対象や時期については、3つのステージがあると思います。
まず、一般論として「死へのプロセスを知る」という知識の獲得ですね。これは「3人称の死」と言えるでしょう。次に、親や隣人など「身近な人の死を受容する」という体験的な理解があります。これは「2人称の死」と言えます。最後に「自らが死に逝く存在である」という「1人称の死」の自覚へと至ります。
急いで「1人称の死」を自覚させる必要などありません。そもそも、他者からの啓発ごときでは無理なんです。むしろ、差し迫った必要もないのに、理解させた気にするような自己啓発があるとすれば、その拙速さこそが問題だと私は思います。これは、アドバンス・ケア・プランニング(ACP)あるいは「人生会議」の"先走り"にも見られる問題ですね。
ちなみに、悟った気になることを仏教では「慢心」あるいは「増上慢」と言い、それだけで煩悩のひとつを背負ったことになります。そして、のちのち苦しみの原因になると説いています。人生会議における「慢心」についても、私たちは十分に注意する必要があるでしょう。
というわけで・・・、広く国民への啓発という施策とするのであれば、あえて「1人称の死」へは踏み込まぬよう注意しつつ、「(自分のことは置いておいて)どのような死に方があるのか」という「3人称の死」を伝えていくのが良いのではないでしょうか?
一番よい媒体はテレビ番組だと思います。沖縄県でも、毎年、県民向けに看取りや意思決定をテーマにした番組を制作して、地上波で放映したり、市民向けの講演会で紹介したりしてきました。
―― 身近な死について準備していくことも必要ではないか?
身近な人の死・・・ つまり、親や隣人など「2人称の死」を体験することは、単に死への準備教育というだけでなく、社会の役割を深く考えるような機会にもなっているでしょう。暮らしのなかに「2人称の死」を取り戻していくことは、私たち医療者が考えているより、もっと重要な社会的意味があるのかもしれません。
とはいえ、高齢化した現代社会で「2人称の死」を取り戻していくには、それを家庭や家族まかせにしていても実現困難でしょう。都会であれば、ボランティアが看取りを支援するような地域づくりが必要かもしれません。地方であれば、地域にある繋がりを立て直すことでよいかもしれません。いずれにせよ、地域ぐるみで「2人称の死」を経験することができれば、弱者にやさしい地域づくりへの切っ掛けとなるかもしれません。
この「2人称の死」においては、暮らしの支援者である介護職がカギとなります。彼らの理解と協力、意志なくして、高齢世帯や介護施設における看取りは実現しません。病院におけるテクニカルな「看取り」と違って、暮らしのなかでの「看取り」支援とは、かなり高度なものでしょうし、支援者自身も深く傷つくリスクすらあると思います。
だからこそ、在宅医療や訪問看護との連携が求められます。ただし、私たち医療者が生活に踏み込みすぎると、ふたたび専門性による囲い込みになりかねなません。医療以外の言葉で「2人称の死」を語れるようにするためにも、多職種連携のなかに現象学的なアプローチを取り込むこと(それを理解すること)が重要だろうと私は思います。
たとえば、ある高齢者が「食べられない」という経験をしているとします。医師は「嚥下機能の低下。その鑑別は・・・」と記述し、ケアマネは「専門的な食事介助ニーズが・・・」と把握し、家族は「いよいよオバアが弱ってきた」と受け止め、本人は「べつに私は何ともないよ」と考えている。
そのどれもが誤りではないし、どれかが優れているわけでもない。ただ、それぞれに表出する物語を互いに尊重しながら、死のプロセスを進めていくこと・・・、これこそが「多職種連携による看取りの在り方」ではないかと思います。
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
またこんな記事も出ている。
令和時代、人は「死」を意識しないようになる →こちら
東洋経済オンライン 5/19(日) 6:20配信
ロケット級の進歩を遂げつつある医療。iPS細胞を利用して臓器をつくり出す再生医療や、AI医師の登場だけではなく、診断、手術、創薬、医療機器、救命救急、予防……。このまま医学が完成していけば、死の脅威をもたらす病気はほとんどすべて姿を消し、病気では人が死なない「不死時代」が到来すると、医学博士の奥真也氏は著書『Die革命――医療完成時代の生き方』で述べている。いずれ訪れる「不死時代」とはどのような未来なのだろうか。
■がんを完封する時代がやってくる
平穏にすごしていた日々に、突然割って入るがん患者としての生活。幸せの絶頂の裏に忍び寄る糖尿病の影……。病気によって人生の予定が狂わされた経験を持つ方はたくさんいらっしゃるでしょう。でも、その状況は大きく変わろうとしています。
1981年に世界で初めて発見されたといわれるエイズは、当初は手の施しようがなく、絶望的な病気と思われていました。しかし、2000年を過ぎたあたりからHIVウイルスの働きを阻害するさまざまな薬が実用化されはじめ、現在では生命を奪う病気ではなくなっています。
エイズの薬のように派手に報道をにぎわせるものもあれば、目立たない進歩を遂げる薬もまた多くあるため、あまり実感がないかもしれませんが、成果を上げている例としては、タミフル、イナビルなど抗ウイルス薬によるインフルエンザに対する強力な治療効果などもそうでしょう。1回飲むだけでウイルスの増殖を抑えられるゾフルーザという進化した薬も世に出ました。
人類にとって最大の病魔の1つと言われているがんも例外ではありません。胃がんや大腸がんは、不治の病のリストから消えつつあります。乳がんや肺がんもそうです。がんの克服は確実に進んでいます。
2018年には、光免疫療法と呼ばれるがんの標的療法と、近赤外線による光化学反応を組み合わせた新しいがん治療の治験が日本でも開始されています。また、がん細胞に感染し、溶解させてしまうウイルスを使った薬は、数社が治験の先陣争いをしており、ほどなく世に出てきます。まさに今、がん治療の地図は大きく塗り替えられようとしているのです。
人類と病気との闘いについて話してきましたが、そもそも、いったいどうなれば、「病気に勝った」ことになるのでしょうか。ほとんどの方は風邪やインフルエンザなどの「治る病気」を思い浮かべ、病気とは治療をすれば治るものだ、とイメージしていると思います。
しかし残念ながら、病気の9割は治りません。医療の立場から言えば、必ずしも病気は治らなくてもかまわないのです。「たいていの病気は治癒しない」し、「治癒する必要はない」というのが医師の感覚です。
ほぼすべてのがん患者は、おそらく風邪などと同じように「がんが完治する」ことを期待していると思いますが、多くのがんは、「治療」はできても「完治」はしません。医者の立場からすると、「今よりも悪くならないようにはできるが、完治するとは言い切れない」と捉えています。
つまり、病気の9割は、医者にとってつねに「病気」というステータスにあります。完全に治癒しなくても日々の生活に支障がなければよい。医療はそこを目指しているのです。
■誰もが「多病息災」で生きていく
ある病気と一生つきあうことになったとしても、その病気が牙をむき、身体に不具合を生じさせたり生命を脅かしたりしなければ困るわけではありません。この「ある病気とともに生きる」ことを一病息災といいます。では、一病息災は不死時代にどう発展するのかというと、その姿は、「多病息災」であると思います。
つまり、1つだけではなく、さまざまな病的な状態を持ちつつ、これらがどれも生命を脅かすことなく、生命との間に均衡を保っている状態。どの病気も、宿主である人間を殺してしまうところにまでは到達しないということです。
多病息災時代においては、つねに自らの中にいくつかの病的な状況があることを理解しなくてはいけません。それこそが人間の普通の状態なのだから、何も気に「病む」こともないのです。ただただ自然にそれを受容していればよく、多病がゆえに死ぬことなどないのです。
さて、「不死時代」到来の大きな立役者は、やはりテクノロジーです。テクノロジーによる医療の進化が近年はより本格化しています。
象徴的なのは、ロボットの導入です。例えば、1990年代にアメリカで開発された手術支援ロボットの「ダヴィンチ(da Vinci)」。現時点ではまだAI(人工知能)が搭載されているわけではありませんから、ロボットといっても人間が操作する機械にすぎません。でも、ここにはイノベーションともいうべき、かつてはなかった進化が起こっています。
たとえ話ですが、身体の硬い人が自分の肩甲骨を手で触るのは簡単なことではありません。同じようなことが外科手術にもあって、膵臓の裏側にある血管の縫合などは、大きく開腹したうえでほかの臓器の間をかき分け、そこまで手指をくぐらせて作業しなくてはならず、人間には困難な手術です。
でもロボットならば、人間の腕や手では不可能な角度からアクセスすることができ、うまく施術できます。切除の精度に関してもそうです。1ミリ幅の切除は、人間なら「神業」ですが、ロボットを使えばさらにその10分の1の幅でも安定して高い精度で切除できます。
よくニュースなどでは「ロボットが人間の代わりを務める」という表現が使われますが、少なくとも医療の場合は単純な代役ではありません。人間には到底できなかった水準のことをやってくれるのが医療におけるロボットなのです。
■AI診断が人間を凌駕する
私たちはこれから、医療イノベーションの収穫期に入っていきます。ビッグデータの活用で創薬のプロセスが大きく変わったり、外科手術にロボットが導入されたりと、治療の方法論は大きな前進を遂げつつあります。
しかし、いくら治療の方法論が完成されても、そもそもの「見立て」が違っていたら克服できるものもできなくなります。医療の完成ということを考えると、あらゆる医療行為の出発点ともいえる「診断」において誤診をなくすことが最大の課題なのは言うまでもありません。
それにはどうすればいいのか。解決策として、最も有力視されているのがAIの導入です。2000年代に突入してコンピューターの計算性能がぐっと上がってきたことに加え、人間の脳神経回路をモデルにした多層構造アルゴリズムを用いて、着目すべき特徴や組み合わせをAI自ら考えて決定する「ディープラーニング(深層学習)」の技術が長足の進歩を遂げたことが重なって、AIが人間を凌駕する時代がやってきてしまいました。
それは医療AIについても例外ではありません。医師の「診察」「問診」はAIが十分に代替できる、ということです。というのも、AIは人間のように思い込みで病気を見逃すことはありません。疲労による判断ミスもない。むしろ、安定的に正確な診断ができます。つまり誤診率をかぎりなくゼロに近づけることができるのです。
奥 真也 :医学博士
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
20台の人気プロゴルファーが1年間のがん闘病のすえに、今週亡くなられた。
50代のプロゴルファー並みのアマチュアゴルファーの医師が練習場で突然死。
そんな知らせを聞くと、「なんのためにあれほど一生懸命に練習したのか」
なんて愚問が、いまさらながらではあるが、頭の中を駆け巡り、落ち込む。
名越康文医師の著書「どうせ死ぬのになぜ生きるのか」→こちら
を読み直してみるも、仏教では死の疑問は解決しない。
「死を考えること」は悪いとは思わない。
考えてもらうことも、悪いとは思わない。
医者は全員、深く考えるべきである、と思う。
しかし「そんなの関係ない」という医者もいる。
考えても答えが無い問いを考える意味とは何なのか?
池田清彦先生も養老毅先生も
「死を考えても意味ない」という。
たしかにそうかもしれない。
人生に意味などない。
意味があると考えるから、悩み、死にたい人が出る。
ただただ生きて、勝手に死ぬだけが人生。
そう思って生きるのが一番幸せなのかも。

このたびURLを下記に変更しました。
お気に入り等に登録されている方は、新URLへの変更をお願いします。
新URL http://blog.drnagao.com
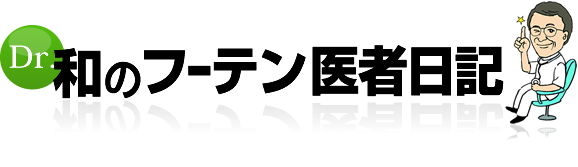


 応援クリックお願い致します!
応援クリックお願い致します!




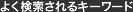




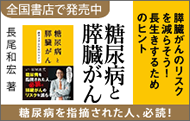







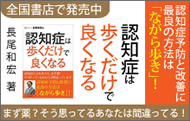

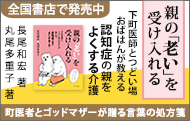
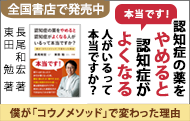


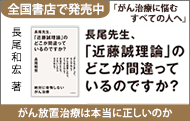
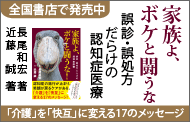
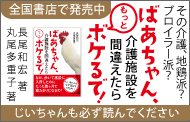

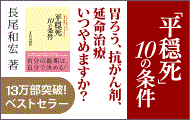
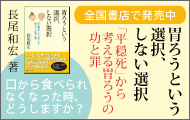

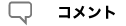


この記事へのコメント
「目の前の誰かの死」と引き換えに「おのれの生」を得た時代、の端くれとしてあれこれ考える。
「死の受容」にいたるプロセスを解明した学者も、「5段階」どおり逝かなかったらしい。
ながねん地域で親しまれてきた在宅医の方も、「こんなはずじゃなかった」と述懐しておられた。
「死ぬときは『有難う』と言って死のう」と、「いい往生際」を説くホスピス医もいるが、
「往生際」は、ひとそれぞれ。「ひとりひとりちがって、みんないい」。
「天国」があるのか、「極楽」があるのか。共通する「地獄」があるのか。何も無いのか。
実父母、養父母、幼い妹には、何もしてあげられなかった。
人それぞれ、生きてきたように死ぬのだろうか。
「死に方はかくあるべし」と、強いることも強いられることも、ない。
「納得できる人生だった」、いや「最後よければすべてよし」。
「残された家族のグリーフ考えよう。」 いや「無理して恰好つけることない。」
百家争鳴、百花繚乱で、いい。
「終活」「ACP」「人生会議」「ガイドライン」・・・。
「平成時代の死」「令和時代の死」?
「明治時代」の天皇側室5人。待望の男子が大正天皇。「妻・妾」が制度化されていた旧民法。
「令和の時代」でも「y遺伝子」が尊ばれ、怪しげな「神代時代の儀式」が公的行事、国事行為として復活。
毎日新聞はじめすべてのメディアが「万世一系」「神聖天皇」復興を、
「平成生まれ」の子どもたちに、意図的に「刷り込む」。
「令和の時代」の幕開けに、1946年ヒロヒト「人間天皇宣言」ご破算!
Posted by 鍵山いさお at 2019年05月19日 08:11 | 返信
やっぱり 生き物の中で 一番 めんどくさい生き物は 人間だぁ〜
金八先生じゃないど…
人っていう字はね…1と1が支えあってるんだよ
人は 人の中(間)でしか生きられないんだよね
…みたいな感じですね
それでも…人間に生まれて
不思議な文化や生活をいただき 苦しいこと 怒れてくることも いっぱいあるけど
楽しいこと うれしいこともいっぱいあります
今日一日 愉快に暮らせれば 明日も愉快な一日がやってきますよね
Posted by 宮ちゃん at 2019年05月20日 11:22 | 返信
他人から聞いた話ですけど、照見皇太后は、子供ができなかったので、側室が多かったとのことです。
昭和天皇も、娘さんばかり産まれたので、周囲が「側室をお持ちになっては」と勧めたが、「長宮で良い」と仰った。その後上皇陛下昭仁氏が生まれたとのことです。
昭和天皇は、大正天皇が心身ともに弱かったことを口実に、軍人の家庭に預けられた。だから生まれながらにして軍人のような、お公家のような存在であったのでしょう。
ラストエンペラーの愛新覚羅溥儀さんの生涯を見ていると、共通点があるような無いような。
傀儡の満州国皇帝になっても、日本軍や甘粕大佐に馬鹿にされ続けて、日本軍が敗走するとソ連に捕縛され、中国共産党に引き渡され、収容所で思想教育されて、収容所長に許されて、出所後、北京の植物園の園丁として平和に暮らしたとか。「わが半生」と言う愛新覚羅溥儀さんの自叙伝が出版されています。その当時の愛新覚羅溥儀さんを許して植物園の園丁にした収容所長は、文化革命で「反動派」として糾弾されたとラストエンペラーでは描かれていました。
昭和天皇は、胸中どうであったのか分かりませんが、昭和天皇の身代わりに平和路線の近衛元首相が自害なさったことは、「良かった。助かった」とお思いなのか「悪い事をした」と思っていらっしゃったのか。太平洋戦争の深淵なブラックボックスだと思います。
明治維新以来、皇室は満州国皇帝と同じ傀儡ではないかと思います。皇女和宮のお兄さんの○○天皇だったでしょうか?急にお隠れになって、明治天皇は未だお若かったので、長州勢力が、神輿に担ぐには容易かったのではと疑っています。
Posted by にゃんにゃん at 2019年05月22日 02:18 | 返信
コメントする
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL: