このたびURLを下記に変更しました。
お気に入り等に登録されている方は、新URLへの変更をお願いします。
新URL http://blog.drnagao.com

10/10公開「ヒポクラテスの盲点」の大西監督が語る制作秘話
2025年10月09日(木)
明日10/10に映画「ヒポクラテスの盲点」が公開される。
その大西監督が制作秘話を語っているのでご紹介したい。
この映画で日本の政治と未来が大きく変わって欲しい。
以下、有志医師の会のメルマガから転載させて頂く。
@@@@@@@@@@@@@
10月10日(金)に公開予定の現在、新型コロナワクチンに関するテーマを扱った作品として、コロナ禍の光と闇を描いた異色のドキュメンタリー映画『WHO?』が公開中です。 https://my159p.com/l/m/j9f5NPBK3hgSpi
そしてこのたび、10月10日(金)に公開を迎える映画『ヒポクラテスの盲点』には、全国有志医師の会の複数の医師が出演しております。そこで本作の監督・大西隼氏より映画制作への思いなどをご寄稿いただきましたので、メルマガ読者の皆様にお届けいたします。 新型コロナワクチン それは、国が推奨した"救世主"のはずだった。 あのとき「喧伝」されたことは本当に正しかったのか? 「喧伝」とは、世の中に広く知らせるために盛んに言いふらすことを意味します。 新型コロナワクチンは、まさに"唯一の解決策"として過剰なまでに「喧伝」された存在だったのではないでしょうか。
==========
.映画『ヒポクラテスの盲点』―大西隼監督によるご寄稿
まずはじめに、この映画にご出演くださった先生方、患者さん、ご遺族の方々の並々ならぬ意志と勇気に、心より敬意と感謝を申し述べさせていただきます。
◆起点
2023年の4月頃、平日の昼間にソファに寝そべりながら、それまであまり見ていなかったSNSをぼんやりスマホで眺めていました。偶然、同年2月の福島雅典医師の記者会見映像(サンテレビ報道)を見た時の衝撃は、今でもありありと覚えています。「科学技術立国としての科学と医学が、深刻に問われている。データサイエンスの時代だ、データが生命線だと言いながら全然それをきちっとやってくれていない」。福島医師の迫力に圧倒されました。ここまで憤りの感情を露わにし、かつ科学的に説得力のある論述をそれまで見たことはなかった気がします。
そして何より、コロナワクチンによる後遺症被害の規模が、想像をしていなかったほど甚大なものである可能性に触れ、慄然としました。その日からおよそ半年ほど熟考を重ね、ワクチン問題研究会の問い合わせフォームに、取材依頼のメールを送ったのがこの映画のはじまりです。
◆私のバックグラウンド 私は、所属する映像制作会社(テレビマンユニオン)において、職域接種の機会を社内に紹介しました。希望者を集計する役割も担い、自らも3回まで接種しました。当時を振り返ると、ワクチンが取り沙汰された頃、ファイザーの「95%発症予防」論文に目を通してみたり、一通りインターネット(主にgoogle検索)で調べたりはしましたが、有効性と安全性の科学的根拠を理解していたとは言えるほど、十分に立ち止まって、考え、調べることはできていませんでした。今となって恐ろしいのは、「不十分の感覚」がありながら、状況に流されてしまったことです。
けれども当時、私はテレビマンユニオンの取締役の1人でもありました。コロナ禍の社会状況の中、国内外の番組制作・ロケ・ドラマ撮影にことごとくブレーキがかかっていて、不自由な制作体制が1年ほど続いていたことに強い焦燥感をもっていました。経営上の大きな障害がいつまで続くのだ?という苛立ちもあったと思います。たまたまプライベートでの大きな変化も重なり、正直なところ世の中の状況を冷静に分析する胆力は持ち合わせていませんでした。私の悔悟、告白です。
コロナワクチン問題の取材に踏み出した背景のもう1つは、大学院まで生命科学分野の研究をしていたことにあります。学部時代は、東京農工大学(東京・府中)の農学部で、動植物・微生物・生態学などについて学びながらも、もっとヒトを知りたい、人間を知るならば意識や思考、認知科学や脳科学が1つの道なのではないかと大学3年の頃から思い始めていました。母の叔母が認知症を患ったことがきっかけで精神疾患への興味が深まり、東京大学大学院の石浦章一研究室の門を叩きました。
修士では「アルツハイマー病発症に関わるプロテアーゼBACE1の機能解析」を研究。博士論文のテーマは「RNA結合タンパク質MBNL1の相互作用分子の生化学的・生理学的解析」でした。MBNL1は、DM(筋強直性ジストロフィー)という疾患の発症に関わる分子です。
◆研究から映像へ
RNAというキーワードを道標として、せっかくなので少し詳しく説明します。MBNL1(musleblind like-1)タンパクは、DNAからタンパク質ができる過程での「RNAスプライシング」という段階を担うファクターの1つです。MBNL1はRNAのCUG配列に結合することから、CUGのリピート(反復)配列が存在するところでは、そこにトラップされて本来のスプライシング機能を果たせなくなることがあります。
結果、RNAのスプライシング異常によって発症するのがDM(筋強直性ジストロフィー)です。 私の研究では「MBNL1がどのようなタンパク質と結合・相互作用し、スプライシング機能を調整しているのか」「細胞内でリピートRNAがどのような分布を示すのか」などを、毎日のように実験・研究していました。
所属していた研究科に一台しかなかった最新鋭の質量分析計については、他のラボの学生や研究員に指導するようになったほど熟達できたことは懐かしい思い出ですし、博士3年の時にはイタリア・ミラノでの国際DM学会で英語で発表させてもらったことも貴重な経験でした。でもその頃にはすでに、研究の道から映像の道へ転身することが決まっていました。
「なぜ研究から映像へ?」とはこれまで幾度となく聞かれてきた質問です。確かにレアなケースなのでしょうが、自分にとっては自然な選択でした。一言で申せば「科学から人や世界を知るのではなく、映像(いわば世界の似姿)を作ることを通して世界を知る道へ」という転身でした。
前述の通り、ヒト(人間)を深く知りたいと思い研究の道を進みましたが、私は研究者には向いていないと途中で気がつきました。基礎の研究では特に、限定されたある対象を極めて深く掘り下げる修行のような営みなので、並々ならぬ我慢強さや、研究の外の世界に気が散らないような特性も必要だと思います。
自分の特性を発揮する場所は別のところにありそうだと気がついたのが、私が博士課程1年だった2005年に東京大学の大学院で立ち上がった「科学技術インタープリター養成プログラム」でした。一期生として参加して副専攻として修了。科学と社会の関係について学び、刺激を受けました。
講師の1人だった立花隆(ジャーナリスト)さんに「メディアの仕事に進もうと思うのだが」と相談し、「野次馬の方が面白いよ」と背中を押されたのをよく覚えています。研究者としてはものにならないことを、周りの大人たちは見抜いていた気がします。生意気で、若気の至りを吐いた採用試験の結果、NHKと文藝春秋は書類で落ち、テレビマンユニオンだけが受け入れてくれました。
◆制作の苦労1(資金面)
ワクチン問題研究会に取材依頼をした当初の仮題は「科学の盲点 ~ワクチンをめぐる悲劇と希望~」でした。「盲点」という言葉が最後までタイトルに残ったことにはある感慨があります。当初は、研究会に対して「テレビ番組」あるいは「ドキュメンタリー映画」として形にしたいという希望を伝えていましたが、正直なところ何も確証はありませんでした。
信頼する井上カメラマンにも半ば無理を言って、24年1月のワクチン問題研究会の記者会見から撮影取材をスタート。 自腹&立替出費という形で費用が嵩んで行く中、これを形にできなかったら個人の貯金を切り崩して補填するしかない。そのぐらいの覚悟はありました。
他の仕事も減り、家計の収支は赤字続き。そんな中、社内の杉田プロデューサーが企画に関心を示してくれ、映画として完成させる道が朧げに見えてきたのが24年の4月頃。社内で正式に事業として申請、劇場の重役に企画をプレゼンできたのは24年12月でした。
◆制作の苦労2(内容面)
お金のこともさることながら、やはり一番苦労したのは、取材の進め方、ドキュメンタリーの構成、そして編集作業でした。福島医師が取材の入り口であり、主人公とさせていただくことは決めていましたが、ある時期から「ワクチンを推奨してきた立場」のもう1人の主人公を見つけなければに立っていただくことで、より複雑で射程の広いドキュメンタリーにはなりえないなりうると考えていました。
誰もが知る日本の感染対策の中枢にいらした方にも取材交渉を粘り強く行ったこともありました。その先生はメールを受け取るなりすぐに招いてくださり、こちらの意図を1時間ほどかけて説明する機会もありました。 答えを保留にされた末、数ヶ月後に再打診をしましたが、最終的には断られました。
「NHKなどでの検証番組であれば出演するが、映画か...」という反応が印象的でした。コロナワクチンの問題1つとっても、メディアが機能不全に陥っている危機的現状を全く意に介していらっしゃらないのだと痛感しました。 個人的には映像制作のプロセスにおいて最も骨が折れ、頭脳と感性を頭と感覚を総動員するプロセスが「編集」です。編集とは言い換えると、映像、言葉(音声・テロップ)、音楽を、ある時間軸の上で最適な配置を目指して試行錯誤する行為です。
今年1月頃から、撮影取材を続けながら、編集をスタートしていました。一見すると淡々とした場面の連続から、どのように「物語」のうねりを作り出すか...暗中模索の日々が続いていました。1つの突破口になったのは森内浩幸先生(長崎大)がインタビュー撮影に応じてくださったことでした。ドキュメンタリーに「転調」を加えることができたことが、編集が加速するきっかけとなりました。
コロナワクチンを推奨してきた立場の専門家が全く取材に応じてくださらなかった中で、ご出演してくださった森内先生には心からの敬意を表したいと思います。 森内先生自身、ワクチンをめぐる賛成/反対の対立の激化を深く憂慮されていました。
私もまた、科学的な意見の違いや感情的な対立を超えて、事実やデータを元に科学的な議論・検証を進めるべきということは、この問題を考える上で最も重要な出発地点だと思っております。そしてSNSを見ることから始まった取材でしたが、SNSの中で科学的な議論を深めることはベネフィットよりもリスクが大きいと感じます。その点は、SNSから距離を置く福島医師から学ばせていただいたことの1つです。
◆最後に
今もなお、ワクチンによる健康被害に苦しみ、闘っている患者の方々、ご家族、そして被害に遭われたすべての方々にとって、この映画がなんらかの「力」になることを祈念します。今このときから始まる「未来」に、同じ過ちを繰り返さないよう、われわれひとりひとりが事実を受け止め、立ち止まり、考えて、前に進んでいけるよう強く願っています。
映画『ヒポクラテスの盲点』 監督 大西 隼 おおにし・はやと
1980年東京都生まれ。東京農工大農学部を卒業後、東京大学院理学系研究科生物科学専攻・博士課程修了。08年にテレビマンユニオンに参加。ディレクター、プロデューサーとして映像制作に携わる。「欲望の資本主義2019 偽りの個人主義を越えて」「地球タクシー ソウルを走る」(共にNHKBS)でギャラクシー賞奨励賞を受賞。
・映画『ヒポクラテスの盲点』舞台挨拶のお知らせ https://my159p.com/l/m/jyerDV0Qz7aTKN
・コロナワクチンの是非を問うドキュメンタリー映画『ヒポクラテスの盲点』を、しっかり映画として観てみた https://my159p.com/l/m/EaDDXE29LCiqwu
・映画 「ヒポクラテスの盲点」大西隼監督インタビュー https://my159p.com/l/m/rnX6tJFCroEW39
・『ヒポクラテスの盲点』日本記者クラブで特別試写会レポート 大西隼監督「ワクチン後遺症は無かったことにできない」 https://my159p.com/l/m/X6eQh54RfzyYK9
『ヒポクラテスの盲点』 2025年10月10日(金)新宿ピカデリーほか全国公開 https://my159p.com/l/m/XhACNJkhQzRGLP 監督・編集:大西隼 撮影:井上裕太 音楽:畑中正人 CG:高野善政 プロデューサー:杉田浩光、杉本友昭、大西隼 出演:福島雅典(京都大学名誉教授)、藤沢明徳(ほんべつ循環器内科クリニック理事長)、児玉慎一郎(医療法人社団それいゆ会理事長)、虻江誠、上島有加里、上田潤、大脇幸志郎、宜保美紀、新田剛、森内浩幸、楊井人文
製作:「ヒポクラテスの盲点」製作委員会
制作・配給:テレビマンユニオン
助成:文化庁文化芸術振興費補助金(日本映画製作支援事業)、
独立行政法人日本芸術文化振興会 2025年/日本/ステレオ/16:9 (C)
「ヒポクラテスの盲点」製作委員会
@@@@@@@@@@@@@@@@
「ヒポクラテスの盲点}公式サイト →こちら
大西監督には、11/10の長尾チャンネルにスタジオ生出演頂きます。
皆様にはそれまでに観ておいてください。(1ケ月間もあります)
楊井弁護士は、実は来週10/13の長尾チャンネルのゲストです。
テーマは、ファクトチェックと言論統制、つまり「情プラ法」です。
この映画は大西監督でなければ成立しなかった映画でしょう。
そして、日本の医療と政治を180度変えます。
一人でも多くの人に観て欲しいです。

このたびURLを下記に変更しました。
お気に入り等に登録されている方は、新URLへの変更をお願いします。
新URL http://blog.drnagao.com
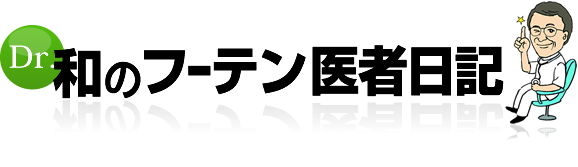


 応援クリックお願い致します!
応援クリックお願い致します!




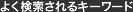
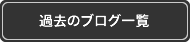
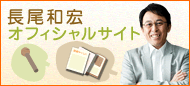
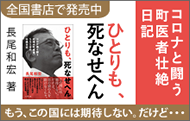
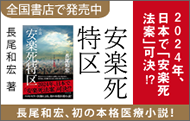
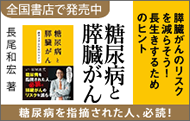
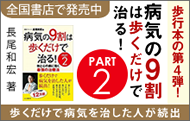
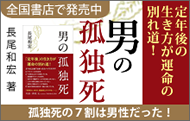
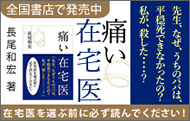

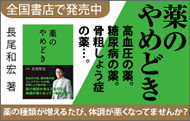
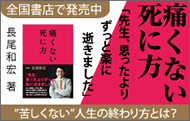
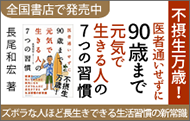
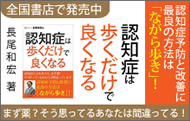
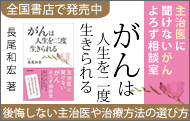
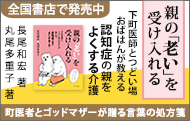
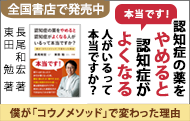


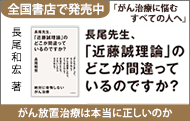
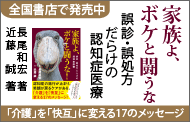
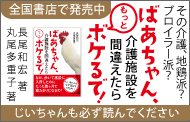

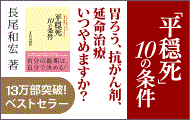
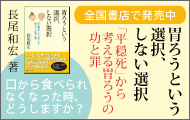


コメントする
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL: