日本呼吸器学会はこのたび、新たに「成人肺炎診療ガイドライン2017」を作成した。同学会はこれまで、成人市中肺炎(2000年初版、2005年改訂)、成人院内肺炎(2002年初版、2008年改訂)、医療・介護関連(2011年)の診療ガイドラインを分けて発表しているが、今回のガイドラインでこの3指針の内容が統合された。
この背景には何があるのか、現代の日本の肺炎診療を考える上で参考になる6つのファクトを紹介する。第57回日本呼吸器学会学術講演会(JRS57、4月21-23日、東京都)における長崎大学呼吸器内科教授の迎寛氏、大分大学理事・副学長の門田淳一氏による講演と周辺情報。全5回。
今回の肺炎診療ガイドライン統合には、高齢者の増加に伴う高齢者肺炎の実態や予後の考え方を呼吸器専門医だけでなく、非専門医や一般社会にも広く共有する狙いもあるようだ。
迎氏によると、戦前の日本人の死因は肺炎、胃腸炎、結核といった感染症がほとんどであったが、抗菌薬の開発で大半の感染症は激減。しかし、肺炎だけが再び日本人の主要な死因として復活。2011年には脳血管障害を抜いて3位に上昇した。「1960年頃から脳血管障害による高齢者の死亡数は減り続けている一方、肺炎による死亡は横ばい」と迎氏は説明する。
日本における肺炎死亡者数に占める65歳以上の高齢者の割合は96.8%。「若い人も肺炎にかかるが、ほとんど死亡しない。肺炎で亡くなるのは高齢者と言える」と迎氏。高齢者の増加に伴い年間死亡者数は増え続けており、2010年時点の全死亡数約120万人のうち、65歳以上の高齢者は約102万人を占める。死亡者のほとんどは病院で亡くなっているのが現状だ。
迎氏によると、2030年には年間死亡者数が今より40万人増える見通し。「このままでは医療資源は限界を迎え、看取り先の確保もままならなくなる」との見方を示す。
高齢者肺炎の多くは誤嚥性肺炎であることも分かってきている。全国調査では全肺炎入院患者の60%強を誤嚥性肺炎が占め、原因別では市中発症肺炎の約60%、院内発症肺炎では90%近くを占める。また、誤嚥性肺炎は50歳以降、加齢とともに急激に上昇し、70歳以降ではほとんどを占める(J Am Geriatr Soc 2008; 56: 577-579)。門田氏らによる市中肺炎患者417例と医療ケア関連肺炎(HCAP)患者220例の後ろ向き研究では、肺炎による死亡リスクは肺炎の重症度や耐性菌による治療失敗よりも、誤嚥性肺炎で最も高まることが明らかになっている(Respirology 2013; 18: 514-521)。
迎氏と門田氏は、終末期の医療に対する考え方の参考になる報告として、国立長寿医療研究センターの三浦久幸氏らによる、第50回日本老年医学会学術集会の発表演題を紹介。それによると、高齢者を対象とした終末期の事前指示書の内容に関する、終末期に胃瘻や人工呼吸器、心肺蘇生、抗菌薬の強力な使用を「希望しない」と答えた割合は9割前後に上っていた。
また、迎氏によると、米国の介護施設入所の重度認知症患者323例を対象とした前向きコホート研究では、肺炎症状への抗菌薬投与が投与経路(経口、静注、筋注)にかかわらず無治療に比べ、死亡率を約80%減少させた。しかし、認知症患者の安楽さ(SM-EOLDスコア)は無治療に比べ、有意に悪化したとの結果も報告されている(Arch Intern Med 2010; 170: 1102-1107)。
日本における肺炎の疫学を踏まえ、2011年に日本呼吸器学会は従来のガイドラインでは対応が難しい「医療・介護関連肺炎(nursing and healthcare associated pneumonia; NHCAP)」を新たに策定し、診療ガイドラインを発表した。NHCAPは米国で提唱されたHCAPを参考に、在宅介護患者の医療行為関連肺炎を包括した日本独自の定義。
NHCAPガイドラインでは初めて、医学的適応に基づく重症度判定ではなく「治療区分」の考え方が導入された。これはNHCAPや院内肺炎の多くに誤嚥性肺炎や疾患終末期、老衰が含まれること、こうした患者への強力な治療が時に必ずしも有益なことだけではないと考えられるケースが少なくないとの倫理的な配慮を踏まえた考え方だ。具体的には、NHCAPと診断された場合、患者や家族をよく知る主治医が本人や家族の意向を尊重し、倫理面にも配慮しながらA-Dの4群に分類された治療の場(外来、入院・ICU)と治療内容を決めていくこととされた。
高齢者肺炎について、最近、日本で注目すべきデータが報告されている。門田氏らは、大分県の急性期病院に入院した65歳以上の肺炎連続症例を後ろ向きに解析。傾向スコアマッチングを用いて呼吸器専門医による治療を受けた群(68例)と非呼吸器専門医による治療を受けた群(182例)の予後を比較した。
呼吸器専門医が主治医となった治療群と、非専門医が主治医となって呼吸器専門医が週1回のカンファレンスで相談に応じた治療群との間に有意な生存率の差はなく、多変量解析では90日後の死亡リスクが寝たきりで約4倍上昇し、栄養状態良好の場合の同リスクはほぼ半減していた(Clin Respir J 2016; 10: 462-468)。門田氏は、この結果について「高齢者肺炎では必ずしも呼吸器専門医を主治医とする必要はないが、寝たきりと栄養状態良好など、本人の状態が予後に大きな影響を与えていることからチーム医療・ケアの重要性を示唆しているとも考えられる」と話す。
「NHCAPガイドラインを機に呼吸器専門医の間では、高齢者肺炎の位置付けに対する理解が深まっていったと思う」と迎氏。しかし、「高齢者肺炎の課題として、原因菌をたたくだけでは治癒が困難なこと、そしてそのことを周りの家族や医療者側すらも理解していないことがある」とも指摘。「新規抗菌薬の開発や医療の発展が高齢者肺炎にあまり恩恵を与えていない可能性があることは、広く認識されていくべき」と話す。
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
以上の見解を日本中の介護施設、介護者など多くの人に知って欲しい。(拡散希望)
そして、肺炎裁判で老健施設を裁いた裁判官にも届いて欲しい。→こちら
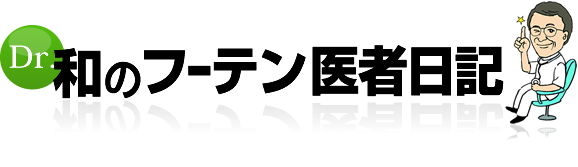



 応援クリックお願い致します!
応援クリックお願い致します!




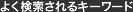




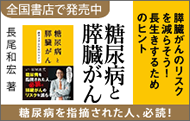







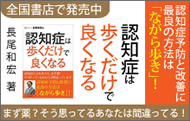

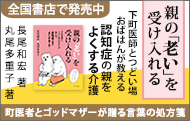
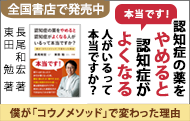


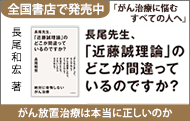
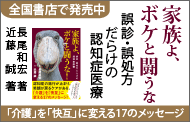
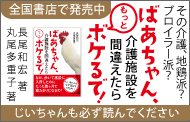

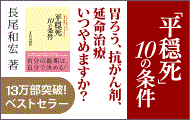
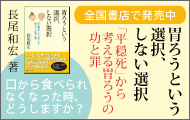


コメントする
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL: